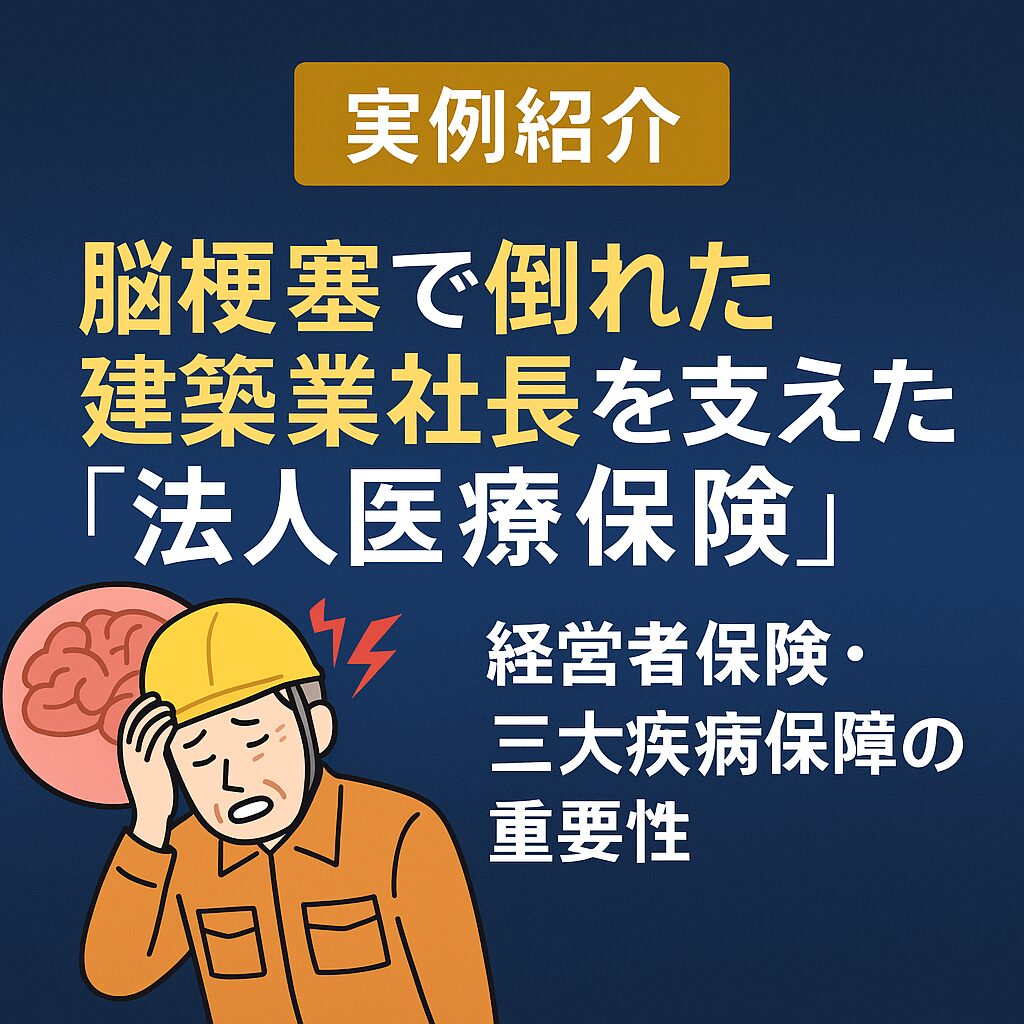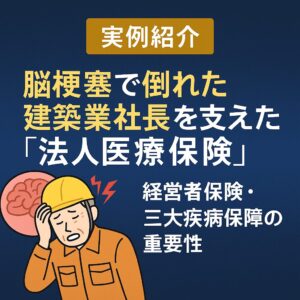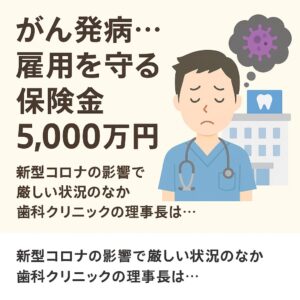総合福祉団体定期保険に入るべきか?会社や従業員に対するメリット・デメリットは?どんな種類はあるか?解説いたします。


個人の保険だけでなく企業保険をおすすめされることがあるかと思います。
ただ、個人保険と比較すると企業保険は普段あまり仕組みを聞くことがないですので、わかりにくい点もあります。
この記事では『企業保険の会社や従業員に対するメリット・デメリット?』
『企業保険の種類?』
『企業保険と総合福祉団体定期保険の違い?』
『総合福祉団体定期保険に入るべきか?』
など、普段はなじみのない企業保険に関する質問に対してわかりやすく解説して行きます。
目次
企業保険とは
まず、企業保険とはどういうものなのかについて解説します。企業保険とは、企業活動に伴うさまざまなリスクから、役員や従業員、企業そのものを守るための保険の総称です。企業は日々の業務の中で、火災・事故・労災・損害賠償・情報漏洩・自然災害など、さまざまなリスクにさらされています。こうした事態が発生したとき、予期せぬ多額の出費や経営への打撃を最小限に抑えるのが企業保険の重要な役割なのです。
企業保険の主な目的
企業保険をどのような目的で加入するのかについてざっくりと整理すると、下記のようになります。
| 目的 | 説明 |
|---|---|
| 経営リスクの軽減 | 思わぬ事故や災害があっても保険金で損害をカバーし、経営の安定化を図ることができる。 |
| 従業員とその家族の安心 | 業務中のケガや病気などに備え、福利厚生の一環としても重要。 |
| 法令遵守 | 一部の保険(例:労災保険など)は法律で加入が義務付けられている。 |
| 企業イメージの向上 | 安全・安心を重視する姿勢が、顧客や取引先からの信頼にもつながる。 |
補償されるリスクの具体例
企業保険は、以下のようなリスクに対する備えが可能です。
💼 従業員が労働災害・通勤災害によって、傷病を負ってしまうリスク
🧑⚖️ 取引先や第三者からの損害賠償請求リスク
📦 製造した製品の欠陥に起因するリスク(たとえばPL責任など)
💻 サイバー攻撃や情報漏洩リスク
🚚 輸送中の貨物の破損や盗難のリスク🏢 営業停止による利益損失リスク
⚠️ ハラスメントや不当解雇による訴訟リスク
👨💼 役員・経営陣が訴えられた場合の責任補償リスク
業種によっては必ずしも必要でないリスクもありますが、最低限まずは上記のようなリスクを想定し、補償の可否を検討すべきといえます。
企業保険の主な種類、分類
企業保険は様々なリスクに対応できることがわかりました。
ここではこのような特性をもつ企業保険をさらに深堀して、カテゴリー分けしていきたいと思います。企業保険は大きく分けると、以下の5つのカテゴリーに分類できます。
・物(建物・設備・在庫など)に関する保険
・賠償責任に関する保険(第三者から訴えられた場合)
・収益・経営リスクに関する保険・車両・輸送に関する保険
以下、それぞれについて解説していきます。
人(従業員や役員)に関する保険
| 保険の名称 | 主な目的・内容 |
|---|---|
| 労災保険(法定) | 労働者が業務や通勤に起因して負傷・疾病・死亡した場合に国が補償するもの。 |
| 業務災害補償保険(労災上乗せ) | 法定の労災保険だけでは不十分な補償を企業側が上乗せして補償する保険。 |
| 団体傷害保険 | 役員や従業員の事故・病気による入院・死亡などを補償。個人向けの傷害保険を法人が契約者、補償対象者を役員、従業員としたたもの。 |
| 使用者賠償責任保険 | 業務災害を被った従業員が安全配慮義務違反等を理由に、企業に対して訴えを起こした際に発生する弁護士費用や法律上の損害賠償金などを補償するもの。 |
| 雇用慣行賠償責任保険 | ハラスメント・不当解雇・差別などで訴えられた場合の損害賠償金・訴訟費用を補償するもの。 |
物(建物・設備・在庫など)に関する保険
| 保険の名称 | 主な目的・内容 |
|---|---|
| 火災保険(企業向け) | 自社の建物や設備、什器、商品などが火災や落雷、風災、水災といった自然災害で損害を受けたときに補償するもの。 |
| 動産総合保険 | 工場や店舗の設備、機械などが損害を受けたときに補償するもの(火災保険とは違い、補償の対象を特定する必要がある)。 |
| 機械保険 | 生産設備や精密機械が故障・事故によって損害を受けた場合に補償するもの。 |
| 建設工事保険/組立保険 | 建設工事の現場での建物・設備の損害を補償するもの(建設業・設備業向け)。 |
賠償責任に関する保険(第三者から訴えられた場合)
| 保険の名称 | 主な目的・内容 |
|---|---|
| 施設賠償責任保険 | 店舗や事務所施設の管理不備や業務遂行に起因して、他人にケガを負わせた、物を壊した場合の賠償責任を補償するもの。 |
| 生産物賠償責任保険(PL保険) | 製造・販売した製品が原因で他人に被害を与えたときに補償するもの。 |
| 請負業者賠償責任保険 | 工事中の事故で第三者に損害を与えた場合に補償するもの(建設業など)。 |
| 情報漏えい保険/サイバー保険 | 顧客情報の漏洩やサイバー攻撃による損害・訴訟費用などを補償するもの。 |
| 専門職業賠償責任保険 | 士業(弁護士・税理士・設計士など)やIT企業が専門業務ミスで訴えられたときに補償するもの。 |
収益・経営リスクに関する保険
| 保険の名称 | 主な目的・内容 |
|---|---|
| 利益保険/休業補償保険 | 火災や事故によって営業停止になった際の、利益の減少を補償するもの。 |
| 取引信用保険 | 取引先の倒産等による、売掛金の未払いなどによる損失を補償するもの。 |
| 役員保険(D&O保険) | 役員個人が会社経営の責任で株主や第三者から訴えられた場合の補償。 |
車両・輸送に関する保険
| 保険の名称 | 主な目的・内容 |
|---|---|
| 自動車保険 | 社用車での業務中の事故に関する社用車そのものの損害や第三者に対する賠償を補償するもの。 |
| 貨物海上保険/運送保険 | 商品を輸送中の事故・破損・盗難などの損害を補償するもの。 |
| 運送業者貨物賠償責任保険 | 運送業者が顧客の貨物を事故で損傷・紛失した場合の賠償を補償するもの。 |
総合保険団体定期保険とは
これまでに、企業保険は様々な種類があることを解説しました。
その中でも、人(従業員や役員)に関する保険の代表例である総合福祉団体定期保険について、ここでは詳しく説明したいと思います。
総合福祉団体定期保険は、企業が従業員の万一に備えて加入する生命保険の一つで、従業員・役員の福利厚生目的として、様々な企業が活用しているものです。
特徴と仕組みの概要
総合福祉団体定期保険の特徴と仕組みをまとめると、下記のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者 | 企業や団体(法人) |
| 被保険者 | 企業に所属する役員や従業員(パート・アルバイトを含めることもできる) |
| 補償内容 | 死亡・高度障害保険金 |
| 保険金受取人 | 原則、企業(企業が従業員の遺族に弔慰金として支給するため)※特約を付帯することで役員・従業員の遺族を指定することもできる。 |
| 保険期間 | 通常1年ごとに更新(定期保険) |
| 保険料 | 契約者(法人)が全額負担 |
| 団体扱い割引 | 単独に契約するよりも割安な保険料設定となっている。 |
| 加入の条件 | 原則として、従業員全員を対象とすることが求められる(任意選択は不可)。※企業全体の公平性や福利厚生の観点による。 |
| 税制上のメリット | 保険料の一部または全額が損金算入可能(契約形態による) |
保険会社によって細かい部分で差はありますが、基本的には上記の構造となっています。
その他、入院特約や医療特約、介護特約などオプション追加が可能な場合もあります。
補償内容についての詳細は後ほど解説します。
企業がこの保険を導入する目的
総合福祉団体定期保険を導入する目的は、以下の4つにまとめることができます。
💸企業の財務負担軽減
📋労災ではカバーできない部分の補填
📈税務上のメリット
それぞれについて解説していきます。
福利厚生の充実
従業員、役員が万が一の際の経済的補償がカバーされていることで、家族への安心感を提供することができます。
総合福祉団体定期保険の保険料負担は法人であるため、実質的には無料の補償となります。
このような福利厚生の充実は、従業員の定着率・満足度向上にも貢献し、ひいては優秀な人材の確保にもつながります。
企業の財務負担軽減
従業員や役員が万が一亡くなった場合、多くの企業は弔慰金規定に基づいて弔慰金や見舞金を支給します。
このような中、突発的な死亡が発生すると、数百万円単位の支出が一時的に発生します。
総合福祉団体定期保険に加入しておくことで、保険金で弔慰金や見舞金の支払いをカバーすることができるので、突発的な支出による財務への打撃を防ぐことができます。
労災ではカバーできない部分の補填
この点は、企業にとっても従業員やその遺族にとっても安心につながる制度設計であり、万が一の際の「セーフティネットの強化」として機能します。
そもそも政府労災の補償範囲は限定的であり、あくまで「業務上または通勤に起因して発生した傷病」に限って補償がされるものです。つまり、業務外のリスクには対応していないのです。
一方で、総合福祉団体定期保険は業務上・業務外を問わず、死亡や高度障害になった場合に保険金が支払われるため、仮に政府労災では対象外となってしまったケースも補償対象になります。
つまり「私的リスク」も含めて補償してくれるのです。
税務上のメリット
総合福祉団体定期保険は、契約者が法人であり、保険料を福利厚生目的で負担しているため、 その保険料は全額、法人の損金として計上できます。
このことは法人の課税所得を減らす効果があり、結果として 法人税の軽減につながることになります。
また一定の要件を満たすことで、支払保険料の経理処理が「福利厚生費」として認められるため、税務調査でも比較的扱いやすい保険商品といえます。
そのための主な要件を以下にまとめます。
・給与との関係がなく、選択制ではないこと
・保険金が就業規則や弔慰金規程に沿って遺族に支払われること
適切な契約形態にすることで、税務面においても様々なメリットがありますので、ぜひ参考にしてください。
主な補償内容
ここでは補償内容を少し掘り下げていきます。総合福祉団体定期保険もその他多くの生命保険と同様、主契約に特約を付帯することで補償範囲を拡張するという仕組みとなっています。それぞれについてみていきます。
【総合福祉団体定期保険の主契約】
・死亡保険金
・被保険者(従業員・役員)が保険期間中に死亡した場合に支払われます。
・死亡原因は問わず、病死・事故死・自殺なども対象(※免責期間や条件あり)。
・保険金の受取人は企業(契約者)であり、企業が保険金受取後、遺族に弔慰金や補償金として支給します。
(保険金の設定例)
一般職:500万円~1,000万円
管理職:1,000万円~2,000万円
役員:2,000万円~5,000万円
このように、役職に応じて設定金額に差を設けることは可能です。
・金額は死亡保険金と同額が設定されるのが一般的。
・一生働けなくなるような状態に備える補償で、本人または遺族の生活を支える目的。
【総合福祉団体定期保険の特約】
保険会社によって取り扱いは異なりますが、以下のような特約を付けることが可能です。
災害死亡特約
不慮の事故や特定感染症による死亡時に、死亡保険金に加えて上乗せされる。
障害特約
後遺障害に対する補償(障害の程度に応じた金額を支給)
入院・通院特約
病気やケガによる入院・通院に対しての定額給付
手術特約
指定の手術を受けた場合に一定金額を支給
がん特約
がんと診断された際に一時金を支給
主契約についてはどの保険会社でも共通した取り扱いになりますが、特約の有無は保険会社ごとに異なるので注意しましょう。
その他にも補償内容に制限がかかる場合がある等、注意すべき点があります。下記にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
【注意点(補償内容に制限がかかる場合)】
・自殺は免責期間(通常2年)経過後でなければ補償対象外。
・犯罪行為、重大な過失による事故、戦争行為など一部のケースは支払対象外。
・高齢者(70歳以上など)やパート・アルバイトは契約条件によって対象外または限定補償となる場合あり。
Q&A:企業保険に関する質問と、それに対する回答
最期に企業保険に関する質問と、それに対する回答をいくつか紹介します。
特に、総合福祉団体定期保険の導入を検討されている企業様は、ぜひ参考にしてください。
質問|企業保険のメリット・デメリットを教えて下さい。
企業保険のメリット・デメリットを教えて下さい。
会社で企業保険への加入を勧められました。
私は既に個人で生命保険と医療保険に加入しているので必要性を感じていません。
おそらく会社の福利厚生の一環なのかなと想像しています。
そもそも企業保険自体、あまり聞きなれない言葉なのでよく分かっていません。
企業保険の従業員に対するメリット・デメリット、会社に対するメリット・デメリットを教えて下さい。
回答:企業保険には2つあり、経営者向けの保険と従業員向けの保険があります。
経営者向けの保険は、経営者に万一のことがあっても、会社を継続して運営していけるように企業防衛の一環として経営者に掛ける死亡保障や医療保障をいいます。
一方で、従業員向けの保障は、従業員の福利厚生を主な目的として死亡保障や医療保障を備えることができます。
回答:保険料は全額企業負担であるケースが多いため、従業員の保険料負担がない点です。
企業保険のメリットは、保険料は全額企業負担であるケースが多いため、従業員の保険料負担がない点です。
従業員が保険料を支払う場合では、給与天引きで団体割引が適用されますので、少しお得に加入ができます。
いずれにしても、個人の保険料負担が軽減される点がメリットです。
回答:会社をやめて転職した場合などは、保障がなくなってしまう点です。
企業保険のデメリットは、その会社をやめて転職した場合などは、保障がなくなってしまう点です。
会社で保険に加入しているからという理由で個人の保険を解約してしまうと、その会社をやめるときに保障がなくなってしまいます。
加えて、会社をやめなくとも会社に業績が悪くなった場合には会社都合で企業保険を解約して保障がなくなったり、倒産してしまい保障がなくなることもありえます。
企業保険は会社にとってもメリットがあります。
企業保険の保険料は支払保険料あるいは福利厚生費として損金算入できますので、法人税の軽減につながります。
また、企業側で従業員のために福利厚生として保障を確保してあげることで、従業員の満足度などが上がり、長期雇用につながる可能性が上がります。
一方で、デメリットは企業保険の保険料が発生するので、業績が悪いときは資金繰りに影響が出てしまう点と、一度導入してしまうと従業員のモチベーションを維持することを考えると解約しずらいという点が挙げられます。
また、これはケースバイケースですが、体況が悪い社員(最近がんになってしまった方など)は保険加入が難しいため、従業員全員に企業保険を掛けてあげたくても、かけられないこともありえます。
その場合は、加入できなかった従業員が不公平感を持ってしまい、モチベーションの低下につながってしまうことも多少想定できます。

質問|企業保険は従業員は必ず入らなければならない義務がありますか?
企業保険は従業員は必ず入らなければならない義務がありますか?
転職をして先月から新しい職場で働き始めました。入社して会社から企業保険に関する説明が書かれた書類を配布されました。
正直いつ辞めるかも分からない会社の保険にお世話になるのは気が進みません。
企業保険は従業員がその会社に所属している限り、加入義務がありますか?拒否することは可能ですか?
また、拒否することで生じる弊害があれば知りたいです。
回答:企業側も強制はできませんので、拒否することは可能です。
企業側としては福利厚生として全員加入を前提に制度を設けていますので、よほどの事情がない限りは、一律で加入してほしいと考えているはずですが、企業側も強制はできませんので、拒否することは可能です。
拒否することで生じる弊害は、会社としては健康上に問題がなければ全員加入を前提としますので、拒否する理由を詳細にヒアリングされる可能性があり、いつ辞めるかもわからないのでという理由を知られた場合は、会社への忠誠心などは低いとみなされてしまったり、変わった方だという認識をされてしまう可能性があります。
加えて、健康上に何か問題があるのに、隠しているのではないかと疑われてしまう可能性もあります。
したがって、特別な理由がなく、保険料が全額会社負担なのであれば、加入手続きをしてしまうことをおすすめします。
保険料はそんなに大きな金額ではないので、会社にかけてもらっても、そんなに重いことではないですし、退職時に解約手続きをするのは会社側なので、従業員の事務負担もありません。
一方で、従業員が団体割引のきいたお得な保険料で加入できるタイプのものもあります。
こちらはお得に加入できることも多いですし、給与天引きなので支払い忘れもないのでよい制度なのですが、完全に任意加入ですので、普通に保険に加入するのと同じ感覚で検討して良いと思います。
また、団体保険はお得ですが、意外と色々な保険会社で比較をすると団体保険よりお得な保険というのはありますので、今回のご質問者様のように会社の世話になりたくないということでしたら、あえて会社で加入せずに、近くのFP事務所や保険代理店でお得なプランに加入するのがいいかもしれません。
質問|総合福祉団体定期保険に入るべきか?
総合福祉団体定期保険に入るべきでしょうか?
経営者様向けの回答と従業員様向けの回答をお願いいたします。
経営者様向けの回答:福利厚生制度の充実にはかなり良い保険制度になる
会社の福利厚生制度の充実にはかなり良い保険制度になると思います。
生命保険の商品で加入するよりも総合福祉団体定期保険で加入する事をお勧めします。
理由は、保障がよい点と保険料が生命保険会社が販売する保険より圧倒的に割安になる点です。
従業員様向けの回答:メリットはかなり大きい
総合福祉団体定期保険は、ある程度の会社規模や福利厚生が充実している会社が導入する保険になります。
ですので、メリットはかなり大きいと思います。
なお、従業員が個々に追加で医療保障や追加の保険にも加入できたりする制度もあるので確認して加入するのがよいです。
個人的な意見で言うと総合福祉団体定期保険の設置ある会社は羨ましいです。
質問|企業保険に入っていたら個人で医療保険や生命保険に入る…
企業保険に入っていたら個人で医療保険や生命保険に入る必要は無いでしょうか?
新入社員です。会社で企業保険について説明をされました。
私は保険に疎いのでとにかく何かの保証なんだなという程度の理解で終わりました。
私は保険については医療保険と生命保険ぐらいしか知りません。
企業保険はどちらに該当するのでしょうか。企業保険に入っていたら個人で医療保険や生命保険に入る必要は無いでしょうか?
回答:企業保険は死亡保障と医療保障の2種類がメインです。
企業保険は死亡保障と医療保障の2種類がメインです。まれに就業不能保険や所得補償保険などの休業補償まで手厚く保険を掛けてくれる会社もあります。
したがって、企業保険の内容は会社によりますので、しっかりと内容の確認をしてください。
会社の人事・総務の方に内容を聞いていただくか、そこで詳しく聞けないようなら企業保険の内容をFPや保険代理店に持ち込んで概要を教えてもらいましょう。
よく企業保険に加入すれば、個人保険は要らないかと聞かれますが、結論は最低限の部分は個人でも加入しておくことをおすすめします。
なぜならば、企業保険はその企業に属していなければ保障されませんので、会社をやめると保障がなくなってしまいます。
また、会社の業績が悪化すると福利厚生で導入した企業は保険を解約してしまうこともありえます。
そうなると保障がなくなってしまいますし、保障がなくなってから新しい保険に加入しようとしても、追加で保険に加入できるかはそのときの健康状態次第で、加入できないこともあります。
このような最悪の事態も想定して、最低限の部分は自分自身(個人)で加入しておくことをおすすめします。
質問|企業保険の種類を知りたいです。
企業保険の種類を知りたいです。
企業保険について会社で先日説明を受けた新入社員です。担当者の方が手厚く説明してくれたのですが、説明が長くて難しく頭に入ってきませんでした。
AグループやBグループという単語はうろ覚えですがなんとか聞き取れました。
しかし、AやBと聞いたところで中身が想像できないので混乱しています。
企業保険の種類は何種類あるのでしょうか?そしてそれぞれどのような商品なのかも教えて欲しいです。
回答:企業保険は保険会社ごとにも商品が異なります
企業保険は保険会社ごとにも商品が異なりますし、どのような保険を企業が選択しているかによって異なりますが、一般的には以下の企業保険が多く採用されています。
総合福祉団体定期保険
総合福祉団体定期保険:死亡保障・高度障害保障がメインで1年更新の定期保険。
会社が保険料を全額負担し、企業側で福利厚生費として損金計上。
保険金は従業員の遺族が受け取るが、ヒューマンバリュー特約を付加することで、企業側も人材の損失補填を行うことができる。
団体医療保険(総合福祉団体定期保険)
団体医療保険:入院・手術の保障がメインで、1年更新の定期医療保険。
会社が保険料を全額負担し、企業側で福利厚生費として損金計上。
保険金受取は従業員(被保険者)ご自身。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
団体長期障害所得補償保険(損害保険):休業補償(医師の診断で休業せざるを得ない状態が続いている場合に一定の範囲内で給与を補償する保険)
特約で精神疾患による休業まで補償できるようにできる商品もありますので、企業では一般的に精神疾患までサポートをしたいと考えて、精神疾患までカバーできるような商品を選択している傾向があります。
今回の質問にあるAやBはご自身で備えるタイプ(団体で加入して保険料は従業員負担)だと思いますので、傷害保険や団体定期保険で保険金額や特約を選択する野だと思います。
企業保険は一般的に企業が保険料を負担するものが多いですが、プラスアルファとして従業員が給与天引きで割り引かれた団体保険料を支払うパターンがあります。
従業員側も団体割引でお得に保険加入できますので福利厚生としてもおすすめですが、こちらは従業員側で保険金額などを選択して任意で加入するものなので、ご自身に合っている保障かをよく検討した上で加入しましょう。
質問|企業保険と団体保険の違いは何ですか?
企業保険と団体保険の違いは何ですか?
ずっと親の家業を手伝っていたので自営業として生きてきました。昨年、そのお店を畳んで別の会社の従業員として働き始めました。
会社から団体保険についての説明をされました。昔、雑談ではありますが知り合いから企業保険についての話をされたことがあります。
響きが似ているので同じものなのかなと思っているのですが、企業保険と団体保険の違いは何ですか?
回答:企業保険には経営者向けの保険と従業員向けの保険があります。
企業保険には経営者向けの保険と従業員向けの保険があります。
時には個人事業主向けの保険も企業保険と呼ばれることもありますので、企業保険は企業で活用する保険という広義の意味で使用されているケースが多いです。
一方で団体保険は経営者・従業員全員で掛ける保険で、保険金の受取人は従業員あるいは従業員の遺族で設定された保険です。
団体保険にも会社が完全に保険料を負担するパターンと従業員が割引された保険料でお得に給与天引きで加入できる保険の2種類があります。
前者は原則全員加入で、企業側が支払保険料を福利厚生費として全額損金計上します。
後者は従業員が任意でプランを選択して給与天引きで加入できます。
これは給与天引きで加入できるだけですので、保険代理店などでより条件の良いものかなどを探してもいいかもしれません。
もしも、後者の給与天引きで任意加入するタイプの団体保険であれば、その内容をFPや保険代理店に持ち込んで、より条件のよいものがないかなどを相談してみましょう。