築古アパート火災保険が加入できる?できない?賃貸オーナーが知っておきたい火災保険のポイント

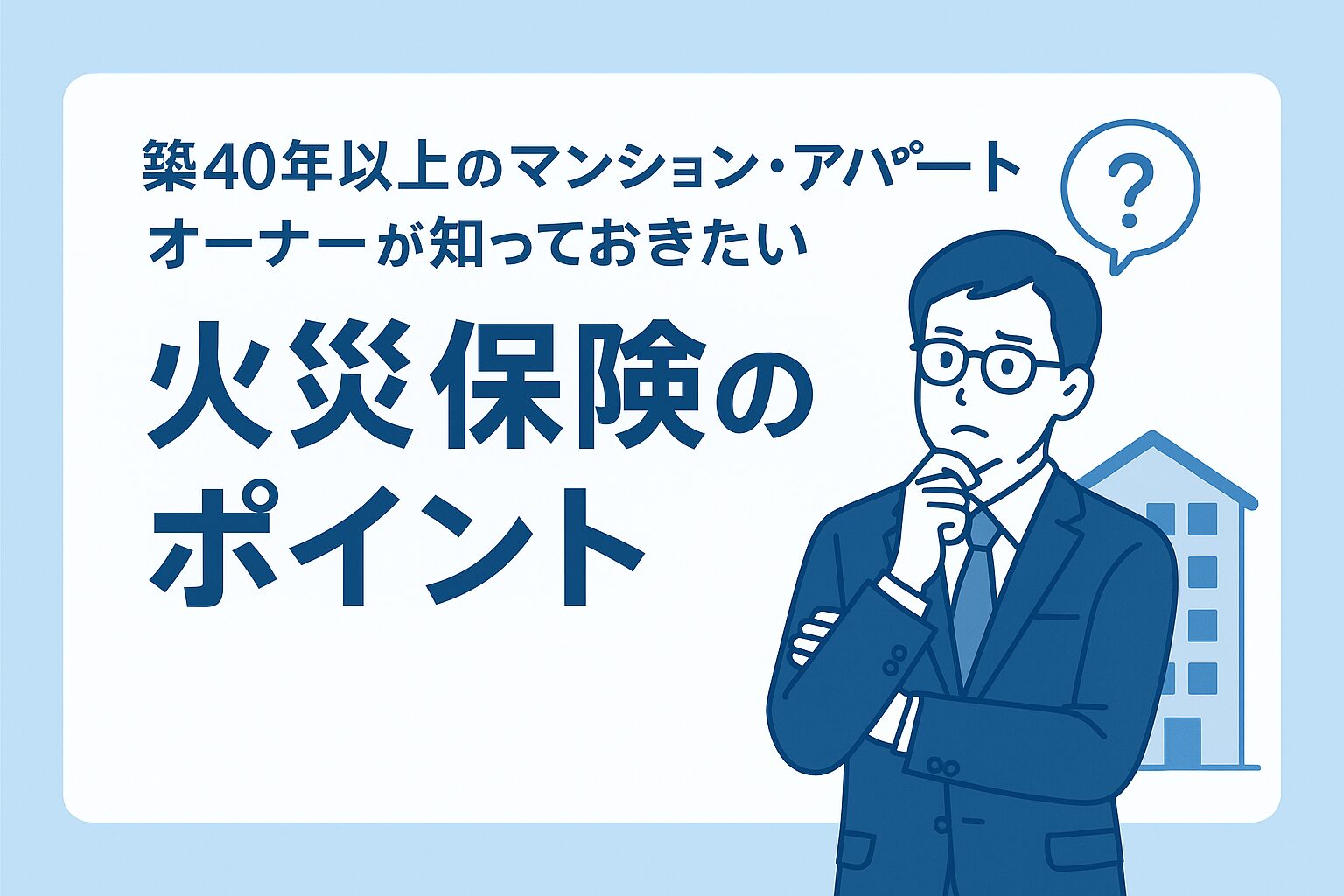
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
近年、日本各地で「築年数の古いマンション・アパート」を所有するオーナーが増えています。
特に築40年以上の物件では、建物や設備の老朽化が進み、火災・漏水・自然災害による損害リスクが高まっています。
いざ火災保険に加入・更新しようとすると、「保険料が想像以上に高い」「築年数を理由に、そもそも引き受けを断られた」といった声も少なくありません。
保険会社の立場からみれば、築古物件は災害・事故の発生確率が高く、保険金支払に至る可能性が大きい「ハイリスク物件」です。
そのため、できるだけ補償を引き受けたくないという判断になりがちです。
そこで本記事では、保険会社側の事情も踏まえながら、築40年以上の築古賃貸物件オーナーが火災保険を検討する際に押さえておきたいポイントや、契約時の注意点・コストを抑えるコツなどを、事例を交えて詳しく解説します。
目次
築40年以上の物件に火災保険が必要な理由
筆者が築年数の古い賃貸物件のオーナーと火災保険の更新について打ち合わせをしていると、かなりの確率で次のような言葉を耳にします。
「もう古い建物だから、全焼しても仕方がないよ」
「こんな古い物件に価値なんてない。火災保険は高いだけだし、掛けるだけ損だ」
ハッキリお伝えすると、これは大きな誤解です。
火災保険は、「建物を建て直すための保険」だけではありません。
• 入居者への対応費用
• 隣家や近隣への賠償責任
• 修繕期間中の家賃収入の減少
など、賃貸経営そのものを守るための重要なリスク対策でもあります。
特に築年数の古い物件では、次のようなリスクが高まります。
・配線・配管の老朽化による火災や漏水
・屋根・外壁の劣化による雨漏り・風災被害
・地震や台風による倒壊・損傷リスクの増加
・入居者や近隣住民への損害賠償リスクの高まり
これらの損害は、場合によっては数百万円〜数千万円規模に達します。
もし火災保険に加入していなかったり、補償内容が不十分であったりすると、その損害がそのままオーナーの経営を直撃することになります。
次項では、筆者が実際に対応した「築古物件での保険金支払い事例」をご紹介します。
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
築古物件における保険金支払い事例
事例①:老朽化したアパートでの電気配線火災(築45年・木造2階建)
<物件概要>
所在地:東京都内
築年数:45年
構造:木造モルタル2階建(延床面積200㎡)
用途:賃貸アパート(6世帯)
<火災保険加入条件>
建物:〇 保険金額 2,000万円
家財:-
補償リスク:火災・落雷・破裂・爆発・風災・盗難など(水災除外)
<事故発生原因>
老朽化した屋内配線(コンセント付近の被覆劣化)からショートが発生。
1階の一室から出火し、屋根裏まで延焼した。
<損害内容と保険金の支払い>
建物修理費用:約1,500万円
仮住まい費用補償(入居者一時対応費):約100万円
→ 合計約1,600万円を保険金として支払い。
<ポイント解説>
・築古物件のため、「再調達価額」ではなく「時価額」での支払い。
(修理額1,800万円に対し、経年劣化分を差し引いた結果、支払額は1,600万円)
・電気配線そのものの劣化は「老朽化による故障」で補償対象外だが、
そこから発生した火災による損害は補償対象として認定。
築年数が古くても、「火災という事故」が発生すれば、しっかり保険金が支払われる好例です。
事例②:築50年マンションの給湯器爆発による火災(RC構造)
<物件概要>
所在地:大阪府
築年数:50年
構造:鉄筋コンクリート造
用途:分譲マンション(オーナー所有の1室を賃貸)
<火災保険加入条件>
建物:〇 保険金額 800万円
家財:-
補償リスク:火災・落雷・破裂・爆発・風災・盗難・破損汚損(水災除外)
家主費用補償特約を付帯
<事故発生原因>
経年劣化したガス給湯器が内部漏れを起こし、点火時に爆発。
浴室と隣接する壁・天井が焼損した。
<損害内容と保険金の支払い>
建物修復費用:約250万円
家主費用補償(入居者退去対応費・原状回復までの家賃損失):約50万円
→ 合計約300万円を支払い。
<ポイント解説>
・RC造は構造がしっかりしているため、築古でも全焼に至らないケースが多い。
・給湯器の爆発事故も「火災保険の爆発・破裂補償」の対象。
・契約方式が「時価払い」ではなく「再取得価額方式」だったため、
老朽化控除なしで満額補償となった。
事例③:築43年木造貸家の台所火災(調理中の出火)
<物件概要>
所在地:名古屋市
築年数:43年
構造:木造平屋
用途:賃貸住宅
<火災保険加入条件>
建物:〇 保険金額 800万円
家財:-
補償リスク:火災・落雷・破裂・爆発・風災のみ(時価額契約)
<事故発生原因>
入居者がガスコンロで調理中に油へ着火。
台所と天井が焼損し、他の部屋も煙・スス被害を受けた。
<損害内容と保険金の支払い>
建物修理費用:約900万円(再調達価額ベース)
保険金支払額:約600万円(時価評価)
入居者への修繕費請求分を家主責任保険で補填:50万円
→ 合計約650万円が支払われた。
<ポイント解説>
・築40年超のため、保険会社側が「時価払い契約」を設定。
・評価額が低く、修理費用を満額カバーできなかった。
・保険金で屋根や内装の一部は修繕できたが、残りはオーナー負担となった。
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
事例④:築47年木造長屋の放火被害
<物件概要>
所在地:福岡県
築年数:47年
構造:木造長屋建(4戸連棟)
用途:貸家
<火災保険加入条件>
建物:〇 保険金額 800万円
家財:-
補償リスク:火災・落雷・破裂・爆発・風災・水災(時価額契約)
<事故発生原因>
隣家からのもらい火(放火)による火災。
連棟のうち2戸が全焼、残り2戸も半焼となった。
<損害内容と保険金の支払い>
建物評価額(時価):1,200万円
修繕・再建費用:1,800万円
→ 支払保険金:1,200万円(契約上の上限額)
残り600万円はオーナー自身の負担となった。
<ポイント解説>
・放火は火災保険の代表的な補償対象。
・しかし「時価契約」の場合、再建費用に足りないケースが多い。
・この事例では、オーナーは再調達価額契約が可能な保険会社への乗り換えを検討することになった。
築古物件は火災保険の加入を断られる? 保険会社の審査の仕組み
築年数40年を超える建物は、保険会社から見ると「災害などで保険金支払いに至る可能性が高い物件」です。
そのため、新築・築浅物件と比較すると、火災保険への加入・更新のハードルが高くなります。
保険会社が火災保険の加入可否を判断する際、特に重視するポイントは次のとおりです。
【審査項目と評価のポイント】
・建築構造
…鉄筋コンクリート造(RC)は比較的リスクが低く有利。
木造は火災リスクが高く、厳しく評価される傾向。
鉄骨造はその中間。
・修繕履歴
…外壁・屋根・配管などの改修履歴の有無。
直近で大規模修繕が行われていると、プラス評価になる場合もある。
・設備状況
…電気・ガス・給排水設備が古いままか、更新済みか。
更新時期も重要なチェックポイント。
・入居状況
…空室率、管理体制、清掃状況なども総合的に評価される。
特に、修繕履歴やメンテナンス記録が整備され、定期的な点検・改修が行われている物件は、「管理状態が良く、リスクが抑えられている」と判断されやすく、審査が通りやすくなります。
逆に、老朽化が進んでいるにもかかわらず改善が行われていない場合、保険料の割増や、最悪の場合は引き受け拒否となるケースも少なくありません。この点について、次の項でさらに詳しく見ていきます。
築古物件の火災保険引き受けの現実
築40年以上の賃貸マンション・アパートを所有するオーナーから、近年よく聞く悩みが、
「火災保険が更新できない」
「新規契約を断られた」
というものです。
これは、リスク管理の観点からオーナーにとって非常に大きな問題です。
筆者も仕事柄、多くの建物オーナーと話をしますが、実際に次のような相談を受けることが増えました。
「知り合いの物件オーナーが火災保険の更新で困っている」
「築古物件でも加入できる保険会社はないか?」
「引き受けてくれる先があれば紹介してほしい」
かつては、築年数の古さだけを理由に火災保険の加入を断られるケースはほとんどありませんでした。
しかし近年は、更新時に「築年数が古いため、今回は引き受けを見送らせていただきます」と言われる事例が、決して珍しくなくなってきています。
ここでは、なぜ築古物件の火災保険引受けが難しくなっているのか、その背景とオーナーが取るべき現実的な対策を解説します。
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
なぜ築40年以上の物件は火災保険の引き受けが制限されるのか
以前は、築年数だけで加入を断られるケースはほぼありませんでした。
しかし現在は、築30年を超えたあたりから保険会社が慎重な姿勢を取るケースが増加しています。
背景には、次のような要因があります。
(1)老朽化による事故リスクの増大
築40年以上の建物では、配線・配管・防水などの設備が劣化しており、火災・漏水・漏電事故の発生率が新築物件の数倍とも言われています。
特に問題になるのは、
・絶縁劣化による漏電火災
・給排水管の腐食による漏水損害
・雨漏りや屋根崩落などの風災事故
などです。保険会社から見ると、築古物件は「事故発生リスクが高く、保険料収入より支払が上回りやすい契約」となりやすいため、どうしても引受けに慎重になってしまうのです。
(2)自然災害の増加と保険金支払いの急増
近年、日本では台風・豪雨・地震などの自然災害が頻発しています。
火災保険は火災だけでなく、風災・水災・雪災なども補償対象とするため、保険金支払額は年々増加傾向にあります。
特に古い建物は耐風・耐水性能が低く、「築古=自然災害で損害が出やすい(=保険金支払いが高額になりやすい)」という構図になっています。
このため、保険会社は築古物件を「高リスク物件」と位置付け、一定築年数を超えると新規引受けを停止する方針を取るようになりました。
(3)保険料率の上限と収益性の問題
火災保険料は、金融庁の認可された料率範囲内でしか設定できません。
つまり、築古物件のリスクがどれだけ高くても、それに見合うだけ保険料を上げることはできないのです。
その結果、「リスクに見合う保険料で引き受ける」ではなく、「そもそも引き受けない」という判断が増えています。
実際に増えている「契約更新の拒否」「補償内容の縮小」の事例
実務の現場では、次のようなケースが実際に報告されています(一部は筆者が対応した事例です)。
・築45年の木造アパート:契約更新時に「建物老朽化」を理由に火災保険の引受けを停止。
・築43年の鉄骨造マンション:風災・水災補償を削除した条件でしか更新を認めない方針に変更。
・築50年のRC造マンション:火災のみ補償の「特別条件付き契約」でしか加入できない。
筆者は複数の保険会社の商品を扱う乗合代理店のため、こうしたケースでは他社の火災保険を提案し、無保険状態を回避してきました。
しかし中には、満期日までに代替保険が見つからず、無保険状態を迎えてしまうオーナーも増えています。
この場合、万一火災が発生すると損害はすべて自己負担となり、賃貸経営にとって致命的なダメージになります。
保険会社が引き受けを検討する条件
築古物件であっても、一定の条件を満たせば引き受けを検討してもらえる余地はあります。
本記事前半でご紹介したとおり、ポイントは「建築構造」「修繕履歴」「設備状況」「入居状況」です。
・構造がしっかりしている(RC造など)
・定期的な修繕やメンテナンスを実施している
・設備更新の記録がある
・管理体制が整っている
といった点を丁寧に説明できれば、火災保険の引き受けを勝ち取れる可能性は十分あります。
交渉にあたっては、保険会社よりも、まずは信頼できる保険代理店に相談するのがおすすめです。
代替策としての「共済」や「地域密着型保険会社」
大手損害保険会社での引き受けが難しい場合、次のような代替策も選択肢に入ってきます。
都道府県民共済・全労済などの共済系保険
築年数による制限が比較的緩く、審査も柔軟なケースが多い。
地元信用金庫系・JA共済などの地域密着型保険
地元物件の引受け実績があり、築古物件にも対応していることがある。
特約火災保険(特定条件付き)
一部補償を限定する代わりに、古い建物も引き受けるタイプの保険。
ただし、これらは補償範囲や上限金額に制約があることも多いため、「最低限のリスクに備える保険」と割り切って利用するのが現実的です。
今後の保険市場とオーナーが取るべき対応
火災保険市場は、今後も築古物件に対して厳しい状況が続くと見込まれています。
2022年以降、火災保険の最長契約期間は「10年 → 5年」に短縮され、さらに2025年には、一部保険会社で築30年超物件の引受け制限が強化されました。
このような環境を踏まえると、オーナーが今すぐ取り組むべきことは次の3つです。
修繕記録・管理記録の整備
更新時に「安全管理が行き届いている物件」であることを示せるようにしておく。
複数の保険会社・代理店への同時見積もり
築年数の基準は保険会社ごとに異なるため、比較検討が必須。
「最低限の補償」を確保するという発想
完璧な補償を求めるのではなく、まずは「火災+賠償」を維持することを優先する。
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
築古物件でも引き受けてもらえる条件
ここまでお読みいただき、築古物件への火災保険引き受けがいかにハードルの高い状況にあるか、ご理解いただけたと思います。
とはいえ、一部の保険会社では、条件付きで築古物件の火災保険を引き受けているのも事実です。
以下は、筆者が情報収集した「築古物件の火災保険引き受けの目安」をまとめたものです。
実際の条件は変更される可能性もありますが、イメージとして参考になるでしょう。
(※社名は仮称)
A社:
・築40年以上/築年数不明:申請不要
・T/H構造の場合
1981年(昭和56年)5月以前の建物は保険期間1年のみ
※継続契約なら最長5年
・保険期間2年以上はWeb申込割引5%
・共同住宅は引受不可
B社:
・築40年以上/50年以上ともに保険期間1年
・所定の「引受チェックシート」全項目を満たせば、保険会社への個別照会不要
C社:
・築40年以上:引受制限なし
・築50年以上:
建物診断アプリを利用 → 診断結果に応じて引受
アプリを利用しない → 保険期間1年・火災風災リスクのみ・免責10万円必須
D社:
・築40年以上:引受制限なし
・築50年以上:建物診断ソリューションを実施することが最低条件
E社:
・築40年以上/50年以上ともに保険期間は原則1年
・1年超の契約には写真・チェックシートなど追加資料が必要
F社:
・築40年以上/50年以上ともに引受制限なし(ただし事故歴の申告必須)
・築古で建物のみ契約の場合、保険料は比較的安い
・メリット:
「不測かつ突発的な事故」特約を免責1万円で付帯可能
・デメリット:
月払契約は保険期間1年のみ、類焼損害補償特約は付帯不可
G社:
・築40年以上:引受制限なし
・築50年以上:専用チェックシートの提出が必要。診断結果により引受可否を判断
H社:
・築40年以上/50年以上ともに引受不可
築40年以上の築古物件に対する引受姿勢は総じて厳しいものの、条件次第では引き受けを行っている保険会社も存在します。
諦めずに、保険会社・保険代理店に相談してみることが重要です。
補償内容の選び方 ― 築古物件だからこそ「建物+家主賠償」を重視
築古物件でも引き受けてくれる保険会社が見つかったとして、次に重要なのは「どのような補償内容で契約するか」です。
築年数が経過した物件では、全損時の再建を100%カバーするよりも、実際に起こりやすい損害をしっかりカバーする設計が現実的です。
代表的な補償項目と、築古物件オーナーが重視すべきポイントを整理すると、次のようになります。
・火災・落雷・爆発…建物・設備の火災による損害を補償 重要度:★★★★★
・風災・雹災・雪災…台風・雪などによる屋根や外壁等の損傷を補償 重要度:★★★★☆
・水漏れ(給排水設備)…老朽化した配管の破損などによる漏水リスク 重要度:★★★★★
・水災…ゲリラ豪雨・河川氾濫等による浸水・洪水の損害 重要度:地域により★★★☆☆
・家主賠償責任保険…入居者・隣家への損害賠償を補償 重要度:★★★★★
・家賃収入補償…修繕期間中の家賃損失をカバー 重要度:★★★☆☆
なかでも、「家主賠償責任保険」は必須に近い補償といえます。
古い給水管の破損により階下へ水漏れを起こし、多額の賠償を求められるケースは決して珍しくありません。
数百万円規模の賠償責任が発生することもあり、火災保険でこのリスクをカバーしておくことは、賃貸経営の安定に直結します。
保険金額の設定は「時価」か「再調達価額」か
築年数が経過した物件では、保険金額(評価方法)の選び方も重要です。火災保険の補償方式には、大きく分けて次の2種類があります。
・時価保険方式…「再建費用 - 経年劣化分」を補償。
→保険料は安くなるが、支払われる保険金は少なくなる。
・再調達価額保険方式…同種同等の建物を新築するための費用を補償。
→保険料は高くなるが、実際の再建には有利(補償が手厚い)。
築40年以上の築古建物では、時価額が極端に低く見積もられるケースも多く、**「時価契約だと、いざというときに補償が全く足りない」**という事態になりかねません。
一方で、「全焼時の建て替えまでは想定せず、一部損害の修繕費用をカバーできれば良い」という考え方もあります。
物件の状態や経営方針に応じて、保険会社・代理店とよく相談しながら、現実的な保険金額を設定することが大切です。
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
築古物件の保険料を抑える3つのコツ
築年数が古い物件では、どうしても保険料が高くなりがちです。そこで、次のような工夫で保険料コストを抑えることができます。
必要な補償に絞る
ハザードマップや近年の災害履歴を確認し、不要と思われる補償(水災など)は思い切って外すことで、年間数万円単位で保険料を抑えられることもあります。
免責金額(自己負担)を設定する
損害保険の基本は、「滅多に起きないが起きると大きい損害」に備えることです。
小さな損害は自己負担とし、ある程度の金額以上の損害のみ保険でカバーする設計にすることで、保険料を抑えつつ、大きな事故には備えることができます。
複数の保険会社を比較する
保険会社ごとに、重視するリスクや料率設定が異なります。
水災リスクに厳しい会社もあれば、風災を重く見る会社もあります。築古物件への考え方も会社ごとに違うため、必ず複数社の見積もりを比較することが重要です。
共済系・地銀系代理店など、築古物件に比較的前向きな会社を探すのもポイントです。
保険更新時の「見直し」を怠らない
火災保険は、一度加入したら終わりではありません。最低でも5年ごと、できれば更新のたびに見直しを行うことが大切です。
近年は、自然災害の増加や建築資材費の高騰などの影響で、保険料・補償条件が頻繁に変わっています。
また、物件の修繕やリフォームを行った際には、
・保険金額が実態に合っているか
・補償内容が現状に適しているか
を必ず確認しましょう。「前と同じ条件だから」と何も考えずに更新してしまうと、いざ事故が起きたときに保険金が足りないという事態にもなりかねません。
Q&A:築古物件オーナーから寄せられた質問とその回答
最後に、実際に築古物件オーナーから寄せられた質問と、その回答をいくつかご紹介します。築古物件の火災保険を取り巻く“今”をイメージしやすくなると思います。
質問①:いま加入している火災保険が満期を迎えたけど、更新できないことはありますか?
私は築40年になるマンションを一棟所有しています。これまで大きな事故はなく、幸い保険を使ったこともありません。
万が一に備えて火災保険にはきちんと入っていますが、最近、同業者から「築古物件の火災保険の引き受けが厳しくなっている」と聞き、不安になりました。
今の保険が満期になったとき、更新できないということは本当にあるのでしょうか?
【回答】|築古物件では「更新拒否」が実際に増えています。
質問者様がおっしゃる通り、現在、火災保険の引き受けは厳しい状況です。
たとえ既契約者であっても、無条件で更新できるとは限りません。主な理由は次の通りです。
・台風や洪水など自然災害による損害率の上昇
・給排水設備事故の増加により、古い建物ほど保険金支払いが増えている
・保険会社がリスクの高い物件の引き受けを段階的に縮小している
実際、築35年を超えると「新規契約は不可・更新も原則不可」とする保険会社が増えています。
保険会社の立場からすると、ハイリスク物件を多く抱えると会社の収支バランスが崩れるため、やむを得ない経営判断ともいえます。
保険契約の更新拒否を回避するヒント
とはいえ、築古物件オーナーにとって火災保険は欠かせないリスク対策です。
契約の更新を勝ち取るために、最低限、次のポイントは押さえておきましょう。
・更新案内が届いたら、早めに保険会社・保険代理店へ相談する
・建物の修繕記録や点検記録を整理し、いつでも提出できるようにしておく
・もし更新が断られた場合でも、補償内容を縮小するなど条件を見直し、再査定を依頼する
こうした取り組みを行うことで、前年と全く同じ条件での更新は難しくても、無保険・無補償状態を避けられる可能性は十分にあります。
質問②:保険会社は築古物件のどこを特にチェックしているのですか?
私は複数の賃貸物件を所有しており、その中には築30年以上の「築古物件」も含まれます。
火災保険の引き受けが厳しくなっていると聞き、オーナーとしてできる対策があれば行いたいと考えています。
保険会社は、築古物件のどの部分を重視して引き受け可否を決めているのでしょうか?
【回答】|主要なチェックポイントは次の4つです。
保険会社が築古物件を審査する際に注目するのは、主に以下の4点です。
●ポイント①:電気系統(配線・分電盤)
・火災リスクが非常に高いため最重要。
・アース付きの新しいコンセントかどうか。
・コンセントの焼損履歴。
・ブレーカーの更新時期。
●ポイント②:給排水設備
・漏水事故の多くが給排水設備の不具合に起因。
・銅管の腐食、排水管の詰まり、パッキン劣化など。
●ポイント③:屋根・外壁の老朽化
・台風・豪雨時の損害が発生しやすい部分。
・コーキングの劣化、スレート屋根の割れ、雨樋の破損など。
●ポイント④:建築図面・修繕履歴の有無
・修繕履歴が不明な建物は、管理状況が悪いと見なされ評価が下がる。
オーナーとしては、これらのポイントを意識して計画的に修繕を行い、その履歴をきちんと残しておくことが、火災保険の引き受けを有利に進めるうえで非常に効果的です。同時に、こうした取り組みはそもそもの事故発生リスクを下げることにもつながります。
質問③:築古物件ではどんな補償を残すべきですか?
私は築40年を超えるアパートを所有しています。
先日、火災保険の更新案内が届いたのですが、正直、物件自体の価値は低いと感じており、保険料も安くありません。
築古物件は火災保険の引き受け自体も厳しいと聞くため、「最低限の補償だけ残せばよいのでは?」とも考えています。
こんな古い物件でも、絶対に残しておくべき補償はありますか?
【回答】|最低限、残すべき補償は2つあります。
いくら古い物件とはいえ、まったくの無保険・無補償でいるのは非常に危険です。
保険会社が引き受けてくれるのであれば、少なくとも次の2つの補償は残しておくべきです。
●備えるべき補償①:火災・落雷・破裂・爆発
火災保険の基本となる補償です。
火災は一度発生すると建物だけでなく、事業継続にも大きな影響を与えます。この補償を外す理由はほとんどありません。
●備えるべき補償②:賠償責任(個人賠償・施設賠償)
賠償責任の中でも、特に考えるべきは次の2種類です。
・個人賠償責任保険:漏水や設備故障などで階下や隣室に被害を与えた場合の補償。
・施設賠償責任保険:建物や設備の管理不備により第三者に損害を与えた際の補償。
築古物件では、設備トラブルによる賠償リスクが高く、場合によっては火災そのものより賠償事故のほうがダメージが大きいこともあります。
火災保険を検討する際は、この2つの補償だけは削らないよう注意しましょう。
まとめ:築古オーナーこそ、リスク管理を「保険」で補う
築40年以上のマンション・アパートは、長い年月の中で多くの入居者や家族を受け入れてきた、いわば“歴史ある資産”です。
一方で、火災・漏水・自然災害などのリスクは年々増しており、火災保険の引き受け環境も厳しくなっています。
火災保険は、「もしも」のときに賃貸経営を守る最後の防波堤です。
• 定期的な点検と修繕
• 修繕・管理記録の整備
• 複数社への見積もり・相談
といった日頃の取り組みと合わせて、信頼できる保険代理店と連携しながら、自身の物件に合った火災保険を確保しておくことが何より重要です。
築古物件オーナーにとって、火災保険は単なる「コスト」ではなく、資産と家賃収入を長期的に守るための経営戦略の一部だと考えていただければと思います。
築古や40年以上の物件でも加入できる、火災保険引き受けの基準が最も柔軟な保険会社 があります。
「他社で断られた」「更新できないと言われた」といったケースでもご案内できる可能性がありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /






とは?-いる・いらない?事例や適用範囲は国内-海外?-300x225.jpg)










