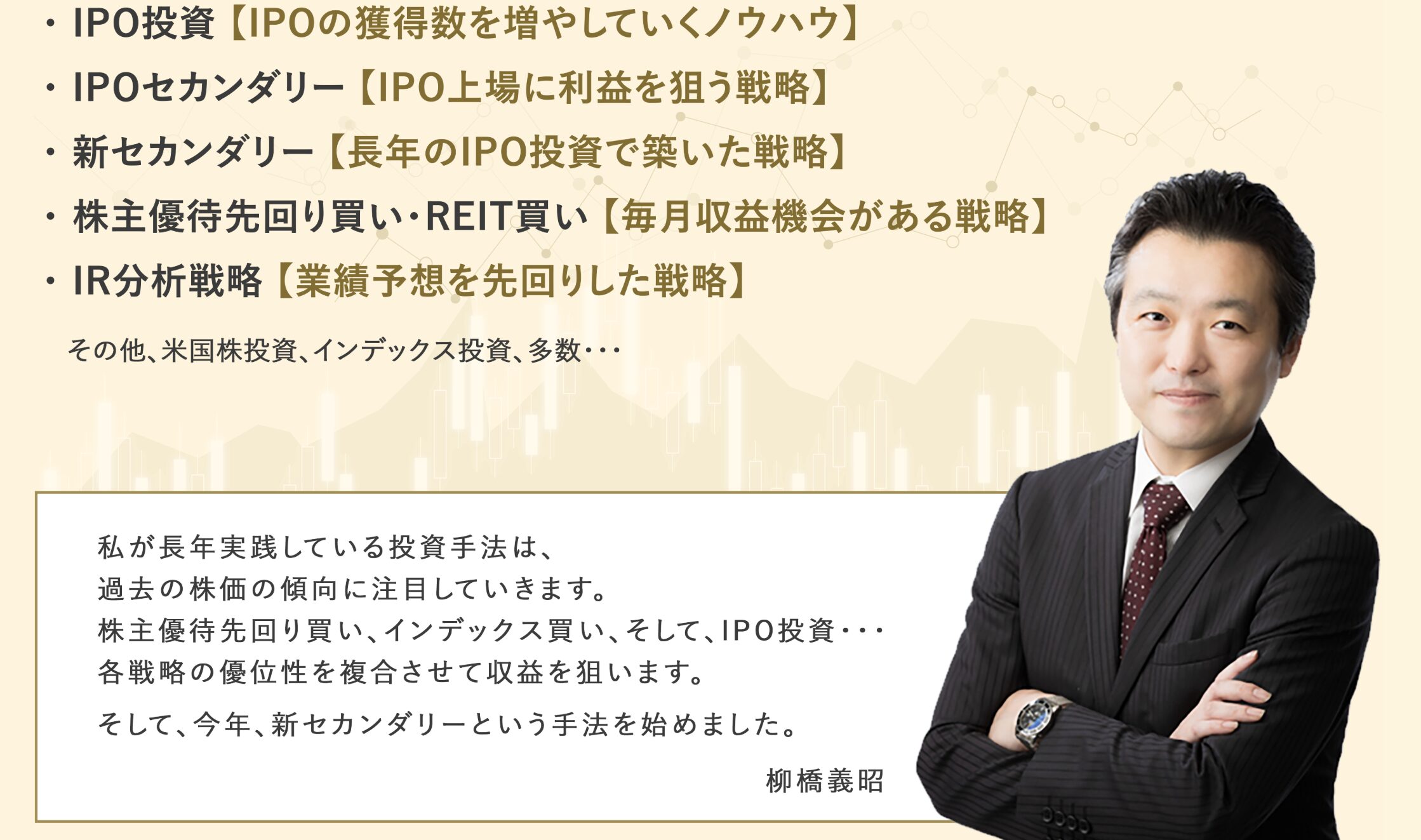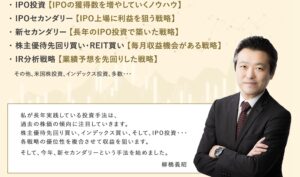退職金がない!積立を保険で行う?個人年金保険とは?資産運用をわかりやすく解説

退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク

老後の2000万円問題が話題になってから、今勤めている会社に退職金があるのか気になって調べたという方は増えています。
しかし、実際には退職金がほとんどない、あるいは、例え退職金制度があったとしても、老後の生活費は賄えるほどは退職金が出ないことがほとんどです。
そこで老後のために保険で積み立てを行おうとしている方が非常に増えていますので、老後の資金の積み立てを保険で行うのはどうなのかを解説していきます。
退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク
目次
老後資金の備えに生命保険が効果的な理由とは?
少子高齢化が進む現代社会において、老後の生活に対する不安は年々高まっています。
公的年金制度だけでは、豊かな老後を過ごすには不十分だと感じる人も多く、自助努力による資金準備の必要性が叫ばれています。
その中で注目されているのが、生命保険を活用した老後資金の形成です。
生命保険は本来、万が一に備えるための保障商品ですが、近年では資産形成の手段としても注目を集めています。
ここでは、個人が老後資金を準備するうえで、生命保険がどのように効果的なのかについて詳しく解説します。
生命保険が老後資金の準備に使える3つの仕組み
貯蓄型保険による資産形成
生命保険は、保険料の面で大きく「掛け捨て型」と「貯蓄型」と分類することができますが、老後資金として活用できるのは、主に貯蓄型保険です。
これは、保険料の一部が保険会社によって運用され、一定期間を過ぎると「解約返戻金」や「満期保険金」として戻ってくるという仕組みです。
たとえば「終身保険」は、その名の通り保障期間が終身にわたるタイプでありながら、保険料の払込期間を10年などと短期間に設定することができます。
こうすることで、加入から20年~30年後に解約すれば、払込保険料の総額を上回る返解約戻金を受け取ることができます。
これを老後の資金の一部として取り崩すという使い方が可能です。
また、「養老保険」では、一定期間(たとえば20年、30年など)満期を迎えると、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れることが特徴で、満期時にまとまった金額を確実に得られることから、老後資金として計画的に利用できます。
貯蓄型保険の最大の強みは、「保障」と「貯蓄」の両方を同時に満たせる点です。
途中で万が一のことがあれば死亡保険金が遺族に支払われ、保険期間を満了すれば積み立てた資金を受け取れる、という二重の安心が得られます。
ただし、一般的に掛け捨て型よりも保険料が高くなるため、長期にわたって無理なく払い続けられるかどうかを見極める必要があります。
また、途中で解約した場合は払込保険料総額に対して受け取ることのできる解約返戻金が少ない(元本割れ)ことになる可能性もあるため、資金を引き出す時期についても慎重に計画することが求められます。
個人年金保険で公的年金の上乗せ
老後の生活資金の柱といえば「公的年金」ですが、少子高齢化による財政圧迫が叫ばれていることもあり、その受給額だけで安心した老後を送るのは難しいと感じる人が増えています。
そこで注目されているのが、「個人年金保険」という保険商品です。
個人年金保険は、契約時に定めた年齢(たとえば60歳、65歳)以降に、一定の期間または一生涯にわたって年金として受け取ることができる仕組みの保険です。
受け取り方には
「一定期間受け取り型(例:10年間)」
「終身年金型」
「保証期間付き終身型」
などがあり、長生きした場合にも安定的な収入を確保できるのが特徴です。
この個人年金保険の大きなメリットは、なによりも公的年金の上乗せになるという点です。
これにより、公的年金だけでは不足しがちな生活費や医療費、介護費などを補完し、よりゆとりある老後を実現することが可能です。
また、個人年金保険は「円建て」と「外貨建て」があり、円建ては元本保証や安定性を重視する方向け、外貨建てはリターンを重視しつつ為替リスクも受け入れられる方向けの商品です。
いずれにしても、長期的な視野で資産を育てるという目的に適しています。
なお、保険料の支払期間中には「個人年金保険料控除」の適用があるため、所得税や住民税の軽減効果も期待できます。
これは、年収の高い人ほど効果が大きくなる傾向があります。
税制優遇のメリット
前項でも少し触れましたが、生命保険を老後資金の準備に活用するうえで、一つの大きな魅力となるのが税制上の優遇措置です。
日本の税制では、保険料の支払いに対して一定の控除が認められており、毎年の所得税・住民税の軽減が可能になります。
具体的に、生命保険料控除には以下の3種類があります。
・一般生命保険料控除:終身保険や定期保険などに適用される。
・介護医療保険料控除:介護保障付き保険や医療保険が対象。
・個人年金保険料控除:所定の条件を満たす個人年金保険に適用。
これらはそれぞれ所得税で最大4万円(住民税は2.8万円)まで控除され、合計で年間最大12万円(住民税は7万円弱)まで控除の対象となります。
これは、保険料を計画的に支払い続けることで、長期的に見れば数十万円~数百万円の節税効果を得ることが可能であることを意味します。
さらに、個人年金保険の年金受取時には「雑所得」として扱われますが、年金受取額から「公的年金等控除」や「基礎控除」などが差し引かれるため、実質的な課税対象額が抑えられることもあります。
これは、他の運用商品(たとえば投資信託や株式の売却益)と比べて、課税負担が軽くなりやすい点として注目されています。
ただし、税制は改正されることもあるため、加入時には最新の制度を確認し、税理士やファイナンシャルプランナーに必ず相談するようにしましょう。
退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク
銀行預金や投資との違いとは?
老後資金を準備するための手段として、私たちはさまざまな選択肢を持っています。
もっとも身近なものが「銀行預金」、そして運用益を狙う「投資」があり、さらには「生命保険」という保障と貯蓄を兼ねた金融商品です。
それぞれに長所と短所があり、自分のライフスタイルやリスク許容度に応じた適切な選択が求められます。
ここでは、銀行預金・投資・生命保険の違いについて、老後資金づくりの観点から比較していきます。
銀行預金:安全だが「増えないお金」
銀行預金は、元本が保証されている点において、非常に安心感のある資産形成手段です。
預け入れたお金が減ることはなく、万が一銀行が破綻したとしても、預金保険制度により元本1,000万円とその利息までが保護されます。
しかし、その一方で、現代の日本における金利は非常に低く、普通預金では年利0.001~0.02%程度、定期預金でも0.1%に満たないのが現状です。
たとえば100万円を1年間預けても、利息は100円〜200円にしかならないことになります。
また、インフレが進行した場合、銀行に預けたお金の「実質的な価値(購買力)」が目減りしてしまうというリスクがあります。
これは、インフレに対して預金が価値を維持できない、という「インフレリスク」です。
つまり、安全性は高いが、老後資金を「増やす」手段としては力不足といえるのが、銀行預金の特徴です。
投資:増える可能性があるが「不確実」
株式や投資信託、債券、不動産投資などの金融商品は、長期的に資産を増やす可能性があるため、老後資金づくりとしても注目されています。
実際、長期で見れば株式市場は右肩上がりの成長を見せており、年率数%~10%を超えるリターンが得られる場合もあります。
さらに、最近では「つみたてNISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」など、税制優遇を受けながら資産運用ができる制度も整っており、特に若年層にとっては投資が老後準備の有力な選択肢となっています。
しかし、投資には当然ながら「リスク」がつきものです。たとえば、株式市場が下落した場合、元本割れを起こす可能性が常にあります。
また、為替リスク、金利変動リスク、流動性リスクなど、さまざまな要因で資産価値が変動するため、知識や経験も必要です。
とくに老後間近や退職後のタイミングで相場が大きく下落した場合、「取り崩す予定だった資金が大きく減ってしまう」といったリスクは無視できません。
これは「タイミングリスク」とも呼ばれ、高齢者には大きな不安要素となります。
生命保険:「計画的に貯めながら、万が一に備える」
銀行預金や投資と異なり、生命保険は「保障機能」と「資産形成機能」を併せ持つユニークな金融商品です。
特に「貯蓄型保険」や「個人年金保険」を活用することで、将来に備えた計画的な貯蓄が可能となります。
大きな違いとして、生命保険には「強制力がある」ということが言えます。
たとえば、銀行預金であれば、いつでも引き出せるため、急な出費や衝動的な支出により貯蓄がなかなか増えないという問題があります。
しかし生命保険は、一度契約すれば一定期間の保険料支払い義務があるため、「半強制的に貯金を継続できる仕組み」として機能します。
さらに、万が一の際には死亡保険金が遺族に支払われるため、老後資金に限らず、家族への経済的サポートとしても効果的です。
保険は一般的にリスクをカバーするための手段とされますが、老後資金形成においては「安定性と計画性を重視する人に適した選択肢」と言えるでしょう。
| 比較項目 | 銀行預金 | 投資(株式・投信等) | 生命保険(貯蓄型) |
|---|---|---|---|
| 元本保証 | あり | なし | 一定期間後に解約返戻金あり(ただし中途解約は元本割れの可能性) |
| 増える可能性 | 低い | 高い(リスクも高い) | 中程度(安定的な増加) |
| リスク | ほぼなし | 市場変動・元本割れ | インフレ・中途解約リスク |
| 流動性 (使いやすさ) | 高い | 高い(市場により変動) | 低~中(中途解約に制限) |
| 税制優遇 | なし | つみたてNISA・iDeCo等あり | 生命保険料控除、個人年金保険控除あり |
| 精神的安定感 | 高い | 低~中 | 高い(保障付き) |
バランスの取れた「第3の選択肢」としての生命保険
上記の比較表の通り、銀行預金は安全だが増えず、投資は増える可能性があるが不安定であることがわかります。
この2つの間を補完する存在として、生命保険は「堅実さ」と「計画性」を兼ね備えた選択肢であると言えます。
特に、人生の後半に向けて「お金の安心感」だけでなく「万一の保障」も確保しておきたいと考える人にとって、生命保険は非常に効果的な手段となります。
もちろん、すべての資産を生命保険で準備するのではなく、銀行預金・投資・保険の3本柱でバランス良く備えることが理想的です。
リスクとリターン、流動性と安定性のバランスを見極め、自分に合った資産形成を考えることが、豊かな老後への第一歩となります。
退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク
生命保険を老後資金に活用する際の注意点
生命保険を老後の生活資金として活用することは、保障と貯蓄を兼ね備えているという点で非常に有効な手段ですが、「保険は一度契約すると長期間にわたって家計に影響を与える金融商品」という面もあります。
そのため、加入前に十分な理解と準備が必要不可欠です。
ここでは、生命保険を老後資金のために検討する際に押さえておくべき注意点を詳しく解説します。
中途解約による「元本割れ」のリスク
貯蓄型の生命保険や個人年金保険は、長期間継続することで利回りが安定し、解約返戻率が増加する設計になっています。
特に加入から5年未満等の短期で解約すると、「解約返戻金」が払い込んだ保険料を大きく下回る、いわゆる元本割れになることが多くあります。
たとえば、月1万円を5年間支払って60万円を積み立てた場合でも、5年目に解約すると返戻金が40万円程度にしかならないといったケースがあります。
これは、保険会社が契約初期に手数料や保険料の一部を差し引いているためです。
このため、契約期間の途中での見直しやライフプランの変更に弱いのが貯蓄型保険のデメリットのひとつです。
住宅購入や教育費の増加、収入の変動といった、将来の家計変動にも柔軟に対応できるよう、加入時には「何年払い続けられるか」「途中で引き出す可能性はあるか」といった点を十分に検討する必要があります。
インフレに対する弱さ
貯蓄型の生命保険商品は、契約時点で保険金やある程度の範囲で解約返戻金額が決まっている者がほとんどです。そのため、将来インフレが進行し、物価が大きく上がった場合には、受け取れる金額の「実質的な価値」が下がってしまうリスクがあります。
たとえば、今から30年後に1,000万円の返戻金を受け取れる契約を結んでいても、30年後に物価が1.5倍になっていれば、今の価値でいうと実質的に約666万円分の購買力しかないことになります。
このようなリスクに備えるには、生命保険だけに老後資金を頼らず、投資信託や不動産など、インフレに強い資産との併用を考えることも重要です。
保険料負担による家計圧迫
貯蓄型の保険は掛け捨て型に比べて保険料が高くなるため、保険料が家計を圧迫してしまうケースがあります。
特に、子どもの教育費が重なる時期や、住宅ローン返済が本格化する時期には、思った以上に家計が厳しくなることも覚悟しなければなりません。
保険料が生活費を圧迫するようになると、「一時払いができない」「保険を解約せざるを得ない」といった事態になり、結果的に損をしてしまうことになりかねません。
このような事態を避けるためには、月々いくらまでなら無理なく支払えるかをシミュレーションし、家計のバランスを見ながら契約内容を決めることが大切です。
保険の営業担当者に勧められるまま高額な契約を結ぶのではなく、自分にとって「必要十分な保障と貯蓄額」を見極めましょう。
生命保険を老後資金に活用する際の選び方のポイント
ここでは上記の注意点を踏まえ、自分に合った生命保険商品を見つけるための選び方のポイントを詳しく説明します。
目的を明確にする
老後資金といっても、「定年後すぐに必要なのか」「70代・80代の生活費に充てるのか」「万一の医療・介護費に備えるのか」など、目的はさまざまです。
まずは何のために保険に加入するのかを明確にすることが大切です。生命保険は加入目的に応じて、大まかに下記のように分類することができます。
・老後の生活費の補完 → 個人年金保険や終身保険が向いている
・医療や介護への備え → 医療保険・介護保険も併用
・万一の遺族保障 → 定期保険や終身保険を検討
受け取り時期と形式をシミュレーションする
個人年金保険では、年金の受け取り開始年齢(例:60歳、65歳)や受け取り期間(10年、15年、終身など)を選択できます。受け取り方によって将来の生活設計が大きく変わるため、「いつから、どのくらいのお金が必要なのか」を具体的に考える必要があります。
また、一括で受け取るか、年金形式で少しずつ受け取るかによって、税金の扱いも異なりますので、受け取り方についても試算しておくと安心です。
商品設計と解約返戻率を比較する
同じ終身保険や個人年金保険でも、保険会社ごとに設計や返戻率が大きく異なります。
たとえば、払い込み期間を短く設定することで返戻率が高くなるケースや、外貨建てにすることで利回りを高める方法もあります。
相見積もりを取る等、複数社の商品を比較検討し、自分のリスク許容度や資金計画に合うものを選びましょう。
また、保険ショップやファイナンシャルプランナーに相談することで、中立的な立場からアドバイスを得ることも可能です。このあたりもぜひ活用しましょう。
保険会社の信頼性と健全性を確認する
長期の契約になる生命保険においては、保険会社の経営状態や信用度も重要なチェックポイントです。万が一、保険会社が破綻した場合、一定の保証はありますが、元本が減るリスクもあります。
保険会社の格付け(S&P、ムーディーズ等)や、ソルベンシー・マージン比率(経営健全性の目安)などの指標を確認して、信頼できる会社を選ぶようにしましょう。
退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク
Q&A:個人年金保険や退職後の老後資金の積み立て方法に関する質問に回答します。
本記事の最期に、筆者がお客様よりいただいた問い合わせ内容をいくつか紹介します。
主に個人年金保険に関する質問になりますが、退職後の老後資金のための積み立てを考える上で、参考になる内容になっております。
質問:個人年金保険とはそもそも何ですか?退職金がない…
個人年金保険とはそもそも何ですか?退職金がないので将来が不安な為に積立を行いながら資産運用が出来るなら魅力的だと感じています。
実際は保険と名前なので保険料金が発生するので、資産は減るのではと感じています。
個人年金保険に関して基本部分をわかりやすく教えて頂けますか?
回答|個人年金保険とは、長生きのリスクに備える積み…
個人年金保険とは、長生きのリスクに備える積み立てタイプの保険です。
個人年金保険料として資金を積み立てて、60歳以降に年金形式で貯めた資金を受け取ることができる保険です。
保障はほとんどないので、死亡保障や病気の備えをすることはできません。
一方で、保障がない分、将来資金を増やしてお金が戻ってくるような商品になっていますので、保険商品の中ではもっとも貯蓄性が高い種類と言えます。
加えて、個人年金には「個人年金保険料控除」がありますので、一定の条件を満たした個人年金保険であれば、所得控除を受けることができ、所得税と住民税を軽減することが可能です。
したがって、ただ資金を積み立てるだけでなく、節税をしながら老後の資金を積み立てることができるのが魅力です。
また、個人年金保険は10年・15年確定年金などの形式で、決まった金額を決まった時期から毎年受け取ることができます。
終身年金などの受け取り方を選択すると、生きている限り年金を受け取ることができますので、長生きの備えをすることができます。
その代わり、終身年金は確定年金とは異なり、早く亡くなってしまった場合にはそこで年金支給は終わってしまいます。
確定年金は、亡くなってしまった後も年金を受け取れる期間が残っている場合には、家族へその年金が支給されます。
このように、自分の老後のプランに応じて、年金開始時期や年金の受け取り方を設定することができます。
退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク
質問:個人年金保険料の控除は年末調整で処理を行うと…
個人年金保険料の控除は年末調整で処理を行うと節税にもなるのでしょうか?
積立て良く保険だと思いますが積立を行っていても年末調整などで、控除の対象などになるのでしょうか?控除される場合はどの程度まで控除されるのかと、他の保険と別途控除が可能なのでしょうか?詳しく知りたいです。
回答|個人年金保険料は、死亡保障などを対象とする…
個人年金保険料は、死亡保障などを対象とする一般保険料保険料控除や医療保険などを対象とする医療保険料控除とは別枠に設けられている個人年金保険料控除の対象です。
したがって、所定の条件を満たす個人年金保険であれば、年末調整あるいは確定申告で控除を受けることができます。
所得税・住民税がどのぐらい軽減されるのかを以下の表にしました。

家族構成や年収に異なりますが、個人年金保険に加入した時の所得税・住民税の軽減される金額になります。
また、個人年金保険の保険料が個人年金保険料控除の対象となる主な条件は以下のとおりです。
●年金受取人が契約者(保険料負担者)または契約者の配偶者であること
●年金受取人が被保険者であること
●保険料払込期間が10年以上あること
●年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ年金支払期間が10年以上あること
思ったような税効果が得られなかったということがないように、上記の条件を満たせているかしっかり確認をして、個人年金保険のプランを検討しましょう。
合わせて読みたい記事
”個人年金保険ってどんな保険?絶対にやっておきたいその仕組みと3つの特徴” ←リンク
質問:個人年金保険を始める最適な年齢でおすすめは何歳…
個人年金保険を始める最適な年齢でおすすめは何歳からが良いのでしょうか?
20代、30代、40代、50代などあると思いますが、50代だと遅すぎるとか、20代だと早すぎるとかあるのでしょうか?
若ければ若いほど始めるのが早い方が良いなどあれば教えてください。
若い時に始める場合の注意点もお願いします。
回答|個人年金保険を始める最適な年齢は、早ければ…
個人年金保険を始める最適な年齢は、早ければ早いほどいいので、20代がベストです。社会人になり、積み立てができる余裕ができれば、すぐに始めてください。
個人年金保険を早めるのが早ければ早いほどいい理由は以下3点です。
1.積立を始める期間が早いほうが将来の年金原資がたくさん貯まる
2.運用期間が長い方が運用利回りが上がる
3.個人年金保険料控除が早くから活用できる
当然のことですが、毎月1万円を積み立てると年間12万円積み立てができます。
20年間積み立てれば240万円で、40年間積み立てれば480万円積み立てができますので、早く積み立てを始めることで現金原資を多く活用できます。
また、金利のように個人年金保険も早期から積み立てを開始することでより高い返戻率になりますので、年金原資をより増やして受け取ることができます。
さらに、個人年金保険料控除がありますので、早くから加入することでより多くの所得税や住民税を節約することが可能です。
年間で6800円の税金を節約できたとして、40年間で節約できる金額は約27万円にもなります。
したがって、積み立てができる余裕さえできるのであれば、早めに個人年金年金保険で積み立てを始めることをおすすめします。
質問:単純に個人年金保険のメリットとデメリットが…
単純に個人年金保険のメリットとデメリットが知りたいです。個人年金保険に加入した場合に注意するデメリットや、恩恵であるメリットをわかりやすく知りたいです。
実際にどの程度、費用が掛かり、受け取れる金額の割合?パーセントなどが知れたら助かります。加入を検討中です。
回答|個人年金保険のメリットは、老後の長生きリスク…
個人年金保険のメリットは、老後の長生きリスクに備えるために、効率よく老後資金を蓄えられる点です。
30年程度積み立てを行えば、支払った保険料の105~140%程度の返戻率となりますので、定期預金を行うよりも資金を増やせます。
それに加えて、個人年金保険料控除を受けることができますので、所得税と住民税を軽減することが可能です。
デメリットは早期解約をすると支払った保険料よりも解約返戻金が低くなることが多いため、結果的に元本割れを起こしてしまいます。
加えて、死亡保障や医療保障もないため、保障がついていないこともデメリットの1つです。
例えば、個人年金保険に加入して間もなく死亡してしまった場合には、解約返戻金しか死亡時に返還されないタイプの個人年金保険であれば、支払った保険料よりも少ない返戻金しか遺族は受け取れず、元本棄損してしまいます。
質問:通常の保険みたいに入院した時などの付帯は…
通常の保険みたいに入院した時などの付帯は個人年金保険にはあるのでしょうか?
単純に積立て年金の代わりになるだけの保険なのでしょうか?加入する事で、入院時や生命保険の付帯的なのが付いていれば加入をしようかと思っています。
特に積立だけだと余程メリットがないと加入しないと思います。
回答|個人年金保険には死亡保障や医療保障は基本的…
個人年金保険には死亡保障や医療保障は基本的にはありません。単純に将来の老後のための積み立てです。
もしも、積み立てをしながら保障を確保したいのであれば、終身保険や養老保険に特約で保障を付帯させるか、生存給付金付きの終身医療保険などを検討してみましょう。
積み立てをしながら、様々なニーズに合致する保障を付帯させることが可能です。
質問:収入もあり複数の個人年金保険に加入したい…
収入もあり複数の個人年金保険に加入したいのですが、複数の個人年金保険に加入する事は出来るのでしょうか?
複数に加入した場合は積み立てた金額に応じて複数から貰う事が可能でしょうか?年末調整などでの控除など複数に入った場合は優遇されるなどはありますか?
複数加入での注意点などあればそれも教えてください。
回答|個人年金保険は複数の契約をすることが可能です。
個人年金保険は複数の契約をすることが可能です。
例えば、定年退職が65歳の場合は、退職後に海外旅行を楽しむために65歳から70歳までの5年間年金を受け取るプランと70歳から85歳あるいは一生涯などの長期間に長生きしたときの備えとして加入するなど、目的に応じて年金開始時期と年金支給年数を定めて複数の個人年金に加入できます。
中には学資目的として子どもが大学~大学院在学予定期間に合わせて個人年金に加入する方もいらっしゃいます。
複数加入するメリットは目的に応じて年金支給を調整できる点です。
それ以外のメリットは、払い済みをこまめにできる点です。
減額をすると、元本棄損をしてしまうので、減額や解約はしたくないが、払い込んだ分は将来受け取りたいというときに払い済み保険への変更は有効です。
保険料を今後支払うことはしなくてよくなりますし、年金開始時期まで運用されて年金支給されますので、元本棄損を防ぐことができる可能性が大きくなります。
目的ごとに契約加入しているため、例えば1万円の契約を3本加入している場合は、1本払い済みにすることで月々の支払いを2万円にすることができます。
このように複数の個人年金保険料を契約することで、保全をして保険料の調整はしやすくなります。
個人年金保険を複数契約するメリットはここまでで紹介した2点です。
一方で、1万円の契約を3本するよりも3万円1本の契約にしたほうが、保険会社によっては高額割引といわれる大きな契約をすることによる割引が適用されてたくさん返戻金が増える場合もあります。
したがって、無理やり複数で加入するよりも1本にまとめたほうが良いのかどうか確認をしてから加入をしましょう。
退職金を少しでも減らさずに老後資金に充てたい方
退職金を安全に運用する方法をしたい人は気軽にLINEもしくはメールから◀︎リンク