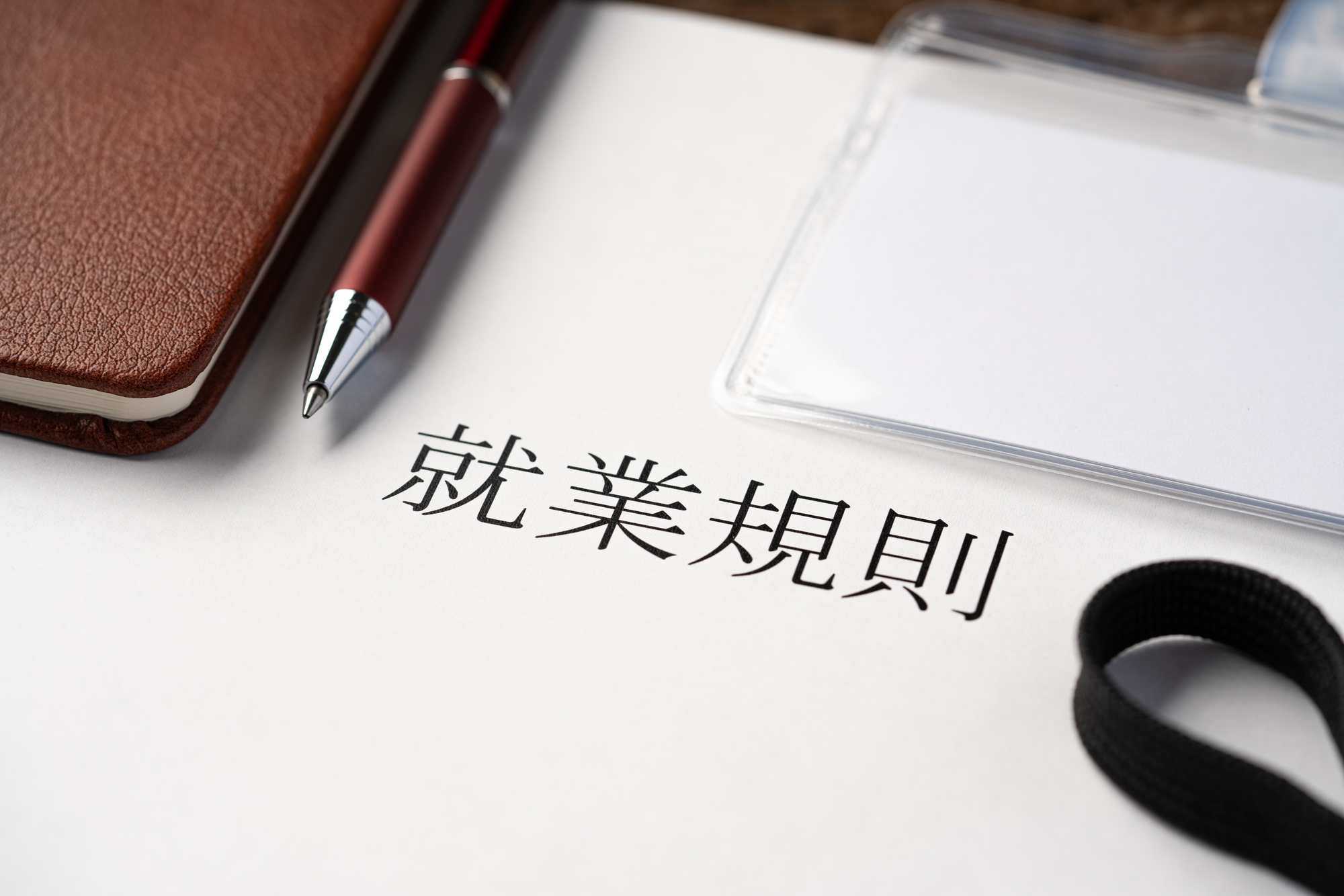医療費控除はいつまでに手続きすべき?確定申告のやり方は?いくらからが対象?いくら戻る?交通費も含まれる?


10月から11月末にかけて 年末調整を行う時期になり、保険会社からは生命保険料の控除ハガキが届く時期にもなります。
この年末調整の手続きをすることにより、その他の控除できる種類や控除金額も気になってきます。
例えば、一年間で病院にかかった医療費や薬の処方を受けたことで対象になるのが医療費控除になります。
今回の記事では、医療費控除の対象の範囲や手続きをすべきなのか?また確定申告をしたほうがいいのか?
など、いただいた質問に回答をして行きます。
目次
所得控除とは
毎年2月に差し掛かると、該当する人によっては確定申告を意識しだします。
納めるべき税金をいかに低く抑えるかを苦慮することでしょう。
納税額を抑える方法として最も一般的なやり方で、所得控除があります。
これは納税額計算となる所得から一定額を控除するというもので、年末調整や確定申告によって適用されるものです。
所得控除は全部で15種類もあり、それぞれに要件があります。
15種類の所得控除は下記の通りです。
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除基礎控除
このように所得控除はたくさんあり、中には申請が必要なものもあります。とりわけ医療費控除に関しては、その存在は知っているものの、具体的なやり方を知らないという人が多いのではないでしょうか。
今回の記事は医療費控除関する質問に回答することで、医療費控除の理解をさらに深めるものとなっています。
確定申告の際に、ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額以上の場合に受けることができる所得控除です。
これをすることで、所得税・住民税の納税負担を軽減することができます。
ただし、医療費控除の適用を受けるためには確定申告が必要であり、会社員であっても年末調整で医療費控除を受けることはできません。
補足:セルフメディケーション税制とは
医療費控除とよく似たもので、セルフメディケーション税制というものがあります。
正式名称を、特定の医薬品購入額の所得控除制度といい、医療費控除の特例として位置づけられています。
こちらも医療費控除と同様、所得税・住民税の納税負担を軽減する効果があります。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用であり、併用することはできません。
医療費控除とセルフメディケーション税制どっちが得か?
医療費控除の適用要件は、年間の医療費が10万円を超えていることです。
一方でセルフメディケーション税制の適用要件は、薬局等で購入した医薬品(スイッチOTC医薬品)の1年間の購入額が12,000円を超えていることとなっております。
年間購入額から12,000円を差し引いた額を、所得から控除することができます。
なお、控除できる上限額は88,000円となっています。本題のどちらが得かを検討する際には、年間の医療費の10万円を基準に考えると良いでしょう。
超えていれば医療費控除、超えていなければセルフメディケーション税制の適用を検討しましょう。
Q&A:医療費控除に関して質問を紹介し回答
それでは医療費控除に関して、いただいた質問を紹介し、回答していきたいと思います。
質問:医療費控除の計算のやり方を教えて欲しいです。
これまで健康優良児として生きてきました。しかし、今年に入って健康診断で引っかかる箇所が増えて、いろいろな科に通院をする事になりました。
病院とはほぼ無縁の生活をしていたのですが、いきなり定期通院が増えてそれに伴って今年の医療費はかなり膨れ上がりそうです。
医療費控除を受けようと思います。
医療費控除の計算のやり方を教えて欲しいです。
回答|4つのステップで計算することができます。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に払った医療費の総額が10万円(所得の合計額が200万円未満の人は所得の合計額の5%)を超える場合に、課税対象となる所得金額から控除することができ、結果的に所得税と住民税を安くすることができるものです。
なお医療費控除の適用を受けるには、確定申告をすることが必要となります。
医療費控除の計算式
以下の4つのステップで計算することになります。
2.医療費控除額を算出する
3.所得金額を計算し所得税率を確認する
4.軽減される税額を計算する
以下、それぞれについて解説します。
1月1日から12月31日までの1年間で払った医療費の合計額を計算する
まずは実際に1年間で支払った医療費の総額を計算します。
領収書やレシートを集めて正確に確認しましょう。
ここで、そもそもの医療費控除の最低限の要件である10万円を超えるか否かを判断します。
医療費控除額を算出する
医療費控除額の計算式は下記の通りとなります。
1年間に払った医療費総額―保険金等で補てんされる金額―10万円(注)
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
医療保険等で保険金が受け取れる場合には、その受給額が控除される点には注意が必要です。
保険金等で補てんされる金額の具体例としては、医療保険の入院給付金や手術給付金等の他、公的医療保険の高額療養費や出産育児一時金も対象となります。
また総所得金額についても、たとえば会社員の場合は給与収入がそのまま総所得金額となるわけではなく、一定の金額が控除される点は抑えておきましょう(この点は後ほど具体例で触れます)。
所得金額を計算し所得税率を確認する
適用される所得税率を確認します。ご自身の収入に応じて課税対象となる所得金額を割り出すことで税率は確認できます。
国税庁ホームページにも記載はありますが、具体的な所得税率を下記の表の通りご案内します。
■所得税率の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※国税庁ホームページより抜粋
軽減される税額を計算する
適用される所得税率がわかれば、軽減される税額を算出することができます。
具体的には②で計算した医療費控除額に、適用される所得税率を乗じて軽減税額を計算します。
なお、住民税の軽減税額は所得に関係なく、医療費控除額に10%を乗じて算出します。
医療費控除計算の具体例
実際にどれくらいの税負担額が軽減されるのか、具体例を挙げて解説します。
前提条件を下記のように定めます。
【前提条件】
・職業:会社員
・総所得金額:400万円
・1年間に支払った医療費総額:30万円
・保険金等で補てんされる金額:10万円(民間医療保険より入院給付金を受け取ったものとする)
まず医療費控除額を算出します。
計算式に当てはめると下記のようになります。
30万円(1年間に支払った医療費総額)―10万円(保険金等で補てんされる金額)―10万円=10万円
次に適用される所得税率を確認します。
所得税率の速算表によると、総所得金額が400万円の場合、税率は20%となります。
最後に軽減される金額を算出します。
所得税:10万円×20%=2万円
住民税:10万円×10%=1万円
合計:3万円
以上のような流れで計算します。それほど複雑な計算式はないので、必要な資料さえそろっていれば、比較的簡単に控除額を算出することはできます。
ただし、医療費控除の適用を受けるには確定申告が必要になります。
忘れずに申告するようにしましょう。
質問:医療費控除の対象になる医療はどこからどこまでですか?
私は歯列矯正をしたりホワイトニングをしたり美容整形をしたりしています。
容姿に関わる手術であり、健康を脅かすものではないので必要不可欠な医療行為ではないと判断されるかもしれません。
しかし、病院に通院しているので医療行為に該当するのでは?と思う気持ちもあります。
医療費控除の対象になる医療はどこからどこまでですか?
回答|ひとつの基準として、治療に該当するかしないかで判断します。
医療サービスを受けた場合、そのすべてが医療費控除の対象となるわけではありません。
対象となるかならないかの境界線はわかりにくいですが、ひとつの基準として、治療に該当するか否かという観点で考えることができます。
参考までにわかりにくいものの具体例を下記にご案内します。
■医療費控除の対象・対象外一覧
| 内容 | 対象/対象外 |
|---|---|
| 歯科矯正の費用 | 〇 |
| インプラントの費用 | 〇 |
| 健康診断、人間ドックの費用(注) | × |
| 医師への謝礼金 | × |
| はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 | 〇 |
| 保健師、看護師等による療養上の世話の対価 | 〇 |
| インフルエンザ等の予防接種費用 | × |
| 持病の治療のために温泉へ行った際の費用 | × |
| 視力回復手術(レーシック)に係る費用 | 〇 |
| コンタクトレンズ代金 | × |
| 助産師による分娩介助費用 | 〇 |
| 医師による診察を受けるための通院費等の交通費 | 〇 |
| 病院まで自家用車で通院する際のガソリン代、駐車場代 | × |
| 美容整形手術にかかる費用 | × |
| ニキビ治療のための塗り薬の購入費用 | 〇 |
| 脱毛費用 | × |
人間ドックの費用について
医療費控除の対象となるか、ならないかの議論の中で、よく間違えられるのが人間ドックの費用です。
原則として人間ドックは健康診断費用に該当し、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、人間ドックの結果、重大な病気が見つかり、当該病気の治療を継続するような場合は医療費控除の対象と認められる場合があります。
その場合は、人間ドックを治療のための検査とみなすためです。
また、よく勘違いされやすいのが、保険適用外の治療は医療費控除対象外となり、保険適用の治療は医療費控除の対象となるという区分です。
それは間違いです。保険適用外となる自費診療であっても、治療目的と認められたら医療費控除の対象となります。
たとえば歯科矯正にかかる費用は保険適用外となりますが、医療費控除の対象となる良い例です。しっかりおさえておきましょう。
質問:医療費控除を受ける為の確定申告はいつまでにやるべきですか?
先月、親不知を抜歯する際に2泊3日の入院もした上での手術を受けました。
入院ももちろんですが、その前に撮影したレントゲン写真やCT画像についても計算するとまあまあな金額に到達しました。
私にとってはかなり痛い出費となります。少しでも優遇措置を受けられるのであれば受けたいです。
損はしたくありません。
医療費控除を受ける為の確定申告はいつまでにやるべきですか?
回答|その確定申告の期限は、原則として毎年2月16日から3月15日です。
医療費控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。
その確定申告の期限は、原則として毎年2月16日から3月15日となっています。
ちなみに令和7年については、曜日の関係で2月17日から3月17日となります。
医療費控除の適用を受けるには多くの書類が必要になります。
年が明けたらなるべく早めに準備を進めることをおすすめします。
具体的な必要書類は下記の通りです。
・医療費の明細のわかる領収書、レシート等
・交通費のメモなど
・保険金等で補てんされる金額の内容のわかるもの
医療費控除の明細書
国税庁ホームページでダウンロードした書式を使用します。
ここには受診した医療機関やそこで支払った医療費を記入します。
医療費の明細のわかる領収書、レシート等
医療費控除の明細書を記入する根拠資料となります。
なお、領収書やレシート等は確定申告に際して提出の義務があるものではありませんが、税務調査が入ってしまった場合は開示しなければならないものです。
しっかり保管しておきましょう。
交通費のメモなど
医療機関までの交通費も一定の要件を満たすことで医療費控除の対象となります。
電車賃やバス代は領収書が発行されませんが、かかった費用はメモしておいて、医療費控除の明細書にそのメモの情報を記入するようにしましょう。
保険金等で補てんされる金額の内容のわかるもの
医療保険から給付金を受けた場合、医療費控除の金額に影響することになります。
その根拠資料として保険会社から送付される給付金明細書といった支払内容のわかる資料が必要となります。
質問:いくらから医療費控除の対象になりますか。
今年から定期通院をして治療を始めた者です。2週間に1回の通院をしており、着実に年間医療費の金額が増えてきています。
このような経験は初めてです。健康保険によって三割負担なので既に国から支えられているからこれ以上は安くならないのかなと思っていたのですが、医療費控除という精度があることを最近知りました。
いくらから医療費控除の対象になりますか。
回答|その人の収入によりますが、10万円をひとつの基準と考えましょう。
医療費控除の金額の基準は、適用を受ける人の収入金額によって変わります。
具体的な基準は下記となります。
・総所得金額が200万円以上:10万円
上記のように、その人の収入によって異なりますが、ひとつの目安として年間の医療費総額が10万円を超えるかどうかで判断しましょう。
なお医療費控除の対象となるのは、自分自身の医療費だけではありません。
同一生計の家族の分すべてが加算対象となります。ただし、病院で払った費用のすべてが医療費控除の対象となるわけではありません。
たとえば美容整形にかかった費用や健康診断の費用は、医療費控除の対象外です。あくまで、治療を目的とした医療費のみが対象となるという観点で理解しておきましょう。
支払った医療費総額が、医療費控除の基準に満たなかった場合でも、「セルフメディケーション税制」というものがあります。
これは医療費控除の特例として位置づけられているもので、医療費控除と同様、所得税・住民税の納税負担を軽減する効果があります。
「セルフメディケーション税制」を適用するためには、薬局等で購入した医薬品(スイッチOTC医薬品)の1年間の購入額が12,000円を超えていることで、医療費控除よりはハードルが低いものです。
医療費控除がダメだった場合は「セルフメディケーション税制」の適用を検討しましょう。
質問:医療費控除は病院への往来にかかった交通費も対象になりますか?
私は地方の田舎に住んでいます。最近、発覚した病気がありまして、大きな病院に通院せざるを得なくなりました。
自宅が交通が不便な奥地の田舎なので通院は毎回電車に乗って片道だけで2時間ほどかけています。
医療費だけでなく交通費もかかって痛い出費です。
医療費控除は病院への往来にかかった交通費も対象になりますか?
回答|交通費も対象となりますが、一定の要件があります。
あまり知られていないことですが、実は病院への往来にかかった交通費は、医療費控除の対象とすることができる可能性があります。
ただし要件があります。国税庁のホームページでは下記のように記載しています。
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費で通常必要なものが対象となります。電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
つまり、原則として電車やバスといった公共交通機関を利用することとし、公共交通機関が通っていない等の場合のみ、例外的にタクシー代が認められるということになります。
なお、患者本人だけでなく、付添人の交通費も医療費控除の対象となることは覚えておきましょう。
また、医療費控除を適用するには原則として領収書等、費用のわかる資料が必要になりますが、公共交通機関を利用しての交通費について、領収書は不要です。
そもそも領収書を取ることが難しいからです。
確定申告の際に細かな経路等の記載をすることで代用します。
まとめ
今回の記事では、医療費控除についていただいた質問に回答することで、深掘りしました。
医療費控除は、その存在を多くの人に認知されているものの、その具体的なやり方や細かいルールについてまでは理解されていませんでした。
交通費や人間ドックの費用も、一定の要件を満たすことで、医療費控除の対象となりうることを知っている人は、きっと少なかったのではないでしょうか。
この記事が、多くの人の節税のお役に立てることができれば幸いです。