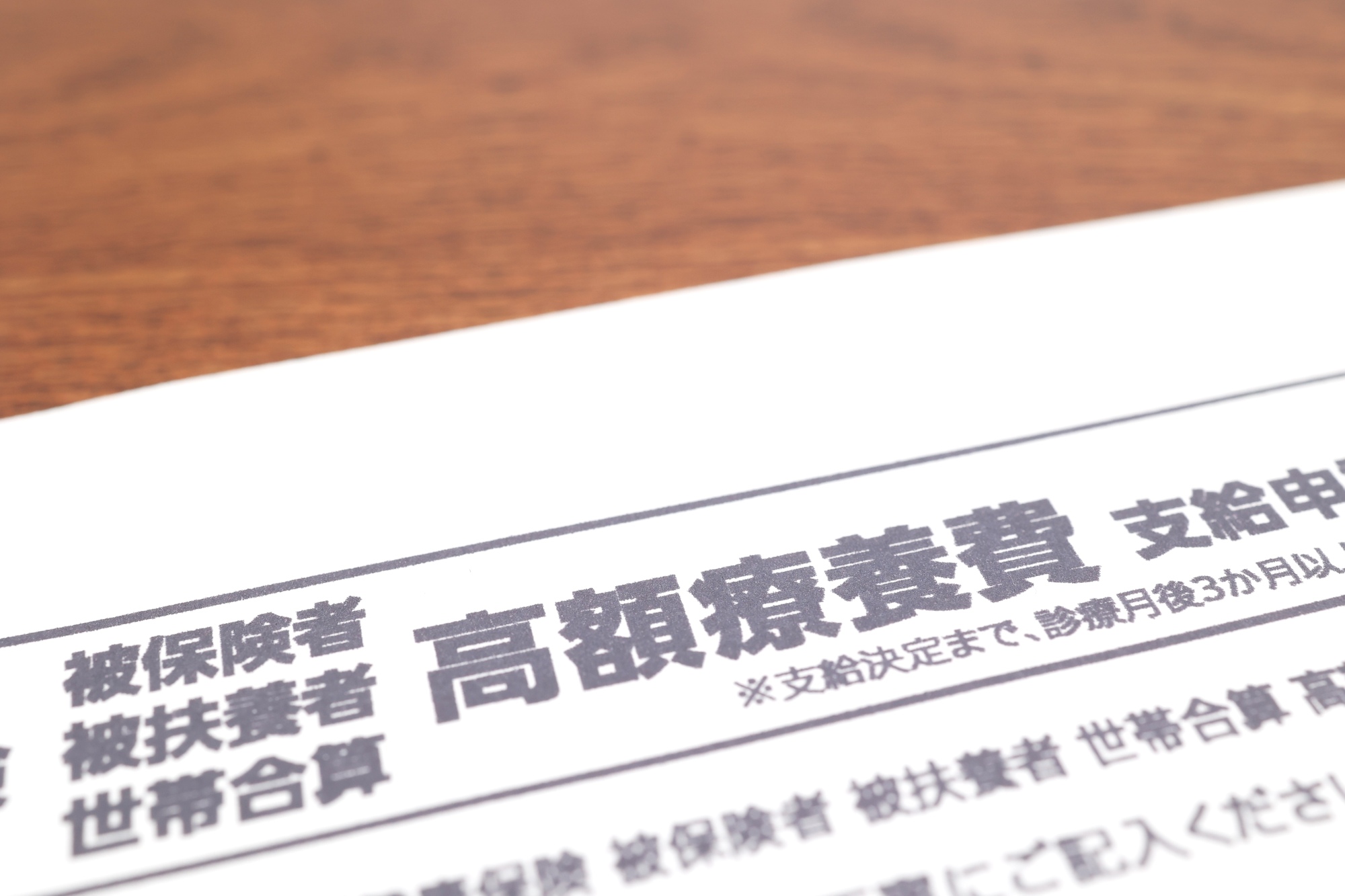障害者控除で税金は安くなる?免除される税金の種類は?還付金はいくら?確定申告は必要?車周りでの優遇はある?の質問に回答します。


障害者認定を受けた時障害者控除の申請をすることにより税金はいくら安くなるのか?
どの程度税金が免除され税金が安くなるのか?確定申告は必要なのか?
障害者控除を受けたときにどの程度税金が優遇されているのか?など、いただいた質問に回答して行きます。
目次
障害者を取り巻く現状
日本において、全人口に占める障害者の割合は現在7.6%であり、実人数で約964万人にものぼります。
約20年前と比較すると実に300万人も増えており、現在も増加傾向にあります。
その主な要因は下記の3点が考えられます。
少子高齢化
医療技術の進歩等もあり、日本人は世界的にも長寿国となりました。
一方で高齢ともなると身体機能や認知機能はどうしても衰え、障碍者認定を受けることにつながります。
少子高齢化が障害者の割合を増加させる大きな要因となりました。
障害者の認定基準の問題
障害というものに対する認識が社会全体に広まったことも、障害者の割合が増加したことの一因です。
たとえば発達障害については、ひと昔前まではあまり世間に浸透しておらず、ただの落ち着きのない人、空気の読めない人程度にしかとらえられていませんでした。
現在ではそのような発達障害の比較的世間に認知されつつあります。
また障害とは、申請をすることで初めて認定を受けるものでもあります。
社会全体への認識の広まりが、障害の申請件数の増加を後押ししたことで障害者が増加したとも言えます。
現代社会の環境要因(精神障害の増加)
現代社会特有のストレス環境に適応できず、精神障害を発症してしまう割合が増加していることも一因です。
精神障害は全体の障害者のうち、実に半数近くを占めているのです。
このような障害者を取り巻く状況を受けて、政府も様々な策を講じています。
そのひとつが障害者雇用の奨励です。具体的には、障害者の雇用義務のある企業(常用労働者が100人超いること)が雇用人数の要件を満たせないとき、不足人数1人につき月額5万円が課せられます。
逆に一定の人数以上の障害者を雇用する企業に対しては給付金が支給されます。
このような仕組みを作ることで障害者の雇用の促進を図っているのです。
税制の面でも障害者に対する優遇措置は整備されてきており、障害者にとっては生活しやすい環境は整ってきたと言えます。
しかし、このような取り組みは世間に認知されておらず、制度の利用ができていない人が多いという課題があります。
今回の記事の狙いは、質問の回答を通じて障害者の税制面、社会保険料の面での優遇措置の理解を深めることも含まれています。ぜひ参考にしてください。
Q&A
障害者関連の税制面での優遇措置に関する疑問等、いただいた質問とそれに対する回答を紹介していきたいと思います。
質問:障害者控除で税金はどれぐらい安くなるのですか?
いわゆるブラック企業で働いていた者です。慢性的に体調不良を抱えて数年間働き続けていたのですが、ある日文字が読めなくなったことがきっかけで怖くなり通院をしたところドクターストップがかかりしばらく休職することになりました。
傷病手当金などの援助があるとは知りつつも、しばらく収入が途絶える不安があります。
元同僚に既に精神疾患で退職した人がいるのですが、その人曰く障害者手帳を持っていれば障害者控除を受けれるとのことでした。障害者控除で税金はどれぐらい安くなるのですか?
回答|所得税や相続税等、税制面の優遇措置は様々あります。
障害者が受けることができる税金面の優遇措置で代表的なものとして、多くの人が所得税の障害者控除を思いつくと思います。
ただ、税金面での優遇措置はこれだけではありません。そのうちのいくつかを紹介します。
◆相続税の障害者控除
これは遺産を相続する人が障害者に該当する場合、相続税が軽減される仕組みです。
対象となる相続人が85歳未満の障害者である場合、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を、納めるべき相続税から控除することができます。
納めるべき税金からダイレクトに差し引くことのできる税額控除になりますので、税額軽減効果がとても大きいものです。
◆心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
心身障害者扶養共済制度とは、障害のある人を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納付することで、自身に万が一のことがあった場合に、当該障害のある人に一定額の終身年金を支給する制度です。このような給付は福祉的な側面が強く、所得税非課税で受給することができます。
◆特定障害者に対する贈与税の非課税
障害者に対しては3,000万円、特別障害者に対しては6,000万円までの贈与が非課税になるというものです。ただし通常の贈与では、この非課税の適用を受けることができません。
適用を受けるには、信託銀行を利用して、一定の信託契約に基づく財産の信託があった場合に限られるのです。
詳細につきましては、信託銀行や税理士に相談した上で進めるようにしましょう。
◆少額貯蓄の利子等の非課税
預貯金や公社債の利子は、所得税および復興特別所得税として15.315%(プラス地方税5%)が控除され、その残額が支払われています。この仕組みを源泉徴収といい、そこで納税を完結させるようになっています。一定の障害者に該当すると、一定額まではこの利子を非課税で受け取ることができるのです。
ただしこの制度の適用を受けるためには申請が必要です。具体的には、最初に預け入れをする日までに「非課税貯蓄申告書」、「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所を経由して税務署に提出しなければなりません。
このように、障害者であることで税金面の優遇措置はいくつか定められています。そのほかにも、自治体によっては独自の優遇制度が定められているところもあります。
具体的には公共料金や鉄道運賃の割引制度が用意されている自治体もあります。
取り扱いの有無に関しては、必ず各自治体の福祉課等に確認してみましょう。
質問:障害者が受けれる税金の還付にはどのようなものがありますか?
交通事故に遭って障害者となった者です。これからの人生がハードモードになりお先真っ暗で気持ちまで落ち込んでいます。
ただでさえ1日1日を生きるので精一杯なのに、これにさらに税金という重荷がのしかかってくることを考えるととても払い切れる気がしません。
障害者が受けれる税金の還付にはどのようなものがありますか?できる限り制度や優遇措置は使いたいと思っています。
回答|自動車関連の税金優遇措置として、自動車税、自動車取得税の減免があります。
障害者であることを要件とした、自動車関連の税金減免制度はあります。
具体的には自動車税・自動車取得税(※)が減免の対象となります。(※)
・自動車税・・・自動車を所有しているという事実に対して課せられる税金です。毎年4/1時点の所有者に対して課せられるもので、総排気量が大きければ大きいほど税額も高くなります。
・自動車取得税・・・自動車を購入する際に課せられる税金です。50万円以上の自動車が対象で、自家用車が3%、事業用車が2%の税率が購入金額に課せられます。
ただ、減免対象となる障害者にも要件があります。その要件も自治体によって異なります。
適宜実例を交えつつ、解説していきます。
障害者の要件
各自治体によって異なりますが、障害者の区分や傷害の程度としては、おおむね下記のような要件に該当する必要があります。
※下記は埼玉県川口市の要件です。
障害区分 障害程度
視覚 1級から3級。4級は他に要件あり。
聴覚 2級、3級。
平衡感覚 3級。
音声機能及び言語障害 3級(こう頭が摘出された場合に限る)。
上肢 1級、2級。
下肢 1級から6級。
体幹 1級から3級、5級。
乳幼児期以前の非進行形脳病変による運動機能「上肢」 1級、2級
乳幼児期以前の非進行形脳病変による運動機能「移動」 1級、3級。
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓 1級から3級。
戦傷病者手帳 身体障碍者手帳の減免の範囲に準ずる。
療育手帳 〇A、A
精神障碍者保健福祉手帳 1級でかつ自立支援医療(精神通院)を受けている方。
減免される税額
◆自動車税
各自治体によってバラつきはありますが、おおむね上限45,000円の設定になっています。
◆自動車取得税
自動車取得金額に対して該当する自動車取得税の税率を乗じた額が減免されます。
例えば、自動車の価額が300万円、一定の税率が4%であれば、12万円が減免されることになります。ただし対象となる自動車取得額には上限額があり、その額も自治体によって異なりますので、注意が必要です。
このように、障害者であることを要件として、自動車税、自動車取得税が減免される制度があります。
ただし、この制度の適用を受けるには申請が必要となります。忘れずに申請するようにしましょう。なお手続きの窓口はお住まいの自治体になります。
質問:障害者で車を持つ者です。自動車周りでの税金優遇はありますか?
障害者で車を持つ者です。田舎での生活なので車がないと生きていくのが厳しいです。
しかし、足が不自由なので車の乗り降りに必要な機材などがあり、健常者よりも車回りに必要な費用が高くなってしまいます。
一人暮らしなので頼る家族も居ないので車を手放すという選択肢がなく、途方に暮れています。少しでもこの負担が軽くなると幸いです。自動車周りでの税金優遇はありますか?
回答|障害者であること要件として税金、社会保険料の減免があります。
障害者であることを要件とした税金の優遇措置はいくつかあります。
代表的なものは下記となります。
・相続税の優遇措置
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
・特定障害者に対する贈与税の非課税
・少額貯蓄の利子等の非課税
なお適用を受けるためには、それぞれに要件であったり、申請が必要なものもあります。
個人で進めるにはハードルが高いものもありますので、国税庁ホームページを確認の上、難しそうなものに関しては、税理士に確認する等して進めるようにしましょう。
実は、障害者であることを要件とした優遇措置は、税金だけに限られません。
社会保険料の面でも優遇措置があるのです。ここでは社会保険料の減免について、いくつか紹介したいと思います。
◆国民健康保険料
障害者であること自体が要件となる減免制度ではありませんが、国民健康保険には家族構成や本人の所得に応じて以下の3種類の減免制度があります。
・7割減・・・世帯年収が33万円以下。
・5割減・・・世帯年収が27万5,000円×世帯人数―33万円以下
・2割減・・・世帯年収が50万円×世帯人数―33万円以下
障害者に該当すると、どうしても就業の面で制限が出てきます。
結果的に所得にも影響が出てきてしまいます。
そのような方のための救済の意味も含まれています。
なお、減免の適用を受けるためには申請が必要になります。具体的な申請方法や必要書類については各自治体に必ず確認しましょう。
また、上記の3種類以外にも自治体によっては独自の減免制度があるところもあります。あわせて確認するようにしましょう。
◆国民年金保険料
国民年金には法定免除制度といって、一定の要件に該当することで、法律上当然に保険料が免除される制度があります。具体的な要件は下記となります。
・生活保護の生活扶助を受けている
・障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている
・国立ハンセン病療養所などで療養している方
上記2番目に記載ある通り、障害等級2級に該当することで国民年金保険料は免除となります(同時に保険料納付要件等を満たしていれば、障害基礎年金を受給することができます)。
なお、障害等級3級等、法定免除の基準には該当しなくても、経済的な理由から保険料の納付が困難の方のための保険料免除制度もあります。
具体的な所得基準は下記の計算式の範囲内となることとされています。
・4分の3免除・・・88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除・・・128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除・・・168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
なお上記の免除制度につきましては、法定免除制度と異なり、申請が必要となります。
◆健康保険料
障害状態に該当しても働き続ける人もいるでしょう。会社員であれば健康保険に加入することになりますが、健康保険には障害による減免制度はあるのでしょうか。
結論、健康保険は会社からの月額給与をもとに計算した保険料を納付する仕組みとなっており、会社から給与が出ている以上、保険料が免除されることはありません。
◆厚生年金保険
健康保険同様、厚生年金保険についても、会社員であれば加入することになります。
いかに障害状態に該当しても、会社から給与を受けている以上、保険料の納付義務は発生します。
ただ、厚生年金保険に関しては一定の障害状態に該当することで、障害厚生年金の受給要件を満たします。障害厚生年金の受給要件を満たした上で退職すれば、障害厚生年金を受給することができ、保険料の納付義務も発生しないことになります。
以上が社会保険料関連の減免措置になります。減免制度は申請を必要とするものが多いので、知っていないと損をしてしまいます。
税理士や社会保険労務士といった専門家に相談して、利用できるものは利用することで、費用負担を少しでも軽減するようにしましょう。
質問:障害者が出来る税金対策を教えて下さい。
私の息子が社会人なのですが、精神疾患を罹患してしまいました。
本人には各種手続きや調べ物をするのはとても厳しい状況なので代わりに親である私が一通り代理で進めていこうと思います。
しかし、このような経験が初めてで周囲にも似た境遇の人がいないので相談相手もおらず不安です。
障害者が出来る税金対策を教えて下さい。
回答|障害者であること要件として税金、社会保険料の減免があります。
障害者であることを要件とした税金の優遇措置はいくつかあります。
代表的なものは下記となります。
・相続税の優遇措置
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
・特定障害者に対する贈与税の非課税
・少額貯蓄の利子等の非課税
なお適用を受けるためには、それぞれに要件であったり、申請が必要なものもあります。
個人で進めるにはハードルが高いものもありますので、国税庁ホームページを確認の上、難しそうなものに関しては、税理士に確認する等して進めるようにしましょう。
実は、障害者であることを要件とした優遇措置は、税金だけに限られません。社会保険料の面でも優遇措置があるのです。
ここでは社会保険料の減免について、いくつか紹介したいと思います。
◆国民健康保険料
障害者であること自体が要件となる減免制度ではありませんが、国民健康保険には家族構成や本人の所得に応じて以下の3種類の減免制度があります。
・7割減・・・世帯年収が33万円以下。
・5割減・・・世帯年収が27万5,000円×世帯人数―33万円以下
・2割減・・・世帯年収が50万円×世帯人数―33万円以下
障害者に該当すると、どうしても就業の面で制限が出てきます。結果的に所得にも影響が出てきてしまいます。そのような方のための救済の意味も含まれています。
なお、減免の適用を受けるためには申請が必要になります。具体的な申請方法や必要書類については各自治体に必ず確認しましょう。また、上記の3種類以外にも自治体によっては独自の減免制度があるところもあります。あわせて確認するようにしましょう。
◆国民年金保険料
国民年金には法定免除制度といって、一定の要件に該当することで、法律上当然に保険料が免除される制度があります。具体的な要件は下記となります。
・障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている
・国立ハンセン病療養所などで療養している方
上記2番目に記載ある通り、障害等級2級に該当することで国民年金保険料は免除となります(同時に保険料納付要件等を満たしていれば、障害基礎年金を受給することができます)。
なお、障害等級3級等、法定免除の基準には該当しなくても、経済的な理由から保険料の納付が困難の方のための保険料免除制度もあります。具体的な所得基準は下記の計算式の範囲内となることとされています。
・4分の3免除・・・88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除・・・128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除・・・168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
なお上記の免除制度につきましては、法定免除制度と異なり、申請が必要となります。
◆健康保険料
障害状態に該当しても働き続ける人もいるでしょう。会社員であれば健康保険に加入することになりますが、健康保険には障害による減免制度はあるのでしょうか。
結論、健康保険は会社からの月額給与をもとに計算した保険料を納付する仕組みとなっており、会社から給与が出ている以上、保険料が免除されることはありません。
◆厚生年金保険
健康保険同様、厚生年金保険についても、会社員であれば加入することになります。いかに障害状態に該当しても、会社から給与を受けている以上、保険料の納付義務は発生します。
ただ、厚生年金保険に関しては一定の障害状態に該当することで、障害厚生年金の受給要件を満たします。
障害厚生年金の受給要件を満たした上で退職すれば、障害厚生年金を受給することができ、保険料の納付義務も発生しないことになります。
以上が社会保険料関連の減免措置になります。
減免制度は申請を必要とするものが多いので、知っていないと損をしてしまいます。
税理士や社会保険労務士といった専門家に相談して、利用できるものは利用することで、費用負担を少しでも軽減するようにしましょう。
質問:精神障害者2級の者です。サイト運営でお小遣い程度の収入がありますが税務調査が入る可能性はありますか?
精神障害者2級に該当する者です。フルタイムで会社に務めるのは到底厳しい健康状態なのですが、体調に波があり調子が良い数時間のスキマ時間を使って無理のない範囲でネットビジネスを始めてみました。
社会復帰のリハビリも兼ねています。サイト運営でお小遣い程度の収入がありますが税務調査が入る可能性はありますか?
回答|事業を営む以上、税務調査の可能性はあります。
税務調査と聞くと、売上規模の大きな企業に入るもので、規模の小さな企業や特に個人には縁のない話だと思われるかもしれませんが、実はそんなことはありません。
事業を営んでいる以上、税務調査が入る可能性は0ではないのです。ただ一見すると怖いイメージのある税務調査ですが、それほど恐れるものではありません。
今回は税務調査を正しく理解すべく、その概要を説明します。
税務調査とは
そもそも税務調査とは何をいうのでしょう。それは、納税者から提出された申告書が正確に記載されているかを調べることで、納税者が正しく納税を行っているかを税務署が直接調査を行うことをいいます。
税務調査の種類
税務調査は、調査担当者等の区分によって2種類があります。
任意調査
管轄の税務署の調査担当者が事務所にやってきて、調査対象者に質問したり、帳簿書類を調べたりします。
一般的に税務調査といえば、この任意調査を指します。事前に連絡があった上で、日程調整を経て実施されるのが一般的です。
強制調査
税務署の上部組織である国税局の査察部(通称マルサといいます)が調査に入ることもあります。
これは事前連絡もなく抜き打ちで実施され、拒否することはできません。
この強制捜査は悪質な脱税など、ある程度の証拠をそろえた上で実施されることになります。そういった心当たりがなければ実施されないと考えてよいでしょう。
調査対象となる基準
ここでは①の任意調査の対象となる、大まかな基準について触れます。
一般的に売上が1,000万円を超えてくると税務調査の対象となりやすいと言われています。
その理由の一つとして、売上1,000万円という数字は消費税の課税事業者の基準であるからです。さらに、毎年ギリギリ1,000万円に届かない申告を続けていることも注意が必要です。
課税事業者にならないために所得を隠しているのでは?とみなされてしまうからです。
さらに明確な基準は公表されていませんが、売上、利益に大幅な変動があったり、多額の特別損失、特別利益が計上されていたりすると、税務調査官の目に留まりやすいとされています。
その他にも、同業他社と比較して、明らかに利益率が低かったり、何年も少額の赤字が続いていたりしても、目に留まります。
特に何年も赤字続きでいるのに事業を継続できていると、納税を逃れるために帳簿を操作して、赤字に見せているだけなのではないか、とみられてしまう可能性もあります。
ここまで税務調査(任意調査)について説明しましたが、過度に恐れる必要はありません。
調査担当者も人間なので、協力的なスタンスで臨めば、スムーズに進むことが大半です。
それでも不安がある場合には、思い切って専門家である税理士に相談してみましょう。