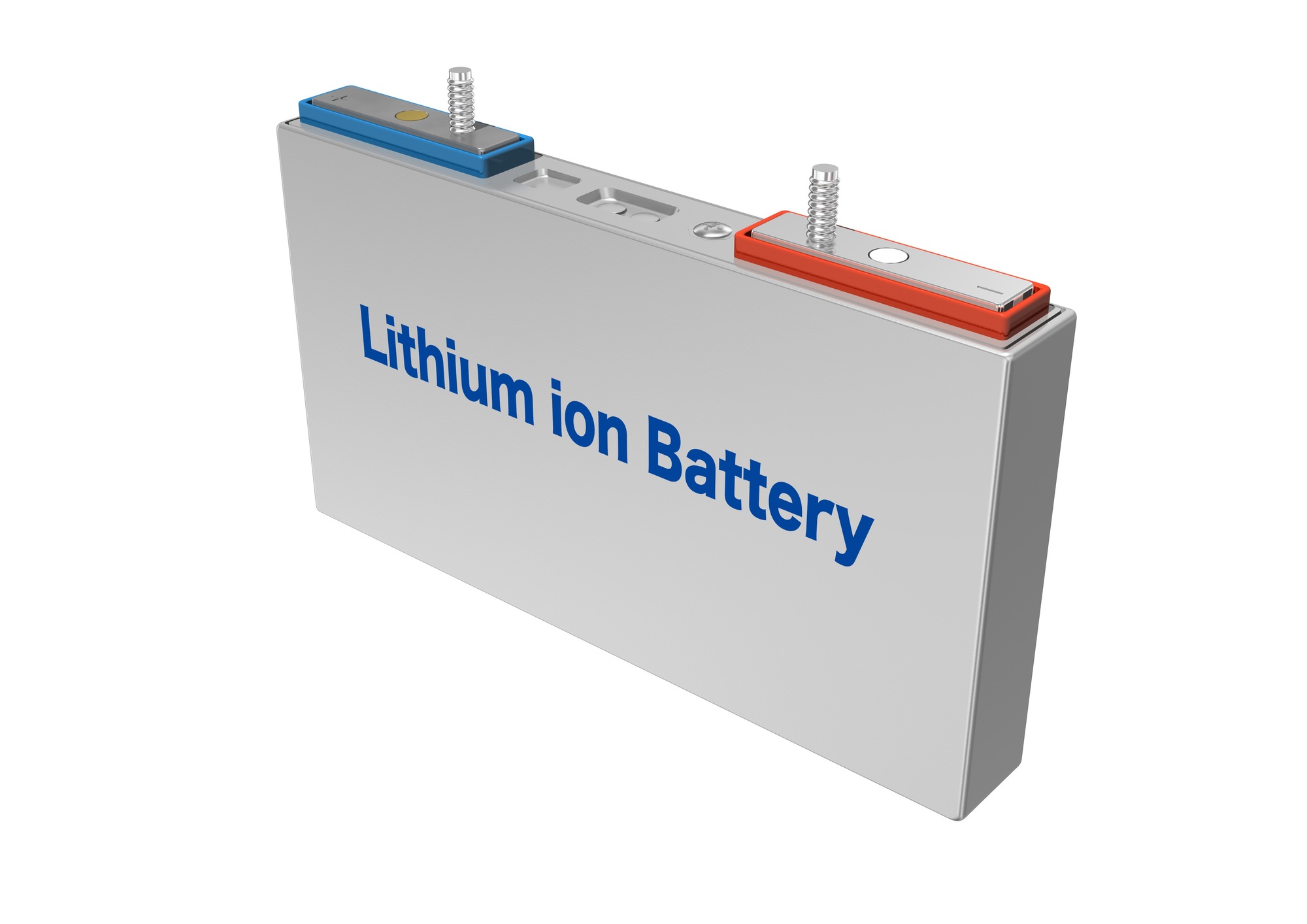業務災害保険とは?必要性はある?労災との違いは?の質問にプロが回答いたします。


仕事をする以上、ケガをするリスクは存在します。
特に建設業などは業務中のケガのリスクの高い代表的な業種です。
事業主はそのような従業員の業務災害のリスクに備える必要があります。
今回の記事では、業務災害のリスクに備えるのに活躍する業務災害保険について、労災保険との違いに触れながら解説していきます。
目次
労災保険とは
まず、本記事の本題となる業務災害保険のQ&Aを紹介するにあたり、前提知識として必要となる労災保険の基礎知識について、解説していきたいと思います。
労災保険とは正式名称を労働者災害補償保険といい、民間の損害保険会社が提供する保険商品と区別して、政府労災とも呼ばれています。
政府労災では、労働者の業務上の事由、または通勤に起因する傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
なお、政府労災の運営にあたる費用は、全額が事業主の拠出する保険料によってまかなわれており、労働者の費用負担は発生しません。
これは、事業主には労働者が安全かつ健康に働くことができるよう、職場環境を整備しなければならないという安全配慮義務からきています。
もし事業主が安全配慮義務に違反して、労働者が傷病を負ってしまった場合、事業主が被災労働者に対して責任を負わなくてはなりません。
加入対象者
政府労災は、労働者を一人でも使用する場合、業種の種類を問わず原則として加入しなければなりません。
自動車でいうところの自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)のような位置づけになります。ここでいう労働者とは、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも含まれ、雇用形態は問われません。
なお、企業の社長や役員に関しては、経営に携わる立場であることから労働者とはならず、原則として政府労災の補償対象とはなりません。
ただ、一定の要件を満たす中小事業主に該当することで、政府労災への加入が認められます。
これを特別加入制度といいます。
ここでいう中小事業主の具体的な要件は下記の通りです。
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業 | 50人以下 |
| 保険業 | 50人以下 |
| 不動産業 | 50人以下 |
| 小売業 | 50人以下 |
| 卸売業 | 100人以下 |
| サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
※厚生労働省ホームページ 特別加入制度のしおり より抜粋
上記の要件に該当すれば、労働保険事務組合を通じて、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署に提出することで、申請することができます。
政府労災の保険給付の内容
政府労災では実に様々な保険給付が定められています。この項では、保険給付の概要を下記に解説したいと思います。
以下、保険給付の解説にあたり、業務災害によるものの場合、(補償)も含めて読みますが、通勤災害の場合、(補償)は含みません。
例)業務災害→療養補償給付、通勤災害→療養給付 と読みます。
療養(補償)給付
業務災害、または通勤災害による傷病により療養するとき、必要な療養の給付を受けることができます。
つまり、業務災害によって労災指定病院で診察等を受けた場合、原則として費用負担は発生しないことになります。なお通勤災害の場合は、一部負担金として200円の費用負担が発生します。
休業(補償)給付
業務災害、または通勤災害による傷病の療養のために労働ができず、事業主から賃金が得られない場合、現金の給付を受けることができます。
なお給付を受けることができるのは、休業の4日目からとなっており、現職中の日給相当額(以下、給付基礎日額と表記します)の60%、特別支給金としてさらに20%加算され、合計で80%の給付となります。
障害(補償)給付
業務災害、または通勤災害による傷病が治癒した後に、身体に一定の障害が残った場合に、障害等級に応じて給付されます。障害等級第1~7級に該当すると年金として、障害等級第8~14級に該当すると一時金として給付されます。
受給金額は給付基礎日額をもとに、障害等級に応じた日数分を乗じて計算されます。詳細は下記をご確認ください。
|
障害(補償)年金 |
障害(補償)一時金 |
||
|
障害等級 |
給付基礎日額の日数 |
障害等級 |
給付基礎日額の日数 |
|
第1級 |
313日分 |
第8級 |
503日分 |
|
第2級 |
277日分 |
第9級 |
391日分 |
|
第3級 |
245日分 |
第10級 |
302日分 |
|
第4級 |
213日分 |
第11級 |
223日分 |
|
第5級 |
184日分 |
第12級 |
156日分 |
|
第6級 |
156日分 |
第13級 |
101日分 |
|
第7級 |
131日分 |
第14級 |
56日分 |
なお、休業(補償)給付と同様、障害(補償)給付についても特別支給金として上乗せ補償があります。
遺族(補償)給付
業務災害、または通勤災害によって労働者が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族の人数に応じて、一定の遺族に対して年金が支給されます。金額の詳細は下記をご確認ください。
|
遺族(補償)年金 |
|
|
遺族の人数 |
給付基礎日額の日数 |
|
1人 |
153日分 |
|
2人 |
201日分 |
|
3人 |
223日分 |
|
4人以上 |
245日分 |
なお、遺族(補償)年金の受給要件を満たす一定の遺族がいない場合には、その他の遺族に一時金が支給されます。
一時金の金額は給付基礎日額の1000日分を基準とします。
遺族(補償)給付についても特別支給金として上乗せ支給の規定があります。
葬祭料(葬祭給付)
業務災害、または通勤災害によって労働者が死亡した場合に、葬祭を行う人に葬祭費用を支給します。
業務災害の場合を葬祭料、通勤災害の場合を葬祭給付といいます。支給額は315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方の金額となります。
傷病(補償)年金
業務災害、または通勤災害による傷病が、療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級に該当する場合に年金が支給されます。
支給される金額は、傷病等級に応じて下記のようになります。
・第2級・・・給付基礎日額の277日分
・第3級・・・給付基礎日額の245日分
傷病(補償)年金についても特別支給金として上乗せ支給の規定があります。
介護(補償)給付
障害(補償)年金、または傷病(補償)年金の受給者のうち、第1級または第2級の精神・神経の障害、胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けている場合に介護の費用が支給されます。支給される費用は、介護の状況やサポート環境に応じて下記のように異なります。
|
常時介護の場合 |
随時介護の場合 |
||
|
親族等の介護 |
上限額(円) |
親族等の介護 |
上限額(円) |
|
〇 |
177,950 |
〇 |
88,980 |
|
× |
81,290 |
× |
40,600 |
二次健康診断等給付
事業主が行った定期健康診断において、下記のいずれにも該当する場合に、二次健康診断および特定保健指導の給付がされます。
2.脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること
労災保険の申請手続きについて
前項で解説した通り、政府労災では様々な保険給付の規定があります。ここでは、実際の保険金請求の流れについて紹介したいと思います。
なお、政府労災は様々な保険給付の規定があり、保険給付ごとに申請方法も異なります。本記事では、例として療養補償給付の申請の流れを解説します。
書類を作成する
まずは療養補償給付を請求するのに必要な書類を作成することから始めます。
具体的には、様式第5号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書)を作成し、事業主に証明してもらうことになります。
必要書類は厚生労働省のホームページでダウンロードできますので、ご確認ください。
労災保険指定病院へ提出する
作成した様式第5号を労災指定病院へ提出し、そこで診察を受けます。なお、ここでは被災労働者の費用負担は発生しません。
労災保険指定病院が受領した様式第5号を審査へまわす
具体的には労働局へ審査がまわされることになります。
関係各所へデータが共有される
請求の情報が、労働局から労働基準監督署、厚生労働省へそれぞれデータ共有が図られることになります。
労災保険指定病院へ診療費の支払い
審査完了後、厚生労働省より労災保険指定病院へ診療費が支払われることになります。
療養補償給付については、以上のような流れを経て申請から支払い業務が行われることになります。
なお、被災労働者側でやるべきことは、①~②までの流れで終わりです。
労災保険における損害事例
近年、労災関連事故は減少傾向にあります。
これは事業主の安全配慮義務に対する意識の向上や、企業内の安全衛生教育の結果等、様々な要因が挙げられます。
ただそれでも、依然として様々な労災関連事故が各地で発生しているという事実もあります。
ここで労災関連事故の事例をいくつか紹介したいと思います。
事故概要:ダム建設工事現場の排水管工事において
ダム建設工事現場の排水管工事において、被災者は擁壁上の手すりを撤去する作業を行っていたところ、墜落制止用器具を掛けていた手すりが倒壊し、手すりと共に約10m下の水路に墜落した。
被災者は病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。作業中における労働者の危険防止措置が講じられていなかったことが原因とされた。
業種:その他建設業
災害の種類:墜落、転落事故
被害者数:死亡者数:1人
事故概要:マンションの大規模修繕工事の現場にて足場の解体作業中、
事故概要:製造工場内で稼働中のとある製造ラインにおいて火災が発生。
原因として設備の配線が点検の対象とはなっておらず、当該配線の近くに可燃物が置かれていたことがあげられる。
事故概要:猛暑の日、被災者は倉庫内にて荷下ろし作業を行っていた。
事故概要:畑にて野菜の苗付けの作業をしていたところ、天候が急変し畑に雷が落ちた。
Q&A:業務災害保険に関する質問と回答
これまでの解説で、政府労災の基本的な仕組みを理解してもらえたかと思います。
そのうえで、業務災害リスクに備えるために効果的な、業務災害保険に関する質問を紹介し、回答していきたいと思います。
質問:業務災害保険とは何でしょうか?
業務災害保険とは何でしょうか?会社を設立してから少しゆとりが出てきたので業務災害保険に加入しようと思っております。
業務災害保険の保障内容やどのような時に役に立つのか教えてください。
回答|従業員や役員が業務に起因するケガや病気にり患した場合に、その治療費を補償する保険です。
業務災害保険とは、従業員や役員が業務に起因するケガや病気にり患した場合に、その治療費を補償する保険です。
基本的な補償は死亡・後遺障害補償、入院・通院の補償と、保険会社で取り扱っている労災総合保険と非常によく似たものとなっています。
労災総合保険と並んで、政府労災の上乗せ補償として多くの企業が加入しています。
業務災害保険の大きな特徴の一つとして、政府労災の認定を待たずにスピーディーな保険金の支払いが可能という点が挙げられます。
労災総合保険は政府労災の認定を条件としているので、どうしてもスピード感に欠けてしまいます。
このスピーディーな支払いという点が、業務災害保険の大きな特徴たる所以です。
一般的に政府労災は認定に時間がかかると言われています。
目安として、負傷の場合は3か月、死亡の場合は6か月くらい、精神疾患の場合はさらに多くの時間を要することを覚悟しなければなりません。
一方で業務災害保険であれば、保険金請求書とその他必要資料を提出すれば、長くても一週間以内には保険金を受け取ることができます。
また業務災害保険には、使用者賠償責任保険等の特約で補償内容を充実させることができます。
たとえば使用者賠償責任保険は、従業員が業務中の事故で負傷を負った場合に、会社側に安全配慮義務に問題があると認定されると、会社側は従業員に対し賠償義務が発生します。
このような場合に使用者賠償責任保険で補償することになり、企業防衛を考えるうえで必須の補償といえます。
このほかにも業務災害保険には企業がかかえるリスクに応じて様々な特約を付保することができます。
メンタルヘルス対策費用、ハラスメント対応費用など、保険会社によってさまざまな特色をもった特約があります。
ぜひ参考にしてみてください。
質問:業務災害保険の加入にどんな必要性がありますでしょうか。
業務災害保険の加入にどんな必要性がありますでしょうか。
例えば、建設業での必要であるだったり、製造工業での必要であったり、必要性や保険を使ったときは会社に保険金が支払われる仕組みはどのような仕組みになりますか。
回答|建設業や製造業は、業務災害のリスクの高い業種であるといえます。
建設業や製造業は、たとえば金融業やその他事務職の業務に比べると、業務災害のリスクの高い業種であるといえます。労災保険率をみても比較的高めに料率設定になっています。
保険料率が高いということは、それだけ業務災害のリスクが高いということを示しています。
その意味でも、業務中のケガに備えて業務災害保険に加入しておくことには大きな意味があります。
また、保険金の受取人を法人に設定することも可能です。
従業員が万が一業務中のケガが原因で死亡してしまった場合、死亡保険金を法人が受け取り、災害補償規程に基づいて、法人から従業員の遺族に支払うことも可能です。
さらに、これは建設業にいえることですが、業務災害保険に加入することは、経営事項審査の加点ポイントになるということが大きな特徴です。
経営事項審査とは、国、地方公共団体が発注する公共工事を請け負う為に必ず受けておかなければならない審査制度です。
ここでのポイントの高い業者が大きな規模の工事を受注できるようになるのです。
建設業にとっては、業務災害リスクだけでなく営業的な意味でも、業務災害保険の加入は必須といえます。
質問:業務災害保険と労災保険の違いをわかりやすく教えてください。
業務災害保険と労災保険の違いをわかりやすく教えてください。
一般的には仕事上の事故やケガなどに関しては労災保険の適用になると思います。
労災保険と業務災害保険との違いがいまいちわかりません。
よく労災の上乗せのような話を聞いたことがありますが、業務災害保険と労災保険は同時に加入するメリットはあるのでしょうか。
回答|大きな違いは、業務災害保険は任意加入なのに対し、労災保険は強制加入だという点です。
業務災害保険と労災保険の大きな違いは、業務災害保険は任意加入なのに対し、労災保険は強制加入だという点です。ここで労災保険の補償内容を下記に示します。
●療養補償給付・・・病院での入通院の費用、手術代を補償
●休業補償給付・・・日額給与の80%を補償
●障害補償給付・・・身体に障害が残ったとき、その等級に応じて補償
●遺族補償給付・・・従業員が死亡した場合、その遺族への補償
大まかには上記の補償内容となります。
ただ、実際に業務災害が起こった場合、補償額として労災保険だけではとてもカバーしきれない金額が必要になります。
このように労災保険を上回る部分をカバーする意味で、業務災害保険が必要になるのです。
業務災害保険が労災の上乗せと言われる所以です。
さらに業務災害保険には労災保険にはない補償が充実しています。
たとえば労災保険には慰謝料の補償や訴訟等にかかる費用の補償はありません。
業務災害保険では、このような費用も補償対象となり、特約を付加することで、さらに補償を広げることができます。代表的な特約を下記に紹介します。
使用者賠償責任補償特約
使用者賠償責任補償特約・・・補償対象者が業務上の災害によって身体に障害を負い、会社側に責任があるとして損害賠償を求めてきた際に、その賠償金等の費用を補償
雇用慣行賠償責任補償特約
雇用慣行賠償責任補償特約・・・補償対象者が被った差別的行為、ハラスメント等に起因して事業者が負担する賠償損害を補償
メンタルヘルス対策費用
メンタルヘルス対策費用・・・政府労災で認定された精神障害により休職した補償対象者の職場へ向けた対策にかかった費用を補償
事業者費用補償特約
事業者費用補償特約・・・補償対象者の身体障害等により、事業者が臨時に負担した葬儀費用等を補償
労災保険は強制加入なので加入の是非は言うまでもありませんが、業務災害保険もしっかり加入して、従業員の業務災害・通勤災害の補償を充実させましょう。
質問:業務災害保険の保険料を安くするためにはどのような方法がありますか?
現在建設業を営み損害保険の見直しや整理を行っております。
この中で業務災害保険の保険料が高いことに気づきました。この業務災害保険の保険料を安くするためにはどのような方法で安くすればよろしいでしょうか。
コスト削減をよりできるような方法や選択肢加入方法を教えてください。
回答|保険料を少しでも抑える代表的な方法を2つ紹介します。
建設業の業務災害保険は、他の業種と比較すると業務災害のリスクが高く、質問者様が仰る通り、保険料は高いです。
そうはいっても従業員の保護、企業防衛を考えるうえで必須の保険であるといえます。
高い保険料を少しでも抑える代表的な方法を2つ紹介します。
●リスク診断割引を使う
●商工団体に加入する
リスク診断割引を使う
業務災害保険はどこの保険会社の取り扱い商品であっても、リスク診断割引を用意しています。たとえば下記のような質問項目に対し、該当すれば割引ポイントが加算されるといった内容です。
保険会社によっては最大で20~30%の割引になるところもあります。加入を検討する際には必ず保険会社や保険代理店に確認しましょう。
質問例1)ISO 9001、ISO 14001、ISO 22000、ISO45001、HACCPのいずれかの認証を取得しているか。
質問例2)安全衛生管理規定を備えているか。
質問例3)職場の安全管理へ取り組んでいるか。
商工団体に加入する
日本商工会議所、全国商工会連合会といった商工団体を経由して加入することで、スケールメリットを生かした割引を受けることができます。
最大で50%超の割引を受けることができます。商工団体に加入していなければ、割引を受けるために商工団体に加入することもひとつの方法です。
たとえば全国中小企業団体中央会の傘下の全国ビジネスネットワーク協会であれば、年会費3,000円で加入することができます。ぜひ検討してみてください。
一般社団法人 全国ビジネスネットワーク協会 (nbna.jp)
このように、業務災害保険には保険料を抑えるための方法があります。
保険会社ごとに特色のある割引制度が用意されていますので、必ず割引制度の有無は確認しましょう。