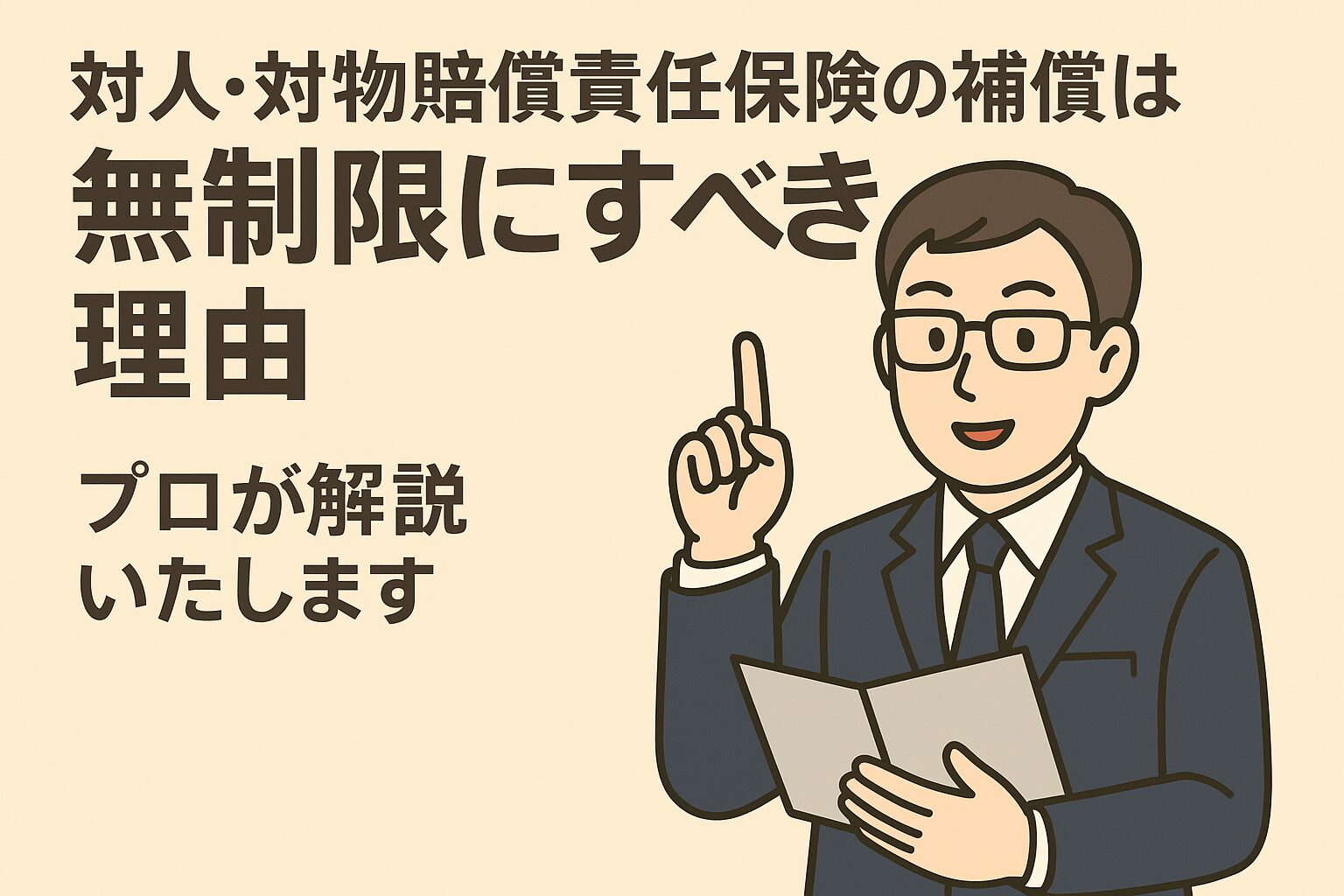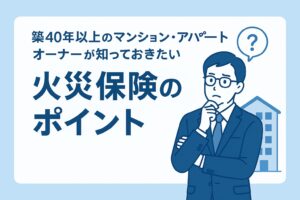個人事業主に必要な損害保険は?どんな損害?選び方?保険料は経費にできますか?プロが分かりやすく解説いたします。


コロナ禍によるリモートワーク普及の影響もあり、ネットで副業をする人が増えてきました。
副業のやりがい、仕事環境の充実さに惹かれ、脱サラを決意し、副業を本業にし始めた人も多いのではないでしょうか。
しかし個人事業主になると、恵まれた環境の反面、万が一のトラブルはすべて自分で解決しなければなりません。
今回の記事では、個人事業主を取り巻くリスクにスポットライトをあてて、深く堀り下げていきたいと思います。
個人事業主に必須の損害保険を、どこよりもお得に加入できる方法があります!
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
目次
個人事業主が想定すべきリスクとは
まず、個人事業主として最低限考えなければならないリスクを4点紹介します。
火災、台風、水災等、自然災害による損害のリスク
まず、火災や台風等といった自然災害によって、事務所建物や設備・什器、備品に損害を被るリスクを考えなければなりません。
業種によっては営業を存続できないほどのダメージを負ってしまいます。たとえば飲食業等であれば、火災によって店舗が焼失してしまった場合、営業をすることができません。
上記のように、特に火を使う業種であればまず第一に考えておかなければならないリスクといえます。
自動車事故のリスク
業務で自動車を使う場合、交通事故のリスクを考えなければなりません。
交通事故によって相手に怪我をさせてしまったり相手のモノを壊してしまったり、自分自身が怪我をしてしまったりと、様々なリスクが想定されます。
運送業や移動手段として日常的に自動車を使用する頻度の高い方は、常に交通事故のリスクを考えなければなりません。
賠償責任を負うリスク
業務遂行中のうっかりしたミスで、第三者に損害を与えてしまうリスクが該当します。
たとえば飲食店の場合を例に考えてみると、具体的に下記のような賠償事例が想像できると思います。
・提供した料理が原因で、お客様が食中毒を起こしてしまうリスク
・お客様から預かった私物を汚損したり紛失してしまうリスク
・従業員が料理を提供する際、不注意でワインをこぼしてしまい、お客様の洋服を汚損してしまうリスク
・店舗施設内の管理不備が原因で、お客様が転倒し、怪我を負ってしまうリスク
上記は飲食店に絞ってリスクを考察してみましたが、業種が変われば当然想定されるリスクも変わります。
今一度、自分自身の事業について、想定されるリスクの棚卸しをしてみましょう。
情報漏洩リスク
いまや情報を取り扱わない事業はないと言っても過言ではありません。情報とは、お客さまの個人情報だけでなく、取引先の法人・個人情報をも含みます。
こういった情報の管理は事業を営む者にとっては必須の義務といえます。いざ情報が漏洩した場合、その件数が多ければ多いほど損害賠償費用は多額になります。
情報を扱うすべての事業において対策は必須となります。
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
それぞれのリスクと損害額について考察
上記で様々なリスクについて考察してきましたが、ここでそれぞれの事故の具体例と想定される損害額についても触れていきたいと思います。
火災、風災等、自然災害による事故の事例
事例1:タバコの火の不始末でぼやが発生。建物、設備・什器にそれぞれ損害を受ける。
被害総額:1,969,500円
事例2:台風によって飲食店店舗の外壁、窓ガラス、造作設備が損害を受ける。
被害総額:6,690,000円
事例3:連日続いたゲリラ豪雨により、事務所室内に浸水被害。建物、設備什器、商品にそれぞれ損害を受ける。
被害総額:4,880,000円
自動車事故事例
事例1:住宅街を配送業務中、交差点右から出てきた自転車に衝突。自転車の破損、自転車運転者の腰と右ひざに怪我を負わせてしまった。
被害総額:225,970円(過失割合9:1)
事例2:取引先への移動中、ふと気が緩み、脇見運転をしてしまい、赤信号で停車中の前方車両に衝突してしまった。前方の車両は自走不可の損害を負い、運転者も救急車で搬送されることになった。
被害総額:1,926,330円
事例3:赤信号にて停車していたところ、左より大型トラックが交差点を右折侵入。角度が浅かったため、自動車の右側面にぶつけられてしまった。しかしトラックの運転者は真摯に示談に応じようとせず、弁護士に相談した。
被害総額:322,240円(弁護士への相談費用を含む)
賠償事故事例
事例1:飲食店にて、生食用のカキを提供したところ、集団食中毒が発生。保健所の調べによると、提供した生食用のカキがウイルス感染していたことが発覚。消費者が当該飲食店を相手取って損害賠償請求を起こす。
被害総額:約600万円
事例2:結婚式場にて、お客様より預かったコートを紛失してしまい、コートの相場価格を弁償することになった。
被害総額:約20万円
事例3:事務所にて取引先の来客対応中、コーヒーを出そうとした従業員が誤ってこぼしてしまい、相手方の衣類を汚損させてしまった。
被害総額:2万円
情報漏洩事例
事例1:顧客情報を取り扱っている士業事務所にて、PCがウイルス感染し、メールは誤送信され、PC内に保存していた取引先や顧客の情報が漏洩してしまった。
被害総額:約500万円
事例2:コンビニにて車を停めていたところ、車上荒らしに遭い、個人情報500人が入ったPCが盗難されてしまった。
被害総額:約200万円
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
それぞれのリスクに備える保険
ここで、これまで挙げたリスクに対し、カバーできる保険について解説していきます。
火災保険
火災、台風、水災等、自然災害によって、建物や設備什器、商品製品が損害を負った場合に備えるには、火災保険が最適です。
火災保険とは、火災や風災、水災といった自然災害などによる、建物や家財、設備什器・商品製品などの損害を補償する保険です。ただし、地震や噴火、津波などによる損害、地震を直接の原因とする火災は補償されない点に注意が必要です。
この場合、別途地震保険への加入が必要になります。
モノを作る事業はもちろん、どのような業種であっても最低限パソコンや机、椅子といった什器備品は使用します。
自然災害等で焼失した場合に備えて、火災保険をしっかり付保しておきましょう。
自動車保険
自動車保険は、自動車の運転中の事故などによって生じた損害を補償してくれる保険です。
自動車の事故によって、他者に怪我を負わせてしまったり、他者の自動車に損害を与えてしまうこともあるでしょう。
逆に自分自身が怪我を負ってしまったり、自分の自動車が損害を負ってしまったりすることも想定されます。そういった損害を総合的に補償するものです。
なお、自動車には自賠責保険という強制加入の保険があり、一定額の対人事故が補償されます。
しかし自賠責保険の補償内容はあくまで最低限のものであり、決して充分な補償とは言えません。
自動車保険は自賠責保険の補償内容を超えて補償してくれるものです。
自動車保険に関しては、どのような業種であっても自動車を運転する可能性があるのであれば、しっかり付保しておきましょう。
自動車を運転する以上、被害者にも加害者にもなりえます。どんなに安全運転をしている方でも事故をもらってしまう可能性があるからです。
賠償責任保険
賠償責任保険とは、偶発的な事故により、他人を死傷させたり、他人のモノに損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害額に対して支払われる保険をいいます。
賠償責任保険には様々な種類があります。
最低限おさえるべき賠償責任保険について説明します。
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
生産物賠償責任保険(PL保険)
製造・販売する生産物や工事が結果で起こった事故による賠償責任を補償してくれる保険です。
飲食店における食中毒の補償であったり、防水工事における工事不備による水漏れ損害が代表的な損害事例です。
施設賠償責任保険
施設の欠陥等や仕事の遂行が原因となって他者にケガを負わせてしまったり、他者のモノに損害を与えたりした場合に、賠償金等の費用を補償する保険です。
受託者賠償責任保険
他人から預かった物(受託物)を保管中、誤って破損や汚損、紛失、火災による焼失、盗難などによって、その受託物を他人に返せなくなった場合に負う法律上の賠償責任を補償する保険です。
請負業者賠償責任保険
工事等の請負業務遂行中に発生した偶然な事故、または請負作業遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然の事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物に損害を与えた場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に被る損害を補償するための保険です。
事業を営んでいる以上、賠償責任を負うリスクをゼロにすることは難しいです。
また、賠償責任に関しては、業種によって想定されるリスクが様々です。リスクの洗い出しが難しいようなら、思い切って保険会社に相談して、適切で合理的な備えを準備しましょう。
個人情報漏洩保険
事業主が管理している個人情報の漏洩によって生じる、損害賠償や訴訟費用を補償する保険です。
特約を付保することで、原因調査費用や初期対応のサポート費用を補償することもできます。
個人情報を多く取り扱う業種にとっては必須の保険といえます。PCのウイルス感染だけでなく、人為的なうっかりミスによっても情報漏洩してしまうリスクはあります。
しっかり備えておきましょう。
個人事業主に必須の損害保険を、どこよりもお得に加入できる方法があります!
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
Q&A:「個人事業主に必要な損害保険」の質問と回答をわかりやすく解説
個人事業主として仕事をしていると、売上や経費管理はもちろんのこと、万一のトラブルへの備えも欠かせません。
事業を順調に運営していても、火災や自然災害、取引先やお客様とのトラブルなど、予測不能な出来事は突然やってきます。
しかも、会社員と違い、事故や損害が発生したときに守ってくれる「会社の傘」はありません。
発生した損害や賠償は、すべて自分で負う必要があるという点が、個人事業主にとって理解しておくべき最も重要な点です。
そのようなリスク対策として頼りになるのが損害保険です。損害保険は、建物や設備など自分の財産を守るだけでなく、第三者に損害を与えてしまった場合の賠償や、災害で事業が止まったときの経済的な損失までカバーすることができます。
しかし、損害保険といっても種類や内容はさまざまで、何を選べばよいのか迷う人も多いでしょう。そこで本記事の最後に、「個人事業主に必要な損害保険」というテーマで、よくある疑問を質問&回答形式でわかりやすく解説・紹介します。
自分の事業に必要な補償を見極め、いざという時に事業と生活を守るための参考にしてください。
質問①:そもそも、個人事業主に損害保険は必要ですか?
個人事業主にとって、損害保険は必要なのかどうかについて質問です。自分はサラリーマンを10年ほど勤めた後、つい先日、とある士業として独立しました。
士業は基本的に事務仕事なので、他人の物を壊すとかケガを負わせるといった賠償リスクはなく、損害保険に加入する必要性はほぼないのでは、と個人的には思っています。
ただ、まったくの無保険ということに対して、漠然とした不安を感じているのも事実です。個人事業主にとって、損害保険は必要なのでしょうか?
回答|自身の事業におけるリスクを深堀りし、適切に準備しましょう。
個人事業主にとって損害保険は「事業を守るための安全装置」とも言えるほど重要です。
その理由は、会社員と違い、個人事業主はあらゆるリスクの最終責任を自分一人で負う立場だからです。
会社員の場合、業務上のミスや事故が発生しても、企業が損害を肩代わりしてくれることがほとんどです。
たとえば業務中のケガであれば、その治療費は政府労災の補償を得られたり、その他、賠償事故を発生させたとしても、会社加入の損害保険等でカバーしてくれていました。
しかし、個人事業主の場合は、万一の事故や損害による賠償金・修理費・休業損失をすべて自己資金で賄わなければなりません。
さらに、事業活動は思った以上にリスクにさらされているものです。
たとえば、以下のようなケースを想像してみてください。
・店舗や事務所での事故
来客が事務所の床の段差で転倒しケガをした場合、治療費や慰謝料を請求される可能性があります。
・提供した製品やサービスによる損害
製造した商品が欠陥で発火し、購入者の家財を損傷させた場合、数百万円以上の賠償が発生することもあります。
・設備や財産の損害
火災・台風・水害などで店舗や事務所、在庫商品が被害を受けると、修復・再購入に多額の費用が必要になります。
こうした事故は、自分がどれだけ注意していても相手や自然災害によって突然起こってしまうこともあるため、完全に防ぎきることはできません。
特に個人事業主は事業資金と生活資金が直結しているため、ひとたび大きな出費や賠償責任が発生すると、事業継続が困難になる危険も隣り合わせとなります。
損害保険は、こうした予測不能なリスクに備え、「もしも」のときに事業と生活を守るクッションの役割を果たします。
実際、損害保険に加入していたことで、数百万円規模の賠償金を自己負担せずに済んだという事例も少なくありません。
要するに、個人事業主にとって損害保険は「加入すべきかどうかを迷うもの」ではなく、事業を継続するための必須インフラといえます。
質問者様仰る通り、士業のお仕事は他の業種と比べて危険の少ない仕事かもしれません。
しかし例にあげたように、事務所に来客があった際の事故であったり、車での移動中の賠償事故は当然想定されます。
今一度、業務中に考えられるリスクを深堀りし、適切な備えをすることを強くお勧めします。
質問②:どんな種類の損害保険が考えられますか?
脱サラして現在フリーで生計を立てている者です。リスク対策として、損害保険に加入して備えなきゃと思っています。
ただ、損害保険はたくさん種類があって、内容も複雑なので、自分の中で整理できないでいます。
個人事業主にとって必要なのは、どんな種類の損害保険が考えられますか?アドバイスがほしいです。
回答|自分の財産の保険、第三者に対する賠償責任の2つの軸で考えましょう!
個人事業主に必要な損害保険は、事業内容や業種によって異なります。
しかし、大きく分けると「自分の財産を守る保険」と「第三者への賠償責任を補償する保険」の2つの軸で考えると整理しやすくなります。
自分の財産を守る保険
事業で使う設備・建物・商品・車両などが、火災・自然災害・盗難などで損害を受けた場合に備える保険です。
具体的な損害保険をいくつか例示します。
◆事業用火災保険
店舗や事務所、倉庫などが火災や落雷、風災・水災によって被害を受けた場合に修復費用を補償します。事業用の什器や商品、在庫も補償対象にできるため、小売業や飲食店には特に重要です。注意点として、自宅兼事務所の場合は「事業用の部分」が保険対象になるよう契約内容を確認する必要があります。
◆動産総合保険
事業用の機械やパソコン、工具などが火災・盗難・破損などで損害を受けた場合に補償されます。建物ではなく中身(設備・機材)を指定して補償対象とするため、フリーランスのデザイナーやカメラマンなど、高価な機材を持ち歩く職種に適しています。
◆自動車保険
営業や配送で使う車の事故に備える保険です。特に営業車は事故の頻度が高く、対人・対物賠償は「無制限」に設定するのが基本です。車両保険を付けておくと、自分の車の修理費もカバーできます。
第三者への賠償責任を補償する保険
業務中や事業施設内で他人や他人の物に損害を与えた場合、賠償金や訴訟費用をカバーします。
具体的な損害保険をいくつか紹介します。
◆施設賠償責任保険
店舗や事務所での事故(例:お客様が店内で滑って骨折)に対する賠償を補償します。来客型のビジネス(飲食店、美容室、学習塾など)では必須クラスの保険です。
◆事業活動包括賠償責任保険
施設内だけでなく、業務中の外出先や作業現場での事故も対象になる保険です。工事業者、出張サービス業、イベント運営者などに適しています。
◆生産物賠償責任保険(PL保険)
製造・販売・提供した商品やサービスが原因で事故や損害が発生した場合に補償します。
例)食品の食中毒、家電製品の発火、家具の破損によるケガなど。
製造業・飲食業・ネットショップ運営者など、物や食品を扱う業種では特に重要です。
◆請負業者賠償責任保険
建設・工事業者向けの保険で、作業中に第三者に損害を与えた場合の賠償をカバーします。
例)工事中に工具が落下して通行人にケガをさせた場合など。
日常生活や事業外もカバーできる保険
個人事業主の場合、業務内外の境界線が極めて曖昧です。
事故内容(または事故報告の仕方)によっては保険金の支払いを否認されてしまうリスクもあります。下記の保険に加入し、事業中だけでなく事業外もしっかり備えておきましょう。
◆個人賠償責任保険
自転車事故、日常生活での他人への損害などを補償します。業務外の事故でも事業主本人の生活を守る意味で有効です。
火災保険や自動車保険の特約としてセットされることが多く、年間数千円で加入できる、コスパの良い保険です。
保険選びのポイント
個人事業主にとって、適切な損害保険に加入することはとても重要です。
下記のポイントを参考にしてください。
・事業形態や業種に合った保険を選ぶ(飲食業=PL保険必須、工事業=請負業者賠償など)
・補償範囲と免責金額を確認(「その事故は対象外」にならないよう注意)
・事業の成長に合わせて補償額を見直す(売上増や設備増に伴い、必要額も変動)
つまり、個人事業主が選ぶべき損害保険は「自分の財産を守る保険」と「他人への賠償責任を守る保険」の両方をバランスよく組み合わせることが重要です。
どちらか一方しか加入していないと、カバーできない事故で事業が一気に立ち行かなくなる可能性があります。
個人事業主にとって、特に独立したばかりの人にとっては、どんな損害保険・補償内容が適切なのか、わかりにくい場合が多々あるかと思います。
決して自己判断せず、保険会社や保険代理店に相談した上で、適切な補償内容で加入するようにしましょう。
個人事業主に必須の損害保険を、どこよりもお得に加入できる方法があります!
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /
質問③:損害保険はどのように選べばよいですか?
フリーランスで活動している者です。リスク対策として、いくつかの損害保険に加入しています。
先日、飛び込み営業で保険屋さんが来たのですが、自分の加入状況を説明したところ、保険料をもっと安く下げられるとの説明を受け、さらに新しい種類の保険まで提案を受けました。
このようなこともあり、果たして自分のいまの加入状況が適切なのか疑問を持っています。適切な損害保険の選び方について、教えてください。
回答|無駄なく不足のない保険選びの方法を紹介します!
損害保険の選び方は、単純に「保険料の安さ」で決めるものではありません。個人事業主の場合、事故や災害が事業継続に直結するため、自分の事業に潜むリスクを正しく把握し、そのリスクを十分にカバーできる保険を選ぶことが何より大切です。
ひとつの参考事例として、無駄なく、かつ不足のない保険選びができる手順を、6つのステップに分けて紹介します。
その1:自分の事業リスクを洗い出す
まずは事業の種類・場所・規模から発生しうるリスクを整理します。リスクは大きく下記の3種類に分けられます。
◆財産リスク
火災、自然災害、盗難による店舗・事務所・在庫・設備の損害など
◆賠償責任リスク
来客や取引先へのケガ・物損、商品やサービスによる事故で第三者に対する損害賠償責任の発生など
◆事業中断リスク
災害や事故で営業できなくなり、収入が途絶えるなど
【具体例】
・飲食店 → 火災・食中毒・来客事故
・工事業 → 作業中の物損事故・第三者へのケガ
・フリーランスデザイナー → 高額機材の破損・盗難
その2:必要な保険種類を特定する
リスクが整理できたら、そのリスクをカバーできる損害保険を選びます。例えば、火災リスクがあるなら「事業用火災保険」、製品リスクがあるなら「PL保険」、現場作業中の事故が想定されるなら「請負業者賠償責任保険」といった具合です。
ここで重要なのは、補償の重複と漏れを避けることです。同じ補償内容を二重に契約すると保険料が無駄になりますし、逆に抜け落ちがあると、いざというときに自己負担が発生します。
その3:補償範囲と免責金額を確認
保険商品のパンフレットや約款を確認し、次の点を必ずチェックします。
・どんな事故・損害が対象になるか(補償対象外の事例も明記)
・補償上限額(例:対人賠償無制限、対物1億円など)
・免責金額(自己負担額が高いと小規模事故は補償されない)
・特約の有無(業務外の事故や休業損失までカバーできる場合あり)
その4:保険料とのバランスを取る
補償内容を充実させると、その分保険料も高くなります。しかし、保険はあくまで「万一の大損害」に備えるものなので、日常的に自己負担できる小さな事故には目をつぶり(免責金額の設定)、その分保険料を抑える方法も有効です。つまり、「低確率だけど発生したら致命的な損害」に重点を置くことで、費用対効果が高くなります。
その5:専門家に相談する
損害保険は商品によって補償内容や条件が細かく異なります。特に事業用保険は一般の火災保険や自動車保険と違い、設計の自由度が高いため、保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して、自分の事業に合わせた補償設計をするのが安心です。その際、事故例や過去の支払実績を聞くと、実際に役立つ保険かどうかの判断材料になります。
その6:定期的に見直す
事業の形態や規模は変化します。売上増、設備増、スタッフ増などのタイミングで補償額を見直さないと、保険が現状に合わず「足りない」状態になりかねません。
目安として、最低でも1年に1回の見直しをおすすめします。
結論
ここまでの手順をまとめると、損害保険は「とりあえず入っておく」ものではなく、下記の6つのステップを意識して選びましょう。
・リスク洗い出し
・必要な種類特定
・補償範囲確認
・保険料とのバランス
・専門家相談
・定期的見直し
この流れで損害保険をしっかり選択することで、無駄がなく実用的な保険設計が可能になります。ぜひ参考にしてください。
質問④:保険料は経費にできますか?
個人事業主になりたての者です。自分のまわりには個人事業主として活動している仲間がたくさんいるので、刺激を受けつつ参考にしてがんばって行こうと思っております。
そんな仲間について共通して見る光景として、レシートや領収書をしっかり取って、経費を少しでもたくさん計上しようとしている姿がありますが、その観点で質問です。
支払った保険料は経費に計上できるのでしょうか?経費計上が可能なのであれば、節税の一環として補償を厚くした保険加入も良いかなと思っています。
回答:事業の為の保険は原則として経費計上できますが、条件もあります。
結論から言えば、事業のために加入した損害保険の保険料は、原則として必要経費に計上できます。
個人事業主は、事業に直接関係する支出を「必要経費」として所得から差し引くことができますが、保険料もその一つに含まれます。
ただし、事業用と私用が混在する場合や保険の種類によっては、全額を経費計上できない場合があるため注意が必要です。以下、保険と経費についてのポイントを解説します。
経費として認められる条件
国税庁の基準では、保険料が経費になるためには次の条件を満たす必要があります。
・事業に直接関係していること
→ 店舗や事務所、事業用車両、事業活動に必要な機械設備などを対象にした保険。
・事業遂行上の必要性があること
→ 業務上のリスクや法律上の義務に対応するために加入している保険。
経費計上できる保険の具体例
上記の条件を満たす可能性の高い損害保険は下記となります。
・事業用火災保険(店舗や事務所の建物・設備)
・動産総合保険(機材・什器)
・施設賠償責任保険
・生産物賠償責任保険(PL保険)
・自動車保険(事業用車両)
・請負業者賠償責任保険
・事業休業補償保険(災害や事故による休業損失に備えるもの)
事業と私用が混ざっている場合の扱い
自宅兼事務所の火災保険や、業務と私用を兼ねる車の自動車保険などは、事業分と私用分を按分計算して経費計上します。
【按分の例】
・自宅兼事務所(面積比)
事務所面積 20㎡/総面積 80㎡ → 事業割合 25% → 保険料の25%を経費計上
・車両(走行距離比)
年間総走行距離 10,000kmのうち、業務使用 6,000km → 事業割合 60% → 保険料の60%を経費計上
なお、按分の根拠は帳簿や記録(走行距離計や間取り図)で説明できるようにしておくことが大切です。
経費計上できない(または一部しかできない)保険
保険であれば何でも経費計上できるわけではありません。
具体的には、下記のような保険は経費計上を否認される可能性が高いものです。
・個人の生命保険や医療保険(事業用でない)
・自宅専用部分の火災保険
・家族のための個人賠償保険(業務外の事故に備えるもの)
これらは事業に直接関係しないと判断され、必要経費とはみなされません。
記帳・申告時のポイント
経費計上を適切にするうえで、記帳・申告の際のポイントがあります。
・勘定科目は「保険料」で記載することが一般的
・年払い保険料の場合、期間が翌年にまたがる場合は月割計算で処理
・領収書や契約書は必ず保管(税務調査で事業用か否かを確認される可能性あり)
結論
ここまでの解説をまとめると、下記のように整理できます。
・事業に直接関係する損害保険の保険料は経費になる
・事業と私用が混在する場合は按分計算が必要
・私的な保険は経費にできない
・根拠資料の保存が重要
保険料の経費計上は節税にもつながりますが、誤って全額計上すると税務署から否認されるリスクがあります。
正確な按分や証拠書類の保管を心がけることが、安心して経費化するポイントです。
質問⑤:保険加入でよくある失敗例はありますか?
個人事業主の保険について相談です。リスク対策として保険加入が必要なのは理解していますが、手あたり次第に加入するのも違う気がします。
保険加入でよくある失敗例等あれば教えてください。
回答:失敗例を5つ紹介し、その対策についても解説します!
個人事業主が損害保険に加入する際には、意外と多くの失敗例があります。これらの失敗は、「なんとなくで契約した」「内容をよく確認しなかった」「見直しを怠った」といった理由で起こることがほとんどです。結果として、事故や災害が発生したときに「保険に入っていたのに補償されない」という事態になりかねません。
以下によくある失敗例と、その原因・対策を詳しく解説します。
失敗例その1:補償対象外の事故だった
【具体例】
・火災保険に加入していたのに、水害で店舗が浸水しても補償されなかった。
・PL保険に入っていたが、海外での事故は対象外だった。
【原因】
保険には必ず「補償対象外(免責)」の条件があります。契約時にこれを確認せず、すべての事故がカバーされると思い込んでしまうことが原因です。
【対策】
・約款や重要事項説明書で「補償されない事例」を必ずチェックする
・業種特有のリスク(例:台風被害、海外輸出)に対応できる特約を付ける
失敗例その2:補償額が足りなかった
【具体例】
・対物賠償1,000万円で契約していたが、実際の損害額が3,000万円となり、差額を自己負担した。
【原因】
「保険料を安くしたい」という理由で補償額を下げすぎると、大きな事故で補償不足になります。特に近年は損害賠償額の高額化が進んでおり、数千万円〜億単位の請求も珍しくありません。
【対策】
・対人・対物賠償の補償額は原則「無制限」に設定する
・財産の補償額は再取得価格(新品を買い直す金額)で設定する
失敗例その3:事業形態の変更に伴う見直しをしていなかった
【具体例】
・開業時は自宅で作業していたが、事務所を借りたのに火災保険の対象を変更していなかった。
・小規模カフェからテイクアウト専門店に変えたが、PL保険の補償内容が旧業態のままだった。
【原因】
保険は契約時の条件に基づいてリスクを計算します。事業形態や規模が変わるとリスクも変化しますが、その更新を怠ると補償が不十分になります。
【対策】
・最低でも年に一度は保険内容を見直す
・店舗移転、従業員増、取扱商品変更などがあったらすぐ代理店に連絡する
失敗例その4:事業用と私用を混同していた
【具体例】
・自宅の火災保険で事務所の什器もカバーされると思っていたが、実際は対象外だった。
・個人用自動車保険で配送中の事故をカバーできると思っていたが、業務使用は対象外だった。
【原因】
事業用リスクは、個人用の保険では補償されないことが多いのに、そこを確認せずに契約してしまう。
【対策】
・保険会社に「業務で使う」ことを明確に伝えて契約する
・自宅兼事務所の場合は事業部分の補償を追加する
失敗例その5:保険料だけで選んでしまった
【具体例】
・最安の保険を選んだら、免責額が高くて小さな事故は補償されなかった。
【原因】
保険料が安いのは、補償範囲が狭い、免責額が高い、補償額が低いといった条件があるということを、しっかり認識していなかった。
【対策】
・保険料と補償内容のバランスを見る
・年間数千円の差で数百万円の補償差が出るケースもあるため、安さだけで選ばない
結論
損害保険は「契約して終わり」ではなく、契約時の確認不足と見直し不足が失敗の大きな原因です。
このような失敗を防ぐためには、最低限下記の5つのポイントを意識しましょう。
・補償対象外の条件を把握する
・補償額を十分に設定する
・事業変更時はすぐに保険を見直す
・事業用と私用を混同しない
・保険料だけで判断しない
この5つを意識することで、大きな失敗は防ぐことはできます。
あとは各々の補償に対する考え方をもとに、補償設計をアレンジしていくのもひとつです。ぜひ参考にしてください。
まとめ
冒頭にも触れたように、コロナ禍によるリモートワークの浸透等によって、個人が開業しやすい土壌が育まれてきました。
開業前の会社員の時であれば、万が一のリスクに際しては、基本的に会社が備えていました。
しかし独立をすると、自分自身で全責任を負わなければなりません。
自分の業種がどのようなリスクがあるのかをしっかり把握し、備えておきましょう。
その備えとして、保険をうまく活用するようにしましょう。
「割安に入りたい」という方は、LINEまたはメールからお気軽にお問い合わせください。
LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。
\ オンラインでのご相談も可能です /