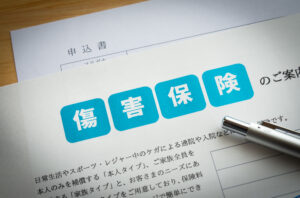損害保険金請求のポイントや査定金額に不満の際の対応方法は?現場でよく聞かれる質問をピックアップして回答します。


万が一の補償として、多くの人が何らかの保険に加入していることと思います。
マイカー所有者は自動車保険、住まいには火災保険、スポーツを趣味としている人は傷害保険と、保険と無縁の生活を送る人はきっといないでしょう。
損害保険は、万が一の災害や損害があった時に経済的な補償をもたらしてくれる、社会的に意義のあるものです。
ただし保険会社へ損害報告をしても、必ずしも損害被害者の希望通りの査定結果が得られるとは限らないのです。
保険金請求をするにあたってのポイントをおさえていないがために、希望よりも少ない査定金額となってまったという事例は数多くあります。
さらに言うと、本来は保険金の支払い対象となる事故であるのに、保険金請求をしていないという事例すらもあるのです。
今回の記事では、保険金請求をする際のポイント、納得のある結果が得られない場合の対応について、火災保険を例にあげて解説します。
記事の最後に、筆者が損害保険の現場でよく聞かれる質問をピックアップして回答をしたいと思います。
目次
火災保険とは
まず、本記事の前提となる火災保険とはどういうものかについて解説していきます。
火災保険の対象となるもの
火災保険で補償の対象としているのは、以下の2点です(家庭用の火災保険の場合)。
・建
・家財
建物のみを補償対象とすることも、家財のみとすることも、両方とも補償対象とすることもできます。
ここは、居住者の特性や補償に対する考え方で変わる部分です。たとえばマイホームを住宅ローンで購入した方は、融資を組んだ銀行の要請もあり、建物を補償対象とすることは必須となりますし、家財もほとんどの方が補償対象とします。
一方で賃貸物件に居住される方は、自分の所有物である家財のみを補償対象とします。
どういうリスクを補償するか
火災保険という名称がついているのでわかりにくいですが、実は火災以外にも様々なリスクに対して補償してくれるのです。
保険会社によりリスク区分は細かい点で異なりますが、概ね下記の6つのリスク区分を補償対象としています。
①火災、落雷、破裂・爆発
隣家からのもらい火によって建物が焼失、落雷によって家電製品が壊れてしまった等、火災や落雷等に起因する損害をいいます。
②風災、雹災、雪災
台風によって窓ガラスが破損した、大雪の重みで屋根がつぶれてしまった等、風や雪による損害をいいます(ただし、窓を開け放していた結果としての吹込みや雨漏りは、補償の対象となりません)。
③水ぬれ
トイレに異物の流してしまった結果、排水管が破損し、結果的に部屋が水浸しになってしまった等、給排水管設備の詰まりや破損に起因する水濡れ損害をいいます。
④盗難
自宅建物内に置いてあった財布や家財道具が盗難被害にあってしまった場合、空き巣目的で窓ガラスが割られた場合等、盗難に起因する損害全般をいいます。
⑤水災
台風やゲリラ豪雨、土砂崩れ等によって発生した浸水被害をいいます。
⑥破損、汚損等
これまでに紹介した①~⑤には該当しないが、急激・偶然・外来による損害をいいます。
たとえば建物の外壁に落書きされてしまった、ハンドル操作を誤った自動車が自宅に突っ込んできた等といった事故が想定されます。
参考:地震保険
火災保険に加入すると、原則として地震保険にも加入することになります。
地震保険は不要とする場合のみ、別途署名をすることで地震保険に加入しないという選択もできます。
地震保険の補償内容は、地震・噴火または地震に起因する津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われるものです。
つまり、保険の対象が火災の損害を被ったとしても、そもそもの火災の原因が地震によるものである場合は、地震保険で支払われることになり、火災保険からは保険金は支払われないのです。
この点はよく勘違いされる部分なので、しっかり押さえておきましょう。
また地震保険は損害の認定の面で火災保険と相違があります。
火災保険は実際に発生した損額をベースとして支払保険金を査定するのに対し、地震保険では損害の程度に応じて以下の4区分での支払いとなります。
・全損
・大半損
・小半損
・一部損
全損
建物の50%以上、家財全体の80%以上の損害が要件。支払保険金額は地震保険金額の100%。
大半損
建物の40%以上50%未満、家財全体の60%以上80%未満の損害が要件。支払保険金は地震保険金額の60%。
小半損
建物の20%以上40%未満、家財全体の30%以上60%未満の損害が要件。支払保険金は地震保険金額の30%。
一部損
建物の3%以上20%未満、家財全体の10%以上30%未満の損害が要件。支払保険金は地震保険金額の5%。
地震保険は、民間の保険会社と国が共同で運営されている、公共性が高い制度です。
地震はひとたび発生すると、損害は震源地を中心に広範囲にわたるという特徴があります。
このようなケースでは、簡易迅速に保険金の支払い事務を進める必要があります。
このような事情から上記の4つの区分設定となっているのです。
損害発生時の保険金請求の流れ
これまで解説してきたように、火災保険(地震保険も含め)は住まいに自然災害等の損害が発生した場合に、金銭的な補償をもたらしてくれるものであることがわかったかと思います。
ただ、具体的にどのような流れで保険金を請求したらよいのか、どういった資料を用意したらよいのかについて、しっかり理解している人は、きっとそれほど多くはないでしょう。
この項では火災保険の保険金請求の流れを解説していきます。
保険金請求において契約者がやるべきことを、大きく4つのステップ分けてそれぞれ解説します。
1.損害発見→発見日時、現場の状況のメモ、写真
まず損害を発見したら、発見日時、現場の状況をメモしておきましょう。
さらに現場の状況や損害のあったものも写真でとっておきます。
メモの例としては、下記のようなもので問題ありません。
割れた窓ガラスと一緒に石ころも落ちていたので、強風とともに飛んできた石がぶつかったことによるものと思われる。
損害の原因については、現場を目撃したわけではない場合、主観や予測程度でも大丈夫です。
予測や主観を基礎づけることができる写真等もあるとなお良いです。
上記の例であれば、割れた窓ガラス、落ちていた石ころの写真があると、査定する側は損害との因果関係を理解しやすくなります。
2.保険会社へ損害報告
次に、保険会社へ損害の報告をします。電話連絡する際には、1.の手順で用意したメモをもとに損害状況を説明しましょう。
なお、報告の際には手元に火災保険の保険証券を用意しておきましょう。保険会社のオペレーターから証券番号を聞かれます。
ただ、仮に保険証券をなくしてしまったりで、証券番号がわからなくても問題はありません。契約者氏名や住所、生年月日等の契約情報で検索してくれます。
保険会社への報告が終わると、保険会社では保険金請求書類の郵送手配しますので、まずはその書類の到着を待ちましょう。
ちなみに保険会社への報告の代わりに代理店へ報告しても問題ありません。
3.修理業者に見積もり依頼
保険会社への報告が終わり、保険金請求書類の到着を待つ間に、損害カ所の修理の見積もりを手配しておきます。
修理見積もりは支払保険金の算出の根拠資料となりますので、先回りして用意しておくと良いです。
損害のあったものが全損となり、修理不能の場合には、購入時のレシートや領収書等、金額がわかるものが必要になります。
これらもあわせて探しておきましょう。
根拠資料が見つからない場合は、製品の取扱説明書や品番など、製品の特定に役立つような情報を探しておくようにしましょう。
4.保険金請求書類に必要事項を記載し返送する
保険会社から保険金請求書類が届いたら、必要事項を記入し、早めに返送するようにしましょう。
火災保険の請求の際に同封されているのは、主に下記の書類です。
・事故状況説明書
・返信用封筒
保険金請求書には契約者氏名や住所、保険金の振込口座等の情報を記入します。
事故状況報告書には損害発生時の状況を記入します。
その記入の際に1.の手順で作成したメモが役立ちます。メモの情報を参考にして記入しましょう。
保険金請求書と事故状況報告書、損害カ所の写真、修理に必要な見積もり(全損の場合には購入時のレシート等)を同封の返信用封筒にて保険会社へ返送します。
以上の1~4の手順をもって、契約者側でやるべきことは終わりです。
あとは査定結果の連絡を待つだけとなります。
なお大規模な損害であったり、修理の見積もりに記載の金額が数百万円を超えるような高額な請求となる場合は、損害鑑定人が現地を見に来ることもあります。
その際も契約者側で特別な対応は必要になることはありません。
日程調整し、損害発見時の状況をそのまま報告し、適切に対応するようにしましょう。
なお保険金請求については、下記の記事でも解説しています。
あわせて参考にしてください。
【参考記事:火災保険の保険金請求する時の注意点と手続きの流れを解説します。】
査定結果に納得できない場合の対策・確認ポイント
保険金請求に必要な書類を保険会社へ送付すると、数日後に保険会社から査定金額の連絡が来ます。
請求金額に対して満額回答であれば、その後の流れはスムーズにいきますが、請求金額に満たない査定結果の場合は、そうもいきません。
契約者としても納得できないこともあるでしょう。
そのような場合について、5つの確認ポイントについても触れておきたいと思います。
1.火災保険の補償内容を確認する
まずは、保険金請求するにあたってのそもそもの事故原因が、加入している火災保険で補償対象とされる事故なのかを確認します。
たとえば、水災の事故として保険金請求したものの、実際に補償内容を確認してみたら、水災は補償対象外としていたなんて場合は、いくら交渉しても結果は変わりません。
2.査定の明細を必ず確認する
査定結果の連絡を受けたら、査定金額の根拠となる明細を確認しましょう。
満額回答の場合はその必要はありませんが、請求金額に満たない結果だった場合は、必ず確認しましょう。
保険会社によっては、契約者から言わないと明細を提示せずに金額だけ提示するところもあります。
明細を細かく見てみることで交渉の糸口が見えてくる場合もあるものです。ダメもとの気持ちで取り組んでみましょう。
3.追加資料の要否を確認する
資料が足りなかったりすることで、査定金額に影響が出ることはよくあります。
たとえば修繕の見積もりには記載されているが、その損害カ所の写真が足りないので損害認定できないなんて場合もあります。
このようなケースは保険会社が査定金額を案内する際に、追加の写真を用意してください、等と説明してくれることが多いです。
面倒と思わずに追加資料を手配し、査定金額の上積みを勝ち取りましょう。
4.修理業者等、第三者の力を借りる
保険金請求書とともに提出した事故状況説明書に、損害の原因を主観であったり現場の状況からの予測で記入したとします。
このような場合で、保険会社の査定担当者が、報告資料からでは損害との因果関係に合理性が掛けるというケースもあります。
このようなときに、修理業者に事故原因の口添えをしてもらうのは非常に効果的です。
修理業者は様々な事故の修理をしてきた、いわばその道のプロでもあります。そのような業者が話す事故原因の予測は信頼性の高い情報として保険会社側も受けとります。
修理業者の見解がダイレクトに保険会社に伝われば査定はプラスに転じます。
ただし、うその見立てを言ってもらったりといった行為は、保険金詐欺とみなされる恐れがありますので、絶対にやめましょう。
5.代理店に相談する
代理店は、あくまで顧客側に立って保険会社と交渉してくれる存在です。数多くの多様な損害対応も経験してきていて、交渉のノウハウももっています。
さらには営業的な目線で考えると、代理店にとっては査定金額の上積みを勝ち取っても、保険会社の財布が痛むだけで、自らの財布は痛みません。
上積みを勝ち取ることで顧客からの信頼も得られると思えば熱も入ります。代理店も巻き込んで交渉するのは非常に効果的です。
なお、保険金請求の代行会社などもあるようですが、筆者としてはおすすめしません。
そのような外部業者を介入させることで、かえって話が大きくなったりするリスクもあります。そうなると契約者と保険会社、もしくは代理店との関係を悪化させてしまうことにもなりかねません。
さらには外部業者を利用すると、業者によっては成功報酬の何%等、手数料もかかることになります。
まずは今回あげた5つのポイントを参考に、取り組んでみましょう。
第三者相談窓口について
損害対応にあたって、様々な手を尽くしても査定金額や保険会社の対応に疑問を持ってしまった場合は、日本損害保険協会のお客様対応窓口であるそんぽADRセンターを相談窓口として利用する手もあります。
ここではお客様と損害保険会社のトラブルの解決支援(和解案の提示等)を行っています。基本的に紛争解決にかかる費用は無料です。
このような第三者的な立場をたてて解決を図るのもひとつの手です。
ここまで紹介した様々な施策を講じても、最終的に査定結果は覆らなかったなんてこともあるでしょう。
このような場合でも、その場の勢いで解約、他社への切り替えをしてしまうのはおすすめしません。
現在、火災保険の保険料は値上げ傾向にあり、契約できる期間についても、以前のように35年といった超長期契約はできません。
保険期間の中途で解約することでデメリットを被る可能性は非常に高いです。
他社へ切り替えるとしても、せめて現契約の満期までは待った上で、契約更改のタイミングで切り替えるようにしましょう。
Q&A:火災保険の損害対応に関してよく問い合わせを受けた質問と回答を紹介。
最後に、火災保険の損害対応に関してよく問い合わせを受けたことを紹介し、回答したいと思います。
質疑応答を通じて、火災保険における保険金請求のヒントにしていただけたらと思います。
質問:保険金請求するにあたり、現場は損害時の状況のまま保存しておかなきゃダメ?
初めまして、質問させていただきます。火災保険には以前に住宅ローンの期間と合わせて超長期の35年契約を組みました。
幸いにも今のところは火災保険の保険金請求するような損害に遭ったことはありませんが、台風等の損害が毎年のようにメディアで出ていると、不安になります。
そこで気になったのですが、台風の損害を受けて保険金請求をする際、場合によっては鑑定人が現地に確認にくることがあると聞きました。
その場合、損害の現場は事故時の状況のまま保存しておかなきゃダメなのでしょうか?現場をそのままにするとなると生活に影響が出るかなと思い、確認したいです。
回答|証拠写真を撮っておけば、現場をかたづけても問題ありません。
質問者様がおっしゃる通り、台風による大規模損害は毎年のように起こっています。
事故時の調査に鑑定人が現場へ出向くことも多く、鑑定人の数が足りずに、保険会社の営業担当者までも応援に駆り出されることもあるくらいです。
台風を初めとした自然災害の急激な増加が、火災保険料率の改定(値上げ)や、設定できる保険期間の短期化の大きな要因ともなりました。
ご質問の回答に移りますが、結論として、損害の現場はそのままにしておかなくても査定には影響ありません。
事故時の状況や因果関係がわかるように写真を撮っておけば問題ないです。
生活にも影響が出てしまったり、場合によっては損害の拡大にもつながってしまうので、証拠写真の手配が完了したら、すみやかに損害カ所を片付けるなど、応急処置にあたりましょう。
質問:ネット系損保は損害時の対応は良くない?
ネット系の火災保険に加入しています。なんとなくのイメージですが、ネット系は保険料が安い分、ネットでない保険会社と比較して、損害時の対応がよくないイメージがあります。
実際はどうなのでしょうか?損害時の対応がよくないのであれば、高い保険料払ってでも対応の良い保険会社に変えることも検討しています。
回答|ネット系も実店舗型も、保険会社の対応は変わらないが、実店舗型ならではの付加価値はあります。
質問者様おっしゃる通り、たしかにネット損保は実店舗型の損保と比較して保険料が安いので、多くの人がネット系を利用しているという事実はあります。
そもそもネット系損保の保険料が安いのは、店舗運営費や人件費といった、実店舗型ではかかるコストを抑えることができるためです。
ただし保険加入時には実店舗型であれば、営業担当者からプロの視点で補償設計のアドバイスをもらうことができますが、ネット系損保では基本的に契約者自身で補償の設計しなければならないというデメリットがあります。
ただ、損害時の対応に関して言えば、ネット系損保だから対応が良い、悪いということは基本的にはありません。
保険金の支払い対象となる損害が発生し、見積もりや根拠資料の提出があれば、しっかり保険金は支払われます。
強いて言えば、ネット系損保の場合は、保険金請求にあたって契約者自身が保険会社と直接やりとりしなければならず、何か難しいことを言われた場合の対応の面で不安は出てきます。
その点、代理店を通じての保険加入であれば、何かあった場合には代理店は損害対応の面でもプロの目線でアドバイスをしてくれる、心強い存在になります。
結論として、ネット系損保であっても実店舗型の損保であっても、保険会社自体の損害対応に差はありませんが、代理店のアドバイス面を考慮すると、実店舗型の方が安心感はあるのではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。
質問:火災保険はそもそも必要ですか?
質問させてください。火災保険に長期加入していて、これまでに何度も保険金請求しましたが、ことごとくゼロ回答でした。
ここまでくると、正直火災保険の必要性に疑問を感じています。
保険金請求の際にもう少し丁寧な言葉遣いをするなど工夫が足りなかったりと、保険金請求におけるマナーが悪かったのでしょうか?
そもそも火災保険は必要なのでしょうか?
回答|火災保険は多くの人にとって必要不可欠なものです。
保険会社側では、損害報告を受けて査定金額を出すにあたって、第一報で受け付けた口頭での説明や、事故状況報告書に記載された損害時の状況と提示された損害見積もり、添付された資料で総合的に判断し、合理性があるかで判断します。
事故状況の説明の仕方が悪いから損害認定が得られないということは、基本的にありません。保険金請求するにあたって、現在契約している保険の補償内容を、いま一度確認する必要があると思われます。
たとえば、台風によるものと思われる損害を受けたが、火災保険の補償内容に風災リスクは担保されているか、といったように確認してみましょう。免責金額についても確認しましょう。
免責金額が設定されていると、免責金額に満たない損害額は支払い対象となりません。
それから火災保険のパンフレットには必ず保険金をお支払いしない主な場合という項目が必ずあります。
その項目を確認し、これまでゼロ回答だった損害について、保険金をお支払いしない主な場合に該当しないかも確認しておきましょう。
わかりにくい点については保険会社や代理店の営業担当者に聞いてしまうのもひとつの手です。
誤解のないよう、補償内容はしっかり理解しておきましょう。
火災保険は火災や台風、水害といった自然災害によって大切な住まいに損害が生じた場合に必要な経済的補償をもたらしてくれる、社会的に意義のあるものです。
住まいと無関係に生活をするという人はおらず、多くの人にとって必要不可欠なものであると言えます。
補償内容の理解を深めることでその必要性も実感できると思います。
おすすめ記事
-
 パーソナルトレーナーやジムに必要な損害保険とは? ケガや事故の補償をプロが解説2025.10.09
パーソナルトレーナーやジムに必要な損害保険とは? ケガや事故の補償をプロが解説2025.10.09 -
 個人事業主に必要な損害保険は?どんな損害?選び方?保険料は経費にできますか?プロが分かりやすく解説いたします。2024.07.23
個人事業主に必要な損害保険は?どんな損害?選び方?保険料は経費にできますか?プロが分かりやすく解説いたします。2024.07.23 -
 ランクル60・70の自動車保険は高い?入れない?車両保険金額は?おすすめで安く加入できる方法を解説します。2024.03.08
ランクル60・70の自動車保険は高い?入れない?車両保険金額は?おすすめで安く加入できる方法を解説します。2024.03.08 -
 傷害保険事故事例10件!医療保険との違い?スポーツや仕事中のケガ・海外の事故にも対応しますか?を解説2024.12.16
傷害保険事故事例10件!医療保険との違い?スポーツや仕事中のケガ・海外の事故にも対応しますか?を解説2024.12.16 -
 自動車保険の代車特約は必要か?修理費用補償特約とは?入る?入らない?特約の特徴を専門家が回答!2024.02.17
自動車保険の代車特約は必要か?修理費用補償特約とは?入る?入らない?特約の特徴を専門家が回答!2024.02.17


共済の違い.jpg)