スポーツ保険いくらもらえる?習い事でのレッスン中にケガや移動中の怪我など補償される1日保険ってありますか?専門家が回答!

 大人の習い事や子供の習い事で怪我をした時の医療費や治療費はどのようになるか心配になる方も多いかと思います。
大人の習い事や子供の習い事で怪我をした時の医療費や治療費はどのようになるか心配になる方も多いかと思います。
今回の記事では、スポーツ保険に加入していることで、習い事でのケガや行き帰りの移動中の怪我など補償されるのかについて損害保険のプロが質問の回答をしていきます。
目次
スポーツ保険とは?~「もしも」の備えとしての保険制度~
スポーツ保険とは、スポーツ活動中およびその前後、たとえば自宅から練習場までの往復中や休憩時間などに発生した事故やケガ、あるいは他人に損害を与えてしまった場合に、その損害を補償してくれる保険制度です。
日常生活における傷害保険とは異なり、スポーツ特有のアクティブな動作や集団での競技、屋外でのリスクを前提として設計されているため、よりスポーツ活動に特化した補償が受けられるという点が大きな特徴になります。
以下、スポーツ保険の特徴を解説していきます。
公的・民間の両方から提供される
一般的に「スポーツ保険」と言った場合、多くの人が思い浮かべるのが公益財団法人スポーツ安全協会が提供する「スポーツ安全保険」です。
この保険は、文部科学省の後援を受けており、全国のスポーツ団体や学校、自治体のクラブ活動、地域の子ども会などで幅広く採用されているものです。
一方、近年では民間の損害保険会社でも多様なニーズに応じたスポーツ保険商品が販売されています。
たとえば、登山やマラソン、スキー、フットサルなど特定の競技に特化したものや、1日単位で加入できる短期保険など、柔軟な補償設計のされたプランが開発されており、個人のライフスタイルや競技レベルに合わせて選択することが可能となっています。
対象は「アマチュア」が基本
多くのスポーツ保険では、アマチュアスポーツの参加者を対象としており、プロアスリートや、報酬を得ることを目的とした活動は対象外となるケースがほとんどです。
たとえば、学校の部活動や地域の野球クラブ、趣味のテニスサークル、自治体の主催するウォーキング大会などでの活動が主な補償対象です。
近年では、障がい者スポーツや高齢者の健康体操などもカバーされるようになり、対象範囲は年々拡大を見せています。
スポーツ活動に特有のリスクを想定
スポーツ保険の補償設計において、以下のようなスポーツ特有のリスクが想定されています。
・プレイヤー同士の接触による骨折・打撲・ねんざなどの傷害
・運動中の心臓発作や熱中症など急性の健康障害
・活動場所への移動中の交通事故
・ボールや用具の飛来による他者への傷害
・器物破損など第三者への賠償責任
上記にようなケースは、どんなに経験豊富な選手であっても、あるいは安全に配慮していても完全に防ぐことはできません。
保険による備えがあることで、いざというときに落ち着いた対応ができ、精神的・経済的な負担を軽減することができます。
活動の安全性と信頼を支えるインフラ
スポーツ保険は、事故に伴って発生する、単なる「経済的損失の補償」の仕組みにとどまらず、スポーツ活動そのものを支える基盤でもあります。
たとえば、保護者が子どもを地域のサッカーチームに預ける際、「万が一ケガをしても保険で対応できる」と分かっていれば、安心してチームの活動に参加させることができます。
また、指導者や運営スタッフにとっても、万が一事故が起きたときに、その責任を一部保険でカバーできるという点で、活動を継続しやすくなるという利点があります。
こうした背景から、現在ではほとんどの学校や地域クラブ、NPO団体において、スポーツ保険への加入が、事実上の必須条件となっているといえます。
保険の種類も多様化
以前は「スポーツ安全保険」のような団体加入型が中心でしたが、最近では以下のような保険タイプも増えてきています。
・1日だけ加入できるスポーツ保険:レンタルサイクルやトライアスロンイベント参加時に活用。
・個人で加入するスポーツ保険:社会人のフットサル、スキー、ヨガ教室など。
・高リスク競技向け保険:登山、スノーボード、空手など事故率が高い競技を対象。
・障がい者スポーツ専用の保険:特別な配慮や補償が含まれた設計。
このように、多様な活動に応じて加入しやすい形態が整えられているため、現代におけるスポーツ保険は「自分に合った補償を選べる」時代になっています。
ここまでスポーツ保険の特徴をあげたように、スポーツ保険は「もしものための備え」でありながら、参加者の安全意識と活動の信頼性を高める重要な制度です。
アマチュアスポーツを支えるインフラの一部として、今後ますますその必要性と重要性は高まっていくでしょう。
なぜスポーツ保険が必要なのか? ~安全と責任の時代における「新しい常識」~
スポーツは、身体の健康を促進し、心を豊かにし、人とのつながりを深めるかけがえのない活動です。
しかしその一方で、スポーツには常にリスクがつきまといます。どれほど注意深く、安全に配慮していたとしても、思わぬケガや事故が起こることは避けられません。
このような状況を前提とするとき、スポーツ保険への加入は「もしもの備え」というだけではなく、現代におけるスポーツ活動の基本的なマナーや責任の一部とも言えるのです。
ここでは、スポーツ保険が必要とされる理由を5つの観点から詳しく解説します。
その1:突発的なケガに備えるため
スポーツは本質的に身体を激しく動かす活動であり、転倒・衝突・急停止・ジャンプ・投球・スライディングといった、身体への負荷が高い動作が日常的に行われます。
そのため、他の生活場面と比べてケガのリスクは格段に高くなります。実際、子どもたちが参加するスポーツクラブや学校の部活動では、ねんざや打撲、骨折、脱臼といった傷害が年間を通じて多発しています。
また、高齢者の健康体操やウォーキング中にも、転倒による骨折や打撲といった事故が報告されています。
こうしたケガにより、医療機関への通院、治療、リハビリが必要になる場合、思いがけない出費が発生します。
このようなとき、スポーツ保険に加入していれば、入院・通院に対する見舞金や傷害補償を受け取ることができ、経済的な負担を大きく軽減することができます。
その2:加害者になってしまうリスクへの備え
スポーツ活動中は、自分のケガだけでなく、他人に損害を与えてしまうリスクも常に存在します。たとえば以下のようなケースを想像してみてください。
・野球の打球が観客席に飛び、観客にケガをさせた。
・サッカー中にタックルして相手選手を骨折させた。
・テニスボールが隣のコートに飛び、相手の目に当たって失明しかけた。
・ゴルフボールが民家の窓ガラスを割った。
こうした事故が発生した場合、競技者に損害賠償責任が発生する可能性があります。
しかも、相手が後遺障害を負ってしまう等、その被害が大きければ、数百万円から数千万円、下手したら1億円超えといった高額な賠償請求につながることも珍しくありません。
スポーツ保険には、その保険設計の中に「賠償責任保険」が組み込まれております。
これにより加害者としての賠償費用をカバーできます。結果として、当事者同士のトラブルや訴訟に発展するリスクも抑えることができるのです。
その3:活動の主催者としての責任
スポーツイベントやクラブ活動を主催する立場にある人にとって、万が一の事故に備えておくことは責任ある行動です。
学校の先生や地域スポーツクラブの代表者、NPOのスタッフ、ボランティア指導者などは、参加者の安全を預かる立場にあり、事故が起きた場合には責任を問われることがあります。
スポーツ保険に加入していれば、団体としての補償体制が整っていることを対外的に示すことができ、参加者や保護者に対する信頼性が高まります。
また、事前に保険加入を条件としておくことで、活動中に発生するトラブルへの備えが明確になります。
その4:「安心して参加できる環境」をつくるため
参加者にとって、スポーツ保険は「安心の証」です。
特に子どもや高齢者、障がいのある人が関わる活動では、「安心して運動できる環境」を整えることが最優先事項です。
保険に加入していれば、参加者やその家族は、万が一のときの経済的な負担が軽減されることで、精神的な不安を抱えることなく活動に集中することができます。
また、昨今では保護者の目も厳しくなっており、「安全対策が不十分な団体には子どもを預けたくない」という声も多くなっています。
スポーツ保険への加入は、活動の信頼性と継続性を支える「見えない基盤」でもあるのです。
その5:高額化する医療費・法的リスクへの現実的対策
現代の医療制度では、公的医療保険があるとはいえ、高額な医療費や治療に時間がかかるケースも少なくありません。
また、万が一の後遺障害や死亡事故が発生した場合には、その補償額は数百万円から数千万円に及ぶこともあります。
さらに、加害者となった場合、法的責任や訴訟リスクに直面する可能性もあります。
こうした金銭的・法的なリスクに対して、スポーツ保険が果たす役割は非常に大きいものです。
単なる見舞金制度を超えて、リスクマネジメントの一環として捉えるべき段階に来ています。
スポーツ保険の補償内容とは?──カバーされるリスクとその具体的な内容
スポーツ保険は、スポーツ活動中に起こりうる多様なリスクに対して幅広く補償を提供する制度です。
保険会社や保険の種類によって細かな差異はあるものの、一般的に共通して含まれる補償内容には次の4つの柱があります。
補償①:傷害補償(ケガに対する補償)
最も基本的な補償項目が「傷害補償」です。
これは、保険の対象者がスポーツ活動中やその前後にケガをした場合の治療費や見舞金、入院・通院に対する保険金などを支給するものです。
【補償される主なケース】
・サッカーの試合中に転倒して骨折した
・野球の練習中にボールが当たり、打撲した
・マラソン大会中に足首をひねってねんざした
・テニス中に肉離れを起こした
・スキー場で転倒し、頭を打って入院した
【保険金支払いの例(※契約内容による)】
・通院1日あたり 1,500円〜5,000円
・入院1日あたり 3,000円〜10,000円
・骨折・脱臼・手術などに対する一時金
・後遺障害が残った場合の等級に応じた保険金
・死亡時の保険金(例:300万円〜1,000万円など)
※保険によっては通院日数の制限や自己負担分の条件があるため、事前に商品を提供する損害保険会社等に確認しておくことが大切です。
補償②:賠償責任補償(加害事故に対する補償)
スポーツ中に他人にケガを負わせたり、物を壊してしまったりした場合の賠償責任をカバーするのがこの補償です。
これは自分自身のケガではなく、第三者への損害賠償責任に対する保険であり、特に競技性のあるスポーツや屋外活動では重要な補償です。
【補償される主なケース】
・フットサル中に相手選手に激しくタックルし、骨折させた
・ゴルフボールが誤って他人に直撃し、ケガをさせた
・野球の打球で観客にけがを負わせた
・サイクリング中に通行人にぶつかり、打撲を負わせた
・練習場の器具を壊してしまった
【補償額の例(※上限あり)】
・対人賠償:1億円まで
・対物賠償:1,000万円まで
※法律相談費用や示談交渉費用も補償対象となることがある。
この補償は、個人だけでなく団体(クラブや学校)としての責任にも適用される場合があります。
近年では、訴訟リスクに備えてこの補償を重視する動きが高まっています。
補償③:死亡・後遺障害補償(重大事故への備え)
万が一、スポーツ活動中の事故により死亡したり、重度の後遺障害が残ったりした場合に支払われるのがこの補償です。
滅多に起こることではありませんが、心臓発作・落下・重大衝突などで死亡や障害が発生することはゼロではありません。
【補償される主なケース】
・マラソン中の心筋梗塞で急死
・登山中の転落事故による死亡
・スノーボードで頭部を強打し、半身麻痺の後遺症が残った
・自転車での転倒で脊髄損傷となった
【補償金の例】
・死亡保険金:300万円〜1,000万円
・後遺障害保険金:障害の等級に応じて支給(例:全身麻痺で1,000万円)
※一部の保険では、死亡補償が別契約になっていることもある。
スポーツイベントの主催者は、こうした重大事故に備えて、高額な死亡補償を備えた団体保険を導入することが一般化しています。
補償④:救援者費用・緊急搬送費用(特に登山や遠征向け)
一部の保険には、事故や病気により救助・捜索が必要になった場合の費用を補償する特約が付帯されています。
登山・スキー・マリンスポーツ・サイクリングなど、遠隔地での活動には重要な補償です。
【補償される主なケース】
・登山中に遭難し、捜索ヘリが出動した
・スキー場で動けなくなり、雪上車で搬送された
・マリンスポーツ中に溺れて海上保安庁が救助した
・遠征中に急病で現地の病院に緊急搬送された
【補償の例】
・救援者費用:最大100万円〜500万円
・緊急搬送費用(ヘリコプター、民間救急):数十万円〜数百万円を補償
・遠征中の家族の現地派遣費用
これらは「アウトドア特約」や「遠征対応プラン」などとしてオプション契約されることが多く、特に大学のサークル活動や社会人の趣味活動においてニーズがあります。
補償その他:その他の補償内容(保険商品によって異なる)
スポーツ保険は日々進化を続けており、以下のような補償が組み込まれることもあります。
・大会中止保険(天候や災害でイベントが中止になった場合の費用をカバー)
・持ち物損害保険(スポーツ用品の破損・盗難を補償)
・弁護士費用特約(トラブル発生時の法的サポート)
・感染症対応特約(新型コロナウイルスなどによる影響をカバー)
また、特定の競技や年齢層に特化したプランも増えており、障がい者スポーツ専用保険、高齢者向け軽運動対応保険、幼児用スポーツ保険など、さまざまなニーズに対応した設計が進んでいます。
ここまでスポーツ保険の基本補償について解説してきましたが、スポーツ保険は、その名の通りスポーツを行うすべての人の安心を支える存在であることがわかるかと思います。
その補償内容は提供する保険会社や保険商品ごとに異なるものです。
ただ加入しているだけで安心するのではなく、「どんなときに、いくら、どういう条件で補償されるのか」を理解することが、いざという時に最も大切になります。
とくにスポーツクラブや学校活動の主催者は、責任を果たす一環として、補償内容を把握し、適切な保険を選ぶ姿勢が求められます。
安全な活動の裏には、しっかりとした備えがあるということを再確認するきっかけとして、スポーツ保険の補償内容を知ることは、極めて重要なのです。
スポーツ保険の加入方法とは?
スポーツ保険は、だれでも比較的簡単に加入できる保険ですが、加入の形態(個人か団体か)、申込方法、保険料の支払方法、補償開始日などによって注意点が異なります。
ここでは、主に「個人での加入」と「団体での加入」の2つのケースに分けて、加入の流れや注意点をご紹介します。
個人で加入する場合
個人でスポーツ保険に加入する場合、自分が参加するスポーツ活動に合わせて自由にプランを選び、インターネットや代理店を通じて申込みを行います。
【加入の主なステップ】保険会社・プランの選定
大手損害保険会社や、スポーツ専門の保険会社が提供する商品から、自分の年齢や活動内容に合ったプランを選びます。プラン選びについては、下記のような観点から考えるようにします。
・ケガ中心の補償が欲しいのか
・賠償責任もカバーしたいのか
・年間契約か短期か
Web申し込みまたは保険代理店に連絡
最近はほとんどの保険がオンラインで申し込み可能です。
保険会社の公式サイトにアクセスし、必要情報(名前、住所、年齢、活動内容など)を入力します。
保険料の支払い
クレジットカードやコンビニ払い、銀行振込などで支払いを行います。
保険料は年間1,000円〜3,000円程度のリーズナブルな価格帯が多く、費用対効果に優れています。
加入完了・補償開始
多くの場合、申込日の翌日や翌々日から補償が開始されます。ただし、即日補償ではない場合が多いので、参加予定日より前に余裕をもって申し込むことが大切です。
※注意点!
・保険期間(例:4月1日~翌年3月31日など)を確認
・一部のスポーツ(格闘技やモータースポーツなど)は補償対象外
・年齢や職業によって制限があるプランもある
団体で加入する場合
クラブ、学校、自治体、スポーツイベントの主催者などが、複数人まとめて加入する団体保険は、スポーツ保険の中心的な利用形態です。
日本スポーツ協会(JSPO)の「スポーツ安全保険」などが代表的な例です。
【加入の主なステップ】団体代表者が窓口となって手続き開始
加入を希望する団体の代表者(クラブのコーチ、学校の教員、NPOの事務局など)が、スポーツ保険の窓口(損保代理店や地域スポーツ協会など)に申込みを行います。
加入者名簿の作成と提出
団体に所属するすべての加入者の情報(氏名・性別・生年月日・区分など)をまとめた名簿を作成し、保険会社または窓口団体に提出します。
保険料の一括支払い
人数分の保険料をまとめて振り込みます。
保険料例:大人1人年間1,850円、子ども1人800円など(スポーツ安全保険の場合)
このように、団体にとっては非常にコストパフォーマンスが高い仕組みです。
補償開始
申込完了後、補償は通常、名簿の提出と入金が完了した翌日または翌々日から適用されます。
特に大会や遠征前は、余裕を持って手続きする必要があります。
【団体加入のメリット】
・参加者全員に一律の保険が適用され、管理がしやすい
・安価で広い補償が受けられる(大人でも年間2,000円前後)
・万一の事故時、団体責任を軽減できる
・イベント会場や施設が「保険加入者であること」を利用条件としている場合がある
スポーツ保険加入にあたってのチェックリスト
スポーツ保険加入時には以下の点を確認しておくと安心です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 補償開始日・期間 | 申込後すぐではないことが多いため、活動日と照らして確認する。 |
| 保険対象となる範囲 | 通勤・通学中は対象か、活動場所に制限があるかなど |
| 補償内容の詳細 | 傷害、賠償、死亡、後遺障害、物損などの有無と上限額 |
| 対象となる活動 | 危険性の高い競技や海外活動などが除外されていないか |
| 加入方法と支払い 方法 | オンラインか窓口か、支払い方法と領収書発行の有無など |
| 保険証や加入証明の 有無 | 大会参加時などで「証明書」が必要な場合は発行できるか |
加入を検討するにあたり、上記のチェックリストをぜひ参考にしてください。スポーツ保険の加入は、決して難しいものではありません。
しかし「いつ」、「どこで」、「どのように加入するか」によって補償内容が大きく変わることもあるため、事前の情報収集と計画的な申込みが大切です。
特に団体活動の場合は、「自分たちには事故が起きない」という思い込みは捨て去って、「誰にでも起こりうる事故への責任ある対応」という意識を持つことが重要です。
加入は義務ではなくても、それがあることで参加者全員が安心して活動できるのです。
実際の活用事例
スポーツは本来、健康や楽しさをもたらす活動ですが、アクティブであるがゆえに予期せぬ事故やケガが起こる可能性も常に存在します。
そんな時、スポーツ保険が実際にどのように役立ったのか、活用された実例を以下にまとめました。
事例①:【少年野球クラブ】練習中の骨折事故と通院補償
【状況】
小学5年生の男児が少年野球クラブの練習中に、ノックされたゴロを捕球しようとして転倒し、左手首を骨折。救急搬送されて整形外科で診察、全治6週間と診断され、通院とギプス固定が必要となった。
【活用された補償】
通院日数:12日間に対し、傷害補償として、通院1日あたり2,000円の保険金が支払われた(合計24,000円)。さらに、骨折による一時金として30,000円が支給された。
【ポイント】
クラブ全体で「スポーツ安全保険」に加入していたことで、治療費の一部を保険金でカバーでき、保護者の経済的負担が軽減された。
事例②:【フットサル大会】相手選手への接触事故による賠償責任
【状況】
アマチュアフットサル大会中、男性プレーヤーが無理なスライディングで相手選手の足に接触し、靱帯損傷(全治2か月)のケガを負わせてしまった。被害者は通院治療を余儀なくされ、勤務先にも欠勤することになった。
【活用された補償】
スポーツ保険の「個人賠償責任補償」を通じ、治療費(実費)と慰謝料を合わせて約50万円を保険会社が被害者に支払った。
加害者本人に自己負担は発生せず、示談交渉も保険会社が代理で対応し事案は収束。
【ポイント】
本人は賠償責任保険が付帯された個人向けスポーツ保険に加入していた。予期せぬ加害者となった場面でも保険が「守り」として機能した事例となった。
事例③:【中学校の部活動】遠征先での交通事故と入院補償
【状況】
中学校のバスケットボール部が県外遠征中、高速道路で軽微な交通事故に巻き込まれた。複数の生徒がむち打ち症や打撲で病院に搬送され、うち1名が入院(4日間)する事態に。
【活用された補償】
・スポーツ保険の「遠征・移動中も補償対象」という契約に基づき、入院1日5,000円×4日=20,000円が支給された。
・通院補償も、ほかの生徒に対して1日あたり2,000円で支払われた。
・学校が団体契約していたため、迅速に保険会社と連携が取れた。
【ポイント】
事故は競技中ではなく「移動中」だったが、包括的に補償する団体契約だったため、適用対象となった。安全管理を重視する学校活動では、こうしたケースは非常に重要となる。
事例④:【登山グループ】遭難・救助ヘリの出動費用を補償
【状況】
中高年の登山グループが山梨県の登山道で道に迷い遭難。天候が悪化したため自力下山が不可能となり、県の山岳救助隊と民間ヘリが出動。メンバー3人が無事救助されたが、救助費用は計120万円にもなった。
【活用された補償】
加入していた山岳活動向けのスポーツ保険で、「救援者費用補償(上限300万円)」が付帯されていたため、それを活用した。
実際に発生した民間ヘリの出動費・搬送費・宿泊キャンセル費用などをすべてカバーすることができた。
【ポイント】
一般的な保険では救助費用は補償されないが、登山専用のスポーツ保険を選択していたことが功を奏した。登山やマリンスポーツなどの「遭難リスク」がある活動では非常に重要な補償項目。
事例⑤:【小学生サッカー大会】熱中症による入院と特別見舞金
【状況】
真夏の大会中、小学4年生の選手が熱中症で倒れ、救急搬送。2日間の入院を余儀なくされた。命に別状はなかったが、体調の回復までにしばらく登校・通学を休むこととなった。
【活用された補償】
・傷害補償で、入院2日×5,000円=10,000円
・熱中症に関する特別見舞金制度(契約により)でさらに10,000円支給
※一部の保険では、熱中症対応特約が標準装備されている。
【ポイント】
最近のスポーツ保険では、「熱中症特約」を設ける商品が増えている。気候リスクに対応した最新型の保険が、子どもの安全を経済的にも支えている例。
加入時の注意点
以下、スポーツ保険加入時の注意点をまとめました。前出のチェックリストとあわせておさえておきましょう。
・補償期間を確認(通常は4月1日~翌年3月31日)
・ケガの発生日や通院日数には制限がある
・保険金給付を受けるには診断書や領収書の提出が必要
・他の保険と重複する場合もあるので内容を整理しておく
Q&A:スポーツ保険に関する質問と回答
最期に、スポーツ保険に関する質問をいくつか紹介したいと思います。どの質問も筆者がお客様より実際に聞かれた内容をもとにしております。ぜひ参考にしてください。
質問:レッスン中の怪我だけでなく行き帰りの怪我も補償されますか?
クラシックバレエを大人になってから習っています。お恥ずかしながら先日爪先で立つトゥシューズのクラスを受講中に、右足首を軽く捻ってしまいました。
すぐに冷やしましたがかなり腫れているため先生からも通院を勧められました。
帰り道に右足を庇って歩いていたところ、転倒してしまい左半身を打ってしまいました。この場合、レッスン中と帰り道の怪我どちらも補償されますか。
回答:スポーツ活動中に第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任の補償をカバーするものです。
一般的にスポーツ保険とは、スポーツ活動中に発生するケガに対する補償や、スポーツ活動中に第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任の補償をカバーするものです。
これらの補償はスポーツ活動中だけでなく、活動のための往復中であってもカバーされます。
ご質問の例のクラシックバレエ受講中のケガも、帰り道のケガも、ともにスポーツ保険の対象となります。
ただし、スポーツ保険の補償内容は入院一日につき5,000円、通院1日につき3,000円といったように定額払いの設計となっていることが大半です。
クラシックバレエ受講中の右足のケガ、帰り道の左半身のケガと、それぞれケガの部位は異なりますが、2か所のケガの治療を1日の通院時に診てもらうような場合は、支払保険金は1日分であることに注意が必要です。
質問:習い事のスポーツ保険は、学校のスポーツの怪我の際にも使えますか?
子供が習い事のダンス教室でスポーツ保険に加入しています。小学校でもダンスの授業があるのですが、先日授業中に足首を捻ったようです。
本人は痛いと言っており成長期ということもあるため、整骨院か整形外科に通院しようかと思うのですが、習い事の方で加入しているスポーツ保険を使って治療することはできるのでしょうか。今までスポーツ保険を使ったことがないので教えてください。
回答:学校管理下で実施される活動における事故については、スポーツ安全保険では補償ができません。
スポーツ保険とはスポーツ活動中のケガや事故に備えるものです。
ただし、学校管理下で実施される活動における事故については、スポーツ安全保険では補償ができません。
あくまで加入手続きを行った団体の管理下における活動中のケガや事故のみ補償の対象となると理解しておいたほうが良いです。
ご質問のケースでは、まず学校で加入している保険の補償内容を確認することから始めましょう。
質問:合宿での事故も補償対象ですか?
周囲ではスポーツ保険に入っている友達がほとんどいないため、質問させてください。
体育系の大学に通う大学生です。怪我をするリスクが高いと思い、保険に加入しています。
今度3泊4日の夏合宿に参加することになりましたが、合宿での事故は補償対象になりますか。条件がつく場合はその条件を知りたいです。
また合宿に行くまでの間と自宅に帰るまでの間の事故も保証されるのでしょうか。
回答:スポーツ活動を目的とした合宿であれば補償の対象となります。
スポーツ活動を目的とした合宿であれば補償の対象となります。合宿所へ行くまでと合宿終了後に自宅に帰るまでとを含めて補償されます。
※日本国内の活動に限るため、海外への合宿活動は補償対象外です。
ただし、往復中で補償対象となるのは、「通常の往復経路中」であり、たとえば合宿終了後、打ち上げで仲間と食事をしたり寄り道をしたりした場合は、「通常の往復経路中」とはいえず、補償の対象外となります。
また、寄り道等から通常の往復経路に復帰した後も対象外となりますので、合宿終了後、寄り道をするような場合は、その寄り道からは補償対象外となることに注意しましょう。
質問:スポーツ保険を検討しています。事故の際の通院回数に制限はありますか?
趣味でテニスをやっているため、万が一怪我をした時のことを考えてスポーツ保険を検討し始めました。
事故の後、補償される通院回数に制限はあるのでしょうか。
年齢も50代に差し掛かっているため怪我をした場合は通院が長引きそうだと考えているため、通院期間の上限も設定されているのか気になります。
色々と種類がある中で迷っていますが、制限や上限設定がない保険を選びたいです。
回答:スポーツ保険の通院補償は、どこの保険会社の商品でも通院日数は概ね90日以内での設定
スポーツ保険の通院補償は、どこの保険会社の商品でも通院日数は概ね90日以内での設定となっているものが多く、無制限に補償するものはないようです。
設定できる保険金額も、上限は5,000円くらいになるでしょう。
また、補償の制限という点で重要なことがあります。
通院補償はケガをした日から180日以内に開始した通院に対して保険金を支払うものであり、それ以上経過して通院を開始しても補償の対象外となります。
180日以上たってから痛みが発症して通院したとしても、それはスポーツ中のケガが原因なのか判断がつかないためです。
このような取り扱いは、どこの保険会社のスポーツ保険であっても統一されているようです。
スポーツ保険の通院補償(入院補償もしかりですが)はどうしても日数に制限があるので、充実した補償をと考える場合は、保険金額を手厚くする等、工夫が必要です。
質問:スポーツ保険を検討しています。年間のものではなく1日だけの保険もありますか?
小学生の子供を持つ保護者です。子供が習い事を始めることになり、お教室からスポーツ保険を進められました。
年間の掛け金は安いものではありますが、習い事で怪我をするという発想がなかったのでイベントの日のみ日数を指定して入れれば十分だと考えています。
年間ではなく日時を指定して入れる保険もあるのでしょうか。その場合は割高になってしまったり、補償条件が悪くなったりするのでしょうか。
回答:1日だけ加入できる保険もあります。いわゆる1DAYレジャー保険
1日だけ加入できる保険もあります。いわゆる1DAYレジャー保険とよばれるものがそれです。
1名・1日あたりの保険料も500円程度であり、補償内容も死亡、入院、第三者に対する賠償責任と広くカバーされています。
加入の際もコンビニでカンタンに手続きできるので、イベントその日のみ補償が欲しいというお考えであれば良いものかと思います。
ただし、割高かどうかという点で考えると、1日だけの保険は保険料面では割高であるといえます。
習い事で勧められたスポーツ保険であれば、おそらく大会などのイベントの日だけでなく、習い事中のケガも補償される設計になっているかと思います。
補償範囲と保険料のバランスを考えて検討すると良いでしょう。


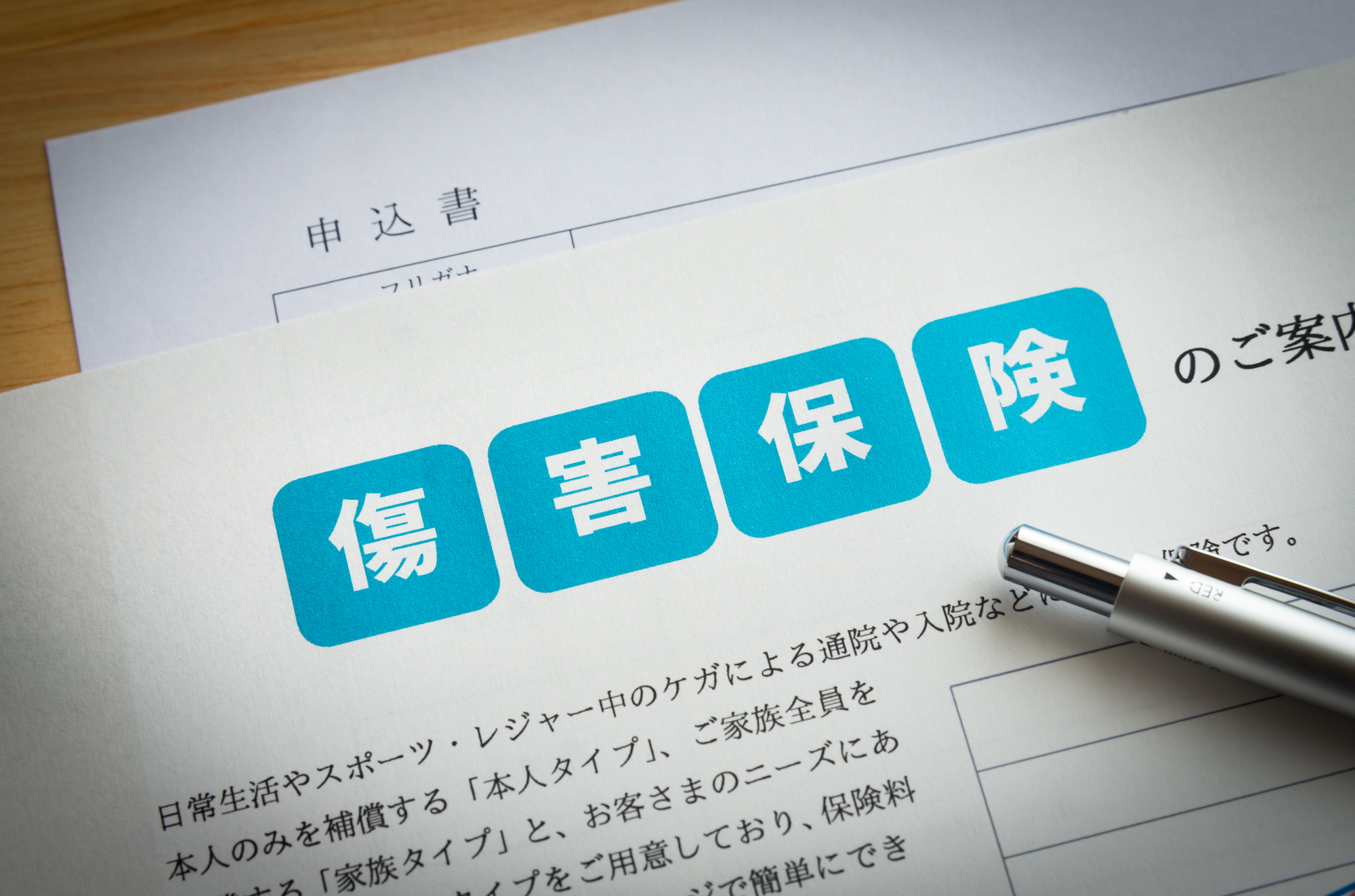



共済の違い-300x200.jpg)










