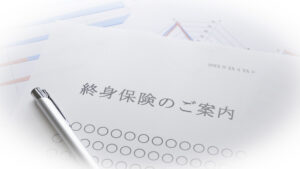がん闘病記|お金と精神的な不安で大変だった。公的保険や民間のがん保険についての実話をお話しします。

がんは2人に1人が罹患する病気と言われています。
すべての人が罹る可能性のある身近であり、かつ怖い病気でもあり、日常生活を健康に営む上では決して無視できない病気です。
近年では、医療技術の進化により様々な治療方法が発見され、確立されてきました。
昔みたいに決して治らない病気ではなくなってきたのは事実ですが、それでも日本人の死因第一位の病気であることに変わりはなく、もっとも怖い病気であると言えます。
がんの診断を受けたとき、きっとほとんどの人はその言葉に衝撃を受け、これから先の人生に対する不安や恐怖感が一気に押し寄せてくるでしょう。
がんは身体に与える影響だけでなく、心にも深い傷を残します。
がんは、罹患者本人だけでなく、罹患者の回りの家族や友人にも影響を与えうるものです。
もちろん罹患者本人が一番つらいのは大前提ですが、近くにいる家族も同じようにつらい思いをすることになります。
実は、筆者は数年前の梅雨の時期、妻をがんによって亡くしました。
がんの診断確定から約4年半の闘病生活をがんばってくれましたが、最後は力尽きてしまいました。
筆者は最も近くで妻の闘病生活を支えてきたという自負があります。
今回の記事では、妻のがん闘病の中で感じたことを紹介します。
金銭面における不安、金銭面以外で大変だったこと、公的医療保険や民間のがん保険、医療保険の大切さについて共有したいと思います。
冒頭にも言いましたが、がんは誰でも罹る可能性のある身近でかつ怖い病気です。
この記事ががんについて改めて考えるきっかけになれば幸いです。
目次
初めての診断とその影響
この項では、がん診断に至った経緯から、がんの診断確定、このことが筆者を含む家族へ与えた影響について記載します。
がんの診断確定までの経緯
まずは診断確定までの経緯を話したいと思います。
妻は定期健康診断として毎年必ず人間ドックを受診していました。
結果票を見ても、それほど目立った指摘項目はなく、比較的健康体ではありました。
しかし、結果的にがんの診断確定を受ける年までの3年間は便潜血の指摘が続いていて、要再検査の案内を受けていました。
妻も私も、当初は生理のタイミングで血が混じっているだけだろうと思っていたこともあり、再検査を面倒がって受診していませんでした。
便潜血を甘く見ていたのです。
事実、厚生労働省には、健康診断で便潜血の反応が出ても、大腸がんの確率は約3%というデータもあります。
そのようなこともあり、当時は高を括っていたのです。
しかし3年も便潜血の指摘が続くと、さすがに不安になりました。
当時の妻は、扶養の範囲内での収入に調整ながらのパート勤務、子ども2人の保育園への送り迎え、家事に育児に日々忙しく動いていました(子ども2人は別々の保育園に通っていたのです)。
面倒だけど時間を作って再検査を受診しに、近所の病院の門をたたきました。
当時の思いとしては再検査の結果、異常なしで安心しておこう、くらいの考えでした。
しかし、再検査の結果、当時の思いは無残に打ち砕かれました。
腫瘍が見つかってしまったのです。
再検査を受診した病院の先生には以下のようなことを話されました。
「再検査の結果、大腸に腫瘍が見つかったが、その腫瘍が良性のものか悪性のものかはお腹を開いてみないとわからないが、おそらく悪性のものである可能性が高い。」
「これもお腹を開いてみないと何とも言えないが、大腸の腫瘍が悪性のものである場合、下手をしたらステージ2~3(※)まで進行している可能性がある。」
「当病院では診られないので、もっと大きな病院で診てもらった方が良い。」
当時このような指摘を受けたものの、心のどこかでは、
「きっと腫瘍は良性のものだろう」
「医者は悪性の可能性が高いと言っているけど、お腹を開いたら良性ってわかるだろう」
なんて楽観的に捉えていました。
すぐに詳しい検査をすべく、その場で自宅から比較的近い場所にある大学病院の紹介状をもらうことにしました。
がんのステージ分類について
・ステージ0・・・上皮内がんとも呼ばれ、がん細胞がまだ他の組織に侵入していない段階。がんは原発部位にとどまり、転移もない段階。
・ステージ1・・・がんがまだ原発部位にとどまっており、リンパ節や遠隔部位に転移していない段階。がん自体が小さく、限られた範囲に広がっている段階。
・ステージ2・・・がんが原発部位に広がり、周囲の組織に侵入しているか、近くのリンパ節に転移している可能性がある段階。遠隔転移はまだ見られない。
・ステージ3・・・がんが原発部位を超えて、周囲のリンパ節に転移しているが、遠隔転移はまだ確認されていない段階。がんの進行が進んでいるといえる。
・ステージ4・・・がんが遠隔部位(例えば他の臓器や部位)に転移している段階。この段階では、がんは非常に進行しており、治療が難しく、完治が難しい場合が多い。症状の緩和や延命治療が行われることがある。
紹介状を受け取りすぐに大学病院に
近所の病院での診断後、大学病院への紹介状を受け取り、すぐに当該大学病院に診察の予約の連絡を入れました。
結果、診断から約一週間後に診てもらうことになりました。
その日から予約日までの日々は、何をするのにも落ち着かず、何も手につかなかったことを覚えています。
きっと妻は筆者の何倍も不安な気持ちを抱えていたでしょう。
しかし、大学病院の予約日までの日で事件が起きます。
予約日の前日の深夜2時、妻が急な腹痛に見舞われたのです。
もともと痛みには強いタイプで滅多なことでは音を上げないのですが、この時ばかりは尋常でない痛みだったのだろうと感じられました。
筆者はその場で予約予定であった大学病院に連絡を入れ、救急での受け入れを打診しました。
幸い受け入れの承諾が得られたので、そのまま車で妻を運ぶことにしました。
深夜の2時過ぎの出来事で、小学校にも上がっていないくらい小さい2人の子どもに留守番させるわけにもいかず、すぐに子どもをたたき起こして、家族総出で病院に向かうことにしました。
大学病院について担当医師に容体を話すと、すぐに手術をすることになりました。
手術をしている間に筆者は両親に連絡を入れ、事情を話しました。
両親には始発で自宅に来てもらい、筆者は子どもをいったん自宅まで送り届け、その世話をバトンタッチすることにしました。
その後、筆者は病院に戻り妻の容体を見守ることにしました。
病院に戻ると、救急の対応をしてくれた医師と話ができました。
その医師によると、子宮と卵巣への転移が確認され、子宮が尋常でないほどに肥大化してしまったことが、腹痛の原因であることを聞かされました。
子宮と卵巣を切除しないと命にも危険がおよぶことの説明を受け、筆者の判断で手術のお願いをしました。
結果、子宮と卵巣の切除の手術は無事に終わったものの、そのまま入院することになりました。
入院からほどなくして、主治医からの呼び出しを受け、病状の具体的な診断内容の説明を受けました。
原発は大腸がんで他の臓器にも転移が見られ進行もしている。
ステージ4で、余命は1年ないかもしれないと。
当初の楽観的な想いはここでも無残に打ち砕かれたのです。
がん診断確定による生活は激変
具体的な診断確定を受け、妻と筆者を取り巻く環境、生活は激変することになります。
筆者はこれまで、子育てに家事、保育園の送り迎えをすべて妻に頼ってしまっていたものを、筆者がやらざるを得なくなりました。
仕事も平日は、ほぼ23時過ぎの帰宅で場合によっては帰らない日もあったものも見直さなくてはなりません。
筆者はまず会社に事情を報告し、相談しました。
幸いにも会社は、家族優先で仕事の調整することを快く承諾してくれました。
結果。ほぼ定時に退社し子どもの保育園の迎えをしつつ、すぐに家事にとりかかるという日々がスタートします(保育園の送りについては筆者の両親に頼りました)。
これまで料理はほとんどやったことなかったので、YouTubeで調べつつ、失敗を繰り返しながらも、なんとか食べられるものを作っていきました。
平日追いつかない家事は、睡眠時間を削ったり、土日にまとめて行ったりと工夫しました。
ただ、このようなバタバタの生活においても幸いだったのは、2人の子どもは文句ひとつ言わなかったことです。
料理の味においても妻に遠く及ばなかったはずですが、子どもたちはおいしいと言って、作ったものは残さず食べてくれたのです。
子どもの成長を感じられたことに小さな幸せを感じました。
治療の選択肢と挑戦
日常生活をなんとか維持しつつも、治療の方法について調べることも始めました。
主治医の先生からは、下記のような説明を受けたことを覚えています。
・治療方法にはそれぞれにメリットとデメリットがあり、患者のがんの進行具合に応じて適切な治療方法を選択しなければならない
。・ただ妻の場合、言いにくいが原発の大腸から各臓器に広がりすぎていて、局所治療の手術ではとても除去しきれない。
・放射線をあててがん細胞にダメージを与える治療方法についても、がんが他の臓器への転移を誘発する可能性が高い。
・抗がん剤治療でがんの進行を遅らせるのが、いま取り得る最も有効な治療。年齢が若いとがんの進行は早いが、逆に言えば体力もあるので強い薬にも耐えることができる。
・強い抗がん剤治療はその分副作用が強く、苦しむこともある。苦しみの少ない緩和ケアという選択肢もあるが、緩和ケアは治療を目指すものではない。
妻には病気のこと、残された時間のことは話していたので、上記の治療についてもすべて話しました。
それに対して妻はこう言ったのです。
「少しでも長く生き子どもたちの成長を見守りたいから、抗がん剤治療選ぶ」
「少しでも治る可能性のある治療に懸けたい。」
「可能性はあるなら、どんなに苦しい副作用も我慢する」
と。
抗がん剤治療の開始と並行して、筆者はセカンドオピニオンやがんの権威の先生が開催しているセミナー等、情報収集を開始しました。
主治医の先生もセカンドオピニオンを積極的に勧めてくれたことも、筆者の動きを後押ししてくれました。

抗がん剤による治療の効果、副作用に苦しむ日々から生活の安定期まで
抗がん剤治療は治療面ではすごい効果を発揮してくれました。
がんの進行を止める効果が確認できたと、主治医も太鼓判を押したほどです。
しかし、抗がん剤の副作用は想像を絶するものでした。
まず食欲が落ち、体重が一気に減りました。
吐き気や日常的な倦怠感が常に付きまとい、手や足先の寒気を常に訴え、暑い日でも手袋や靴下2枚履きという状態でした。
さらには長かった髪も抜け落ち、外に出ることも減ってしまいました。
傍から見ていても、この治療を隔週で受けなければならないのか、こんな苦しい思いをしなければならないのかと、治療開始当初は絶望的な思いをしたものです。
しかし治療を開始してからしばらく経つ頃には、生活のリズムを作ることができました。
抗がん剤を投与した後2~3日は動けない日が続きますが、それが過ぎるころには動けるようになり、家事に食事に子育てに取り組んでくれました。
ウイッグをいくつか買って、体が動けるようになってからは、なるべく積極的に外にも出るようにしてくれました。
もともとお酒が好きだったので、飲酒もできるくらいにも元気になったのです。
妻の精神的な強さを感じたことを覚えています。
抗がん剤治療には高額な費用が不安に
言うまでもないことですが、抗がん剤治療には高額な費用負担が発生します。
隔週で通院し、その都度抗がん剤治療を受けるというサイクルで生活していたのですが、ざっくり通院の度に約60,000円の窓口負担が発生していました。
抗がん剤治療にかかる費用相場には注意が必要
さらに、病状の悪化や新しい抗がん剤を試すというタイミングで入院することもあると、通常の通院費用に加えて入院費用も乗っかってきます。
いまはネットで検索すれば、抗がん剤治療にかかる費用相場のような情報は溢れていますが、この情報には注意点があります。
それは、抗がん剤治療に使用する薬の種類や治療頻度によって費用は異なるという点です。
さらには患者の置かれた生活環境によって、治療費用以外にも付随的に必要となる費用も異なってきます。
このような点は、実際に治療生活を傍で支えた身として強く実感したところです。
費用に関する情報は、参考にはしつつも鵜呑みにはしないことを強くおすすめします。
幸い当時の筆者は、職場の健康保険組合に加入していて、そこから独自の給付(付加給付)も受けることができ、少しは費用負担の足しになりました。
高額療養費の支給申請と合わせて、医療費をなんとか工面することができました。
さらには、妻は医療保険とがん保険にも比較的手厚い保障内容で加入していました。
このように、社会保険からの給付や民間の保険の保障によって、医療費その他の付随費用を捻出していましたが、それでも実際には持ち出しは発生していました。
ただ、もし民間の保険に入ってなかったら得られなかった給付を考えるとぞっとします。
このときほど民間の保険会社の保険の大切さを感じたことはありません。
心の葛藤と孤独感
治療のサイクルが安定することで、体調の変化とそれにともなう生活のリズムが安定してきましたが、時折死に対する恐怖から、メンタルが不安定になることもありました。
妻はもともとの特性として優しくおとなしいタイプだったのですが、不安定な精神状態のときには子どもにも強く当たってしまうこともありました。
そのようなとき、本来ならば筆者が一番しっかりしなければならない立場にありながら、やさしさを忘れ、妻に対してもきついことを言ってしまったこともありました。
いま考えても反省すべき点です。
がん闘病生活は、肉体的な苦しみだけでなく、心の葛藤や孤独感も伴います。
治療の疲れや不安、未来に対する不安感が心を圧迫してきます。
「このまま治療を続けていいのだろうか」
「痛みや副作用を乗り越えられるだろうか」
と思うこともあるでしょう。
いまにして思えば、このとき妻は自身の身体のことだけでなく、社会的な孤立や、周囲との関係においても悩んでいたのでしょう。
家族や友人の支え
がん治療は患者本人だけの問題で片付けられるほど簡単な問題ではありません。
なるべく多くの人の力を借りないと乗り越えていけないものです。
患者に対する看護についても、一人にかかる負荷を、なるべく多くのサポートを受けることで分散することが大事です。
お住まいの自治体によっては公的なサポートが得られるところもありますが、個人的にはまず身近な人に頼った方が良いと思います。
サポートを受ける患者としても、赤の他人に世話してもらうよりも、気心の知れた身近な人の方が安心するでしょう。
その意味で、筆者は周りの人からたくさんサポートを受け、助けてもらいました。
保育園の送りは筆者の両親に助けてもらい、たまに泊りがけでも家事の手伝いをしに来てくれました。
妻の家族にもとても助けてもらいました。
義母が1か月近く泊まり込んでくれたり、義理の姉も子どもたちをつれて頻繁に顔を出してくれました。
患者にとって、がん闘病生活の中で最も大きな支えとなるのは、家族や友人です。
治療中に感じる孤独や不安を共感してくれて、時には一緒に泣き、時には明るく励まし合いながら、共に過ごしてくれる存在がどれほど大切なものかは、言葉では表現しきれません。
家族や友人のサポートがあってこそ、患者は精神的な強さを保ち、希望を持ち続けることができます。
小さな幸せの積み重ね
辛く苦しい闘病生活の中でも小さな幸せを感じました。
逆に闘病が辛かったからこそ感じられたのかもしれません。
そのような小さな幸せをいくつか共有します。
こどもの成長
闘病生活を続けているときに、2人の子どもがともに小学校に入学することになりました。
抗がん剤治療のタイミングを調整し、妻もそれぞれ入学式に出席することができました。
入学式当日は比較的体調も良く、メンタルの面でも終始安定していました。
どんな薬よりも子どもの成長がなによりも効き目があるようにも感じました。
家族でいる時間が増えた
闘病生活を傍で支えるために、仕事を定時退社できるよう調整をするようになりました。
家事や妻の病院への送迎等でバタバタする日々となりましたが、結果的に家族でいる時間が増え、家族の結束が強くなったように思いました。
仕事に対しても、いかに短い時間で結果を残すかが大事なのかという点に気づき、仕事への向き合い方にも、良い意味で変化ができました。
病院で見知らぬ人に助けてもらう
とある日の病院でのことです。
当時妻は体力の衰えからほとんど歩くことができず、移動は車いすに頼るようになっていました。
病院入口で妻を車いすからおろし、車に乗せようとしていたところ、病院に通う患者の方が妻を車に乗せるのを手伝ってくれたのです。
さらには車いすの片付けまでもやってくれたのです。
このことは1度だけではなく、幾度にもわたってこのような機会に遭遇したのです。
人のやさしさに触れることができ、妻はその都度勇気づけられたことでしょう。
このように、闘病生活が長く続く中でも「小さな幸せ」を見出すことができました。
病院での治療を受けながらも、温かい食事を囲んだり、空を見上げたりと、大切な人と過ごす時間の中で、日常の中にある些細な幸せに気づく瞬間が増えていきました。
今になって思うのは、このような些細な幸せに気づけたのは、がんを経験し、具体的に死を意識するからこそ、かけがえのない「今」を感じ取ることができたからかもしれません。
どんどん悪化する身体
辛く苦しい闘病生活の中にあっても、小さな幸せを見出すという日々を送っていましたが、病魔は確実に身体を蝕んでいきます。
最終的に亡くなることとなる年の年始早々に、妻は急激に身体の活力を失い始めたのです。
筆者も看護に割く時間が増え始め、仕事との両立がままならなくなってきました。
そこで会社を休職し、妻の看護と家庭の仕事に専念することにしました。
休職期間が終わっても妻の元気は戻ることはなかったので、筆者は退職を決意し、完全に看護に専念することにしました。
この頃のことをいま振り返ると、きっともう長くはないのだろうなと、筆者自身感じていたのは事実です。
収入が途絶え、貯金を切り崩す日々が始まり、費用面の不安はピークでした。
ハローワークに行き、待機期間の7日間のみで失業保険の給付を開始することはできましたが(特定理由離職者による支給申請をしました)、それでも収入に関する不安は拭い去れません。
がん保険による入通院の給付が多少でも残っていたので、とても助かったことを覚えています。
容体は徐々に悪化する中で、病院への通院も厳しくなり始めました。
ここで、なるべく身体への負担がかからないようにすべく、訪問看護に切り替えました。
この頃にはもう抗がん剤治療は停止していました。
効果の期待できる薬がなく、副作用で苦しめるよりは緩和ケアに切り替えた方が良いだろうという話を受け、妻と話し合って決めたのです。
緩和ケアとはいえ、痛みや苦しみを完全に取り除くことはできません。
思うように身体を動かすことができない苛立ちも重なり、苦しんでたように思います。
次第に言葉を発することも少なくなっていきました。
最期
約4年半続いた闘病生活も実らず、某年の6月某日、妻は息を引き取りました。
診断当初は1年もたないかもしれないと言われていたのですが、約4年半もの間、子どもの成長を見守るためにがんばってくれたのです。
妻は筆者の自宅で最期を迎えました。妻は生前、せっかく買ったマイホームを汚したくないから、最後は病院で迎えたいと言っていたのです。
ところが直前になって、このように言ってきました。
「やっぱり病院はさみしいから家にいさせてほしい。ごめんね」と。
この言葉が妻と交わした最後の会話となりました。
某年の6月某日、42年の生涯に幕を閉じました。
まとめ
がんとの闘いは、決して簡単なものではありません。
痛みや不安、時には絶望を感じることもあるでしょう。
しかし、その中で見つけた希望や小さな幸せ、そして支えてくれる人々との絆は、何よりも大切なものです。
闘病生活は決して一人ではなく、多くの人に支えられながらも、心の中では希望を失わずに歩んでいくことが、回復への第一歩となります。
今回紹介した筆者の妻に関しては、がんとの闘いの末に、短い生涯に幕を閉じてしまいましたが、がんとの闘いの先には、必ずしも終わりが待っているわけではありません。
闘いながらも「生きる力」を育んでいくことが、闘病生活の大きな意味と言えるでしょう。
また、これは現実的な話として、闘病生活にはお金がかかります。
地獄の沙汰も金次第みたいになりますが、お金があれば治療方法の選択肢が増え、生存率が高まるのは事実です。
闘病生活は患者本人が苦しいのは大前提ですが、そばで支える家族も同じように苦しみを共有します。
そのような中で治療方法の選択の幅が広がったことで、生きることに希望が持てるのであれば、いかに闘病生活が苦しくてもそれを乗り越える糧になります。
がん保険や医療保険はその意味でとても重要な役割を果たすのだと、筆者はこの闘病生活を経て痛感しました。
おすすめ記事
-
 終身保険ってどんな保険?わかりやすくメリットとデメリットを保険のプロが解説2022.08.20
終身保険ってどんな保険?わかりやすくメリットとデメリットを保険のプロが解説2022.08.20 -
 保険の年末調整を忘れた!?出さないとどうなる?証明書が届かない・間に合わない場合の対処法を解説2023.01.30
保険の年末調整を忘れた!?出さないとどうなる?証明書が届かない・間に合わない場合の対処法を解説2023.01.30 -
 女性の専門保険って実際どうなの?保障対象や出産・出産後での金額や女性医療特約はどんな病気に対応しているの?専門家が回答!2023.12.13
女性の専門保険って実際どうなの?保障対象や出産・出産後での金額や女性医療特約はどんな病気に対応しているの?専門家が回答!2023.12.13 -
 共済保険ってどのような保険?共済と生命保険との違いと加入についてのメリットとデメリットを解説します2023.02.22
共済保険ってどのような保険?共済と生命保険との違いと加入についてのメリットとデメリットを解説します2023.02.22 -
 がん保険は必要か?いらない?一時金があるとよい?闘病生活でお金以外に困ったことは?身近でがんと闘った経験を持つFPが解説2024.05.24
がん保険は必要か?いらない?一時金があるとよい?闘病生活でお金以外に困ったことは?身近でがんと闘った経験を持つFPが解説2024.05.24