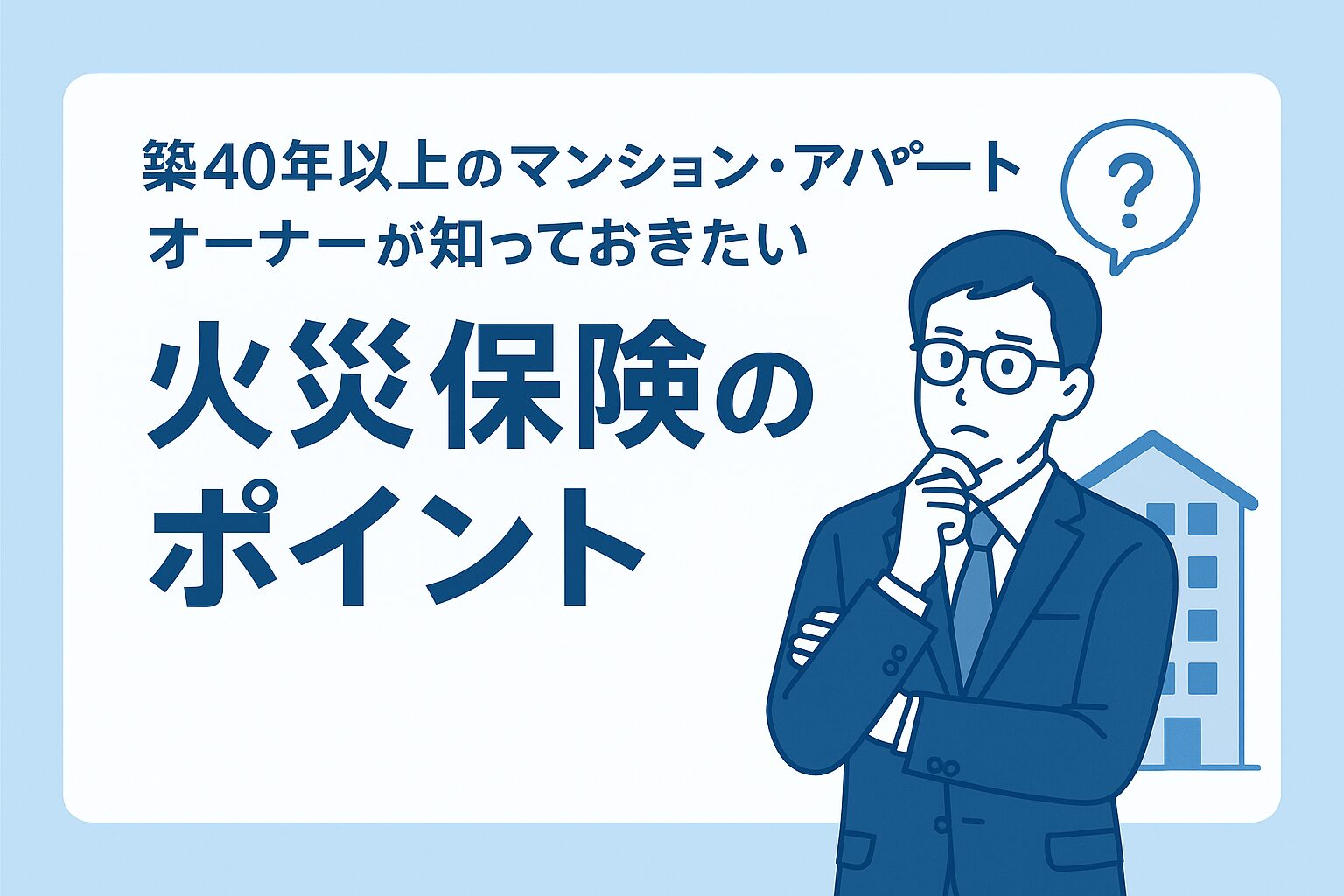リチウムイオンバッテリーのPL保険にリコール対象となる保険会社あり。補償や保険料を比較し解りやすく解説します。

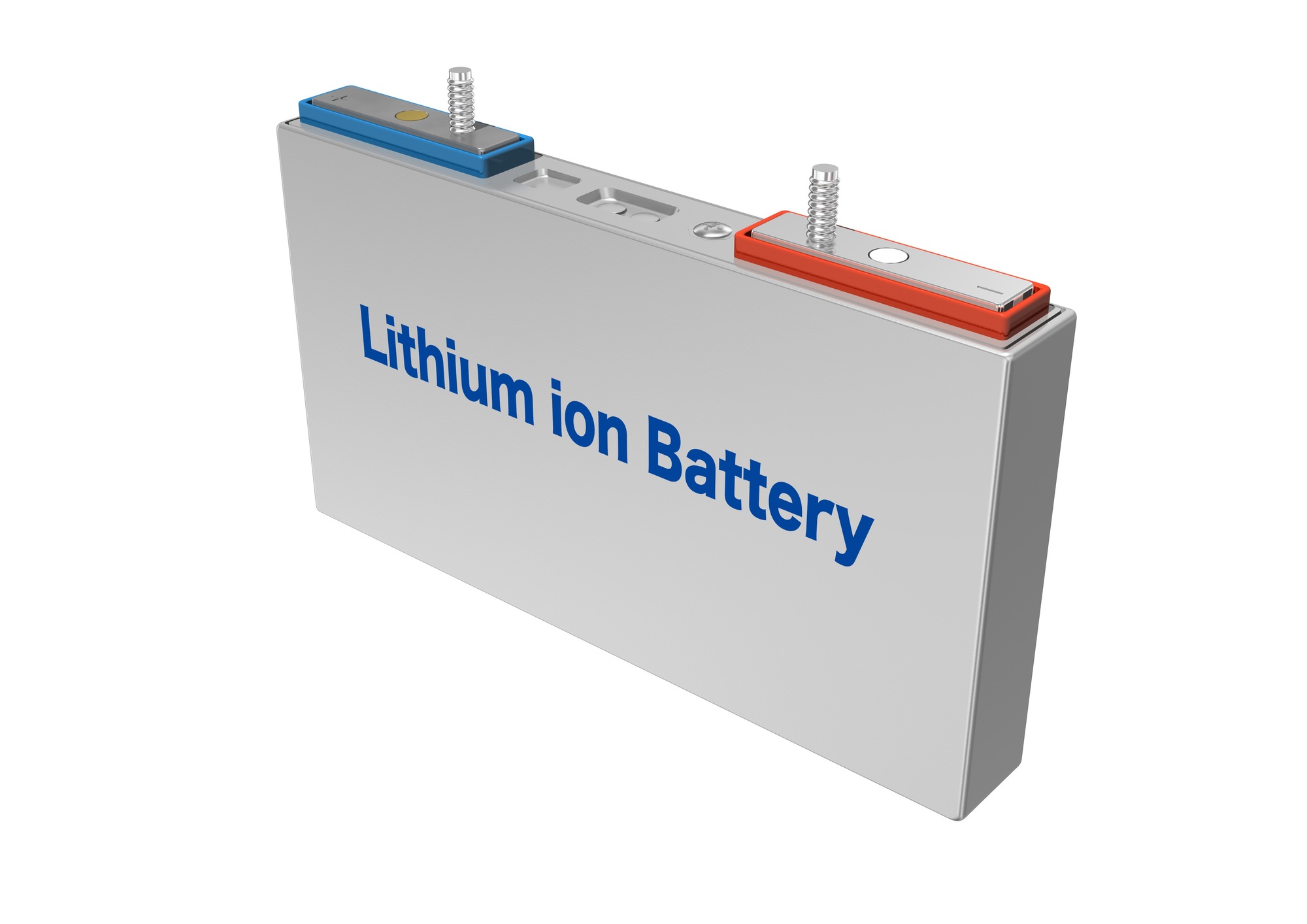
製品の製造やサービスを提供する企業にとって、リスクマネジメントは非常に重要な問題です。
そのため、様々なリスクマネジメントに適した保険商品が開発され、保険会社各社より販売されています。
その中でも、製造事業者にとって特に重要な保険商品が「PL保険(生産物賠償責任保険)」(以下、単に「PL保険」と表記します)と「リコール保険」です。
どちらも、製造事業者におけるリスクをカバーするための保険商品になりますが、それぞれ異なる目的や補償内容を持っています。
ただ、両者の違いを明確に理解している方は、きっと多くはいないのではないでしょうか。
今回の記事では、PL保険とリコール保険の違いについて詳しく解説します。
記事の最後には、PL保険とリコール保険に関して、筆者が現場でよく聞かれる質問と、それに対する回答もまとめてあります。
特に製造事業者は今回の記事を参考に、自社のリスクマネジメントに役立ててもらえたら幸いです。
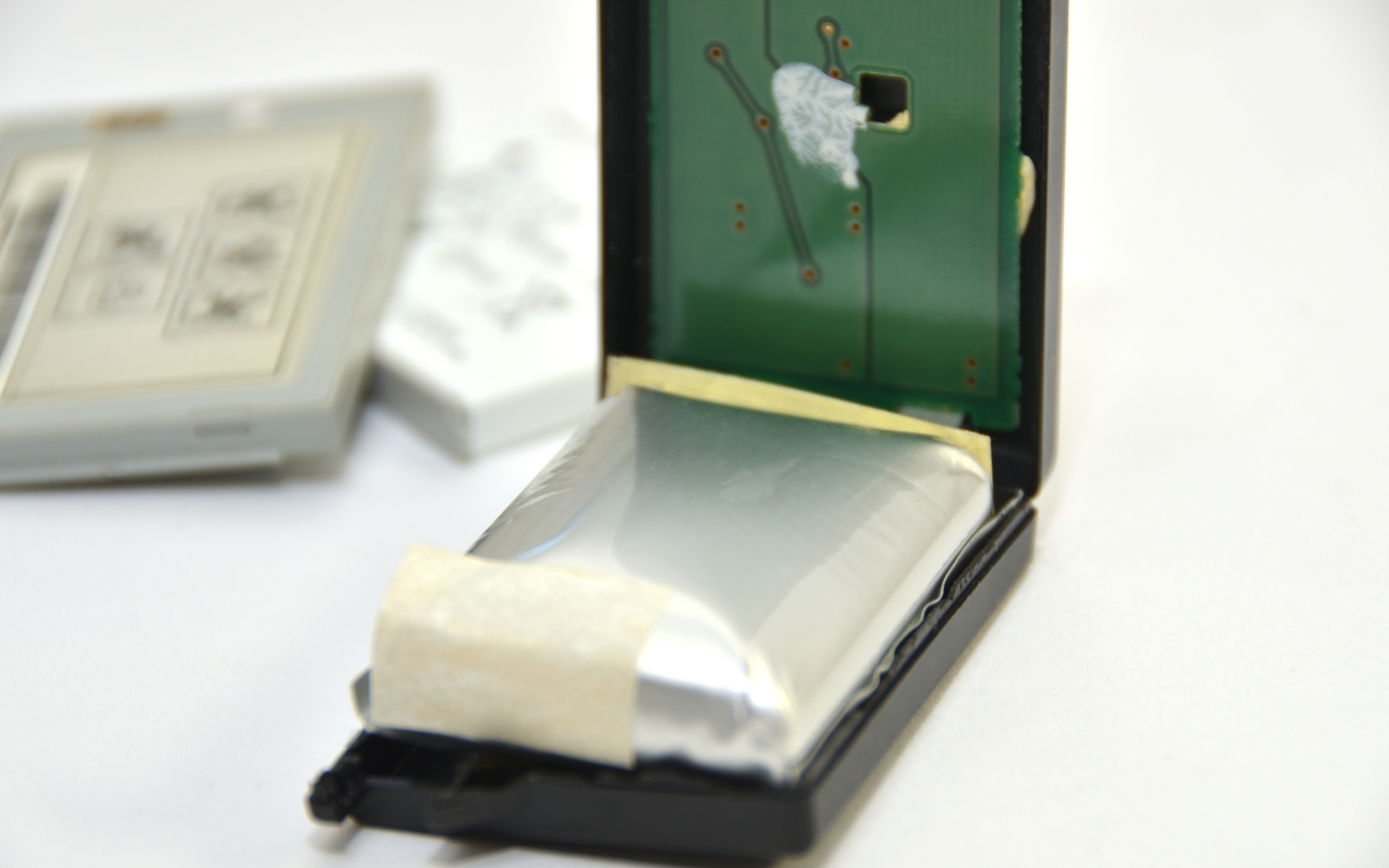
目次
PL保険(生産物賠償責任保険)とは
PL保険は、「製造物責任法(Product Liability Law)」(※)に基づき、保険契約者が製造・販売・輸入した製品が原因で、エンドユーザーがケガをしたり、死亡してしまった場合や、エンドユーザーのモノに損害を与えてしまった場合に、保険契約者が法律上の賠償責任を負担することによって、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を補償する保険です。
(某大手損害保険会社 PL保険パンフレットより抜粋)
※製造物責任法・・・製造物(商品)の欠陥によって生じた損害について、製造業者などが責任を負うことを定めた法律です。
日本では「製造物責任法(PL法)」として、1994年に制定され、1995年に施行されました。
PL保険の主なポイント
PL保険を考える上でのポイントを簡単にまとめると、下記のように整理することができます。
・対象となる主な事業者:製造業者、販売業者などの製品提供者、飲食店経営者および建設業者など。
・目的:製品、商品や提供したサービスの欠陥、不具合による事故や損害に対する法的責任をカバー。
・補償する内容:損害防止費用、緊急措置費用、権利保全行使費用、争訟費用、協力費用、損害賠償金など(その他、保険会社独自の特約により補償内容は拡張の余地あり)。
つまりPL保険では、製品、商品が市場に出た後、サービスの提供後に発生するリスクを対象とし、製品や商品、サービスの欠陥が原因で、消費者等の第三者に損害を与えてしまった場合に、そこで発生する損害賠償責任をカバーします。
このような損害は、時として非常に大きな損害規模にまで発展する余地が内在します。
その経済的損失を被るリスクを補償するために、PL保険はとても重要な役割を果たします。
どんなときに保険金が支払われるか
ここでは、PL保険における補償の対象となる事案について、少し掘り下げて解説します。
PL保険では、損害の直接の原因となる製品を製造した者や、サービスを提供した者に、法律上の損害賠償責任が発生していることが要件とされます。
逆に言うと、法律上の損害賠償責任が発生していない場合は、保険金の支払い対象とはなりません。
この点はリコール保険との比較で非常に重要になります。
損害の具体例
過去に実際に起こったPL保険関連の損害の実例をいくつか紹介します。
ここで紹介するのは、主に製品の欠陥や不具合が原因で発生する事故や被害に関するものです。
家電製品による火災
設計上の欠陥を持っている電気ストーブを消費者が使用していたところ、当該電気ストーブから発火し、家を焼失させてしまった。この事例では、製造者の製品の欠陥に対する法律上の賠償責任が認定されました。
美容器具による健康被害
メーカーの作成した説明書の通りに美容マスクを使用したところ、数日後、顔面と上半身に発疹や痒みが生じ、皮膚の疾患で通院治療を要することとなってしまった。
食品によるアレルギー反応
食品に含まれているアレルギー物質が表示されていなかったため、消費者がアレルギー反応を起こして健康被害(アナフィラキシーショック)を受けてしまった。
自動車部品による事故
自動車の単独事故によって、運転者が半身不随となる重症を負ってしまった。事故の際、エアバッグが適切に作動しなかったことがわかり、その誤作動の原因として、自動車の製造過程で不良部品が使用され、その不良部品によってエアバッグが適切に作動しなかったことが判明した。
上記の事例では、裁判において製造者や販売者が、製品の品質や安全性に関して十分に注意を払わなかったことが認定され、損害賠償を負うことになりました。
なおPL保険における損害事例については、下記の記事でも紹介しています。
あわせて参考にしてください。
【参考記事:生産物・PL保険賠償事故!損害保険金支払い事例17件を一挙公開】
リコール保険とは
リコール保険は、製品に欠陥や危険性が発見された場合に、製品を回収・交換するための費用をカバーする保険です。
リコールは、消費者や市場への被害を最小限に抑えるために必要ですが、その実施には莫大なコストがかかることがあります。
リコール保険は、企業がリコールを行う際に発生する費用(回収・修理費、輸送費、調査費用など)を補償することが目的です。
リコール保険の主なポイント
PL保険と同様、リコール保険についてもポイントをまとめると、下記のようになります。
・対象となる主な事業者:製造業者、販売業者などの製品提供者。
・目的:リコールにかかるコスト(回収、修理、交換、調査費用)をカバー。
・補償する内容:リコール費用、リコール後の顧客対応費用など。
上記からもわかるように、リコール保険では、製品に問題が発覚した際の迅速な対応を支援し、企業がリコールを行うために必要なコストを補償、もしくは軽減するのに力になってくれるものです。
リコールの実施は、企業にとって非常に大きな経済的な負担を伴いますが、リコール保険があればその経済的損失を被るリスクを補償することができます。
どんなときに保険金が支払われるか
リコール保険についても、補償の対象となる事案について、掘り下げて解説したいと思います。
リコール保険で保険金が支払われるケースは大きく下記の3点に分類されます。
・製品の欠陥によるリコール:製品に安全性や品質に関する欠陥が見つかり、その製品を回収または修理するためにリコールが行われた場合。
・リコールにかかる費用:製品を回収するための費用、修理や交換、消費者への通知、返金などにかかる費用が発生した場合。
・企業の責任:企業がその製品に関して不具合があった場合、その責任を果たすために必要な費用(広告、サービス対応、物流費用など)を補償する。
つまりリコール保険においては、契約者に法律上の損害賠償責任が発生するということが、必ずしも要件とされていないという点がポイントになります。
損害の具体例
PL保険同様、リコール保険関連の損害の実例についてもいくつか紹介します。
ここで紹介するのは、いずれも消費者やメーカー側が製品の欠陥や不具合を発見したためにリコールに踏み切ったという事案です。
製品の欠陥による事故発生のおそれ
あるメーカーが販売した自動車のエアバッグをメーカー側で定期検査を実施したところ、欠陥を発見した。
事故時には正常に作動しないおそれがあると判断した結果、自動車の自主回収、無償での検査の実施を決定した。
食品の異物混入
食品メーカーが製造した製品(パン)に、異物(ストローのようなもの)が混入していたことが発覚した。
発覚の経緯は、某県某市内のパン屋で当該製品を購入した消費者からの連絡によるものであった。
健康被害は発見されていないものの、パン製造会社は製品の自主回収をし、製造工程等も含めて調査を実施した。
化学製品の誤使用による事故
化学薬品メーカーが販売した製品に、誤った成分や濃度が含まれていたことが、化学薬品メーカー側の定期検査により発覚した。
その製品が使用された結果、人体に有害な影響を与えうる可能性もあることから、メーカーによるリコールが実施された。
家電製品の火災リスク
家電製品(衣類除湿乾燥機)において、製品内部の除湿ローター付近から発火・発煙する事案が、日本国内のみで複数件の報告を受ける。
原因調査のため、メーカーによる自主回収、無償点検、代替品との交換を実施した。
これらの事例では、製品に欠陥があった場合に発生するリコール費用、事故による損害賠償、回収作業の費用などがリコール保険で補償される対象となります。
PL保険とリコール保険の違い
ここまででPL保険とリコール保険それぞれの概要を解説してきましたが、この2つの保険にはどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは両者の違いについて、3つの観点から解説します。
目的と補償対象
PL保険は、契約者が製造した製品や提供したサービスに欠陥があり、その欠陥が原因で発生した消費者や第三者の身体、財物の損害に対する法律上の損害賠償責任を補償します。
一方でリコール保険では、製品に欠陥が発見された際に行うリコールに関わる費用(回収や交換費用など)を補償します。
つまり、PL保険はあくまで法律上の損害賠償責任が要件とされているのに対し、リコール保険では必ずしも法律上の損害賠償責任は要件とはされていないのです。
リスクのタイミング
PL保険は、製品が市場に出た後であったりサービスが提供された後に、製品を使用した消費者やサービスの提供を受けた者に損害が生じた場合にリスクが発生します。
一方でリコール保険は、製品の欠陥が発見された際に実施するリコールにかかる費用を補償するというものです。
事故が発生している場合はもちろん、事故発生の前であっても製品に欠陥が発見されて自主回収する場合にも補償対象とされるのです。
補償内容の範囲
PL保険は、主に事故や損害賠償に関連する費用を補償対象としています。
補償対象となる費用は主に下記の6つの費用となります。
・権利保全行使費用・・・第三者に権利行使できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用。
・争訟費用・・・訴訟費用、弁護士報酬等の費用。
・協力費用・・・保険会社が事故解決に向けた対応をするのに協力する費用。
・損害賠償金・・・被害者に支払うべき法律上の損害賠償金。
なお、特約を付帯することで補償対象となる範囲を拡張することもできます。
一方でリコール保険は、リコールにかかる費用全般を補償対象としています。
補償対象となる費用は主に下記のものとなります。
・通信費用・・・電話、郵便、FAX、ホームページ開設のための費用など。
・確認費用・・・製品の瑕疵について確認するための費用。
・回収生産物の修理費用・・・回収生産物の修理に要する費用。
・代替品の原価・・・回収生産物と引き換えに代替品を給付する際の、代替品の製造原価。・返還代金・・・回収生産物と引き換えに返還する代金、返還に際して要する手数料、送料等。
・輸送費用・・・回収生産物または代替品の輸送費用。
なおリコール保険は、保険会社ごとに補償対象となる費用に特徴があります。
あくまで上記は一例です。PL保険と同様、リコール保険についても特約を付帯することで補償対象となる範囲を拡張することもできます。
PL保険とリコール補償特約の連携
PL保険とリコール保険はそれぞれに特徴をもっていることが、これまでの解説でわかっていただけたことと思います。
PL保険とリコール保険それぞれの補償範囲をカバーすることで、企業はリスク管理においてさらに手厚くできることになります。
もちろんそれぞれの保険に加入することで、十分なリスク管理という目的は達成できますが、費用面で大きな支出となりえます。
実はリコールの補償はPL保険に特約として付帯することができ、製造業者をはじめ、多くの企業で活用されているのです。
一般的に、リコール保険単体で加入するより、PL保険にリコールの補償を特約として付帯する方が、保険料負担にかかる費用は大幅に軽減することができます。
リスク管理の仕組みを整理すると、次のようになります。
まず主契約であるPL保険で、製品に起因する事故や損害賠償責任をカバーします。
ここで製品が消費者に対して直接的な損害を与えた場合に、企業が負担する賠償金や訴訟費用などを補償します。
さらにリコール補償特約で、製品の不具合が発覚し、その回収にかかる費用や企業の販売停止に伴う損失を補償します。
このように、PL保険にリコール補償特約を付帯することで、互いに補完し合う形で、製品に関連するリスク全般を網羅するため、企業はこれらの保険に加入することでより包括的なリスクマネジメントを実現することができます。
合理的なリスク管理手法のひとつとして参考にしてください。
リコール補償特約付帯の注意点
ここまでの解説を聞くと、製造業者における製造品に関するリスク対策としては、PL保険にリコール補償特約を付帯することがオールマイティな対策手段として思われるかもしれません。
しかしこの手法でも注意が必要な点が2点あります。それぞれ解説していきます。
注意点①:支払限度額が少ない
PL保険に付帯するリコール補償特約は、設定できる支払限度額(補償額)が決して十分な金額とはいえないのです。
保険会社によって異なりますが、概ね1,000万円という取り扱いが多いです。
いざリコールをするとなると、1,000万円でリコールにかかる費用をカバーしきれるでしょうか。
たとえば自動車メーカーによるリコールが発生したと想定してみましょう。
自動車メーカーによるリコールの場合、リコール対象となる車両の修理や部品交換が無料で行われることが一般的です。
しかし、修理や部品交換にはかなりのコストがかかる場合もあります。
仮にエアバッグのリコールを発表した場合には、1台あたりの修理費用が5万円程度になることがあります。
このケースで、リコール対象車両の台数が100万台を超えるような場合、リコール費用は数百億円に達することもあります。
契約者が取り扱っている製品の性質、リコールの可能性、発生した場合の金額の見積もりをした上で、リコール補償特約の1,000万円の補償でカバーできるのかをまずは検討することが非常に重要です。
もし足りないのであれば、リコール保険を単体で加入することを検討する必要が出てきます。
注意点②:支払要件における注意点
PL保険にリコール補償特約を付帯した場合、リコール補償特約における支払いにはPL事故が発生していることが要件となります。
一方でリコール保険の支払い要件は、あくまでリコールの実施です。つまりPL事故の発生、および法律上の損害賠償責任の発生は要件とはされていないのです。
特約の支払い要件の方が厳しくなっているという点はしっかりおさえておくべきです。
このように、取扱品目やリコール可能性を考えた場合、致命的にもなりうる注意点もあります。
上記の2点は必須項目としてしっかりおさえておきましょう。
提案の具体例を紹介
ここで、筆者が実際にお客様に提案した際の具体例を紹介します。
詳細な情報は伏せますが、お客様の事業の概要やニーズと、それに対する提案内容を記載します。
【お客様情報】
・業種:電子機器部品、デバイスの製造
・生産物または仕事の具体的な内容:リチウムイオンバッテリーの販売
・直近の売上高:120,000千円
・お客様の要望:自社が製造した製品の販売にあたって、PLリスクやリコールが発生した場合の費用負担についても、なるべく安い費用負担でカバーしたい。リコールリスクよりもPLリスクを優先度高めでカバーしたい。
【提案内容】
保険期間:1年間
売上高:120,000千円
払込方法:一時払

【支払限度額:3億円】
1事故:300,000千円/期間中:300,000千円
【免責金額】
0千円
【C.S.L(身体・財物共通)】
1事故:300,000千円/期間中:300,000千円
【特約】
共通支払限度額方式
見舞金費用補償
事故対応費用補償
経済的損害補償
生産物損害・回収追加
不良完成品等損害補償
訴訟対応費用補償
【合計保険料】
76,950円

【支払限度額:1億円】
1事故:100,000千円/期間中:100,000千円
【免責金額】
0千円
【C.S.L(身体・財物共通)】
1事故:100,000千円/期間中:100,000千円
【特約】
共通支払限度額方式
見舞金費用補償
事故対応費用補償
経済的損害補償
生産物損害・回収追加
不良完成品等損害補償
訴訟対応費用補償
【合計保険料】
52,930円
今回提案にあたって、当初は取引のある損害保険会社複数社で見積もりを計算し、提案するつもりでいました。
しかし、対象品目であるリチウムイオンバッテリーが、ほとんどの損害保険会社では補償対象外品目だったのです。
唯一、〇〇損害保険会社は引き受け対象としていたので、同社の保険商品を提案したところ、成約に結び付きました。
今回は特にリチウムイオンバッテリーを補償対象としている損害保険会社を探すのに苦労しました。
対象品目によっては引き受け自体に制限がかかる場合もありますので、注意しましょう。
Q&A:PL保険およびリコール保険に関連した質問
最期に、筆者が現場でよく聞かれるPL保険およびリコール保険に関連した質問と回答を紹介します。
質問:PL保険とリコール保険は一緒に加入しなければならない?
町工場を経営している者です。金属のネジ等を中心に作っています。
うちの作ったものが原因で消費者に迷惑がかかったらいけないからと、PL保険には加入しています。
先日、保険屋さんからリコール保険はどうかと提案受けました。
話を聞いていて、リコールが発生する可能性もないわけではないので、入っておきたいと思ったのですが、リコール保険はPL保険と一緒に加入しなければならないのでしょうか?
ついこの間、PL保険の契約を更新したばかりなので、一緒に加入しなければならないとなると、あと1年近く待たないとなりません。
このあたりのことを教えてください。
回答|PL保険とリコール保険はそれぞれ単体で加入することができます。
PL保険とリコール保険は必ずしも一緒に加入しなければならないものではありません。
もちろん同時期に加入することもできますが、それぞれ別のタイミングで加入することもできます。
また、同時に加入する方法のひとつとして、PL保険を主契約として、リコールの補償内容を特約として付帯するというやり方も可能です。
この特約付帯の場合であっても、保険期間の途中で付帯することができます。
ただし、リコールの補償内容を特約としてカバーする場合に気を付けるべき点として2点お話します。
まず1点目、特約でカバーする場合、支払限度額が少ないという点です。
保険会社にもよりますが、だいたい1,000万円に設定されていることが多いです。
この金額で十分かどうかは、よく検討すべきです。十分でないと想定できる場合は、リコール保険単体の加入をおすすめします。
注意すべき点の2点目は、支払要件の違いです。
リコールの補償を特約として付帯する場合、主契約のPL保険において支払い要件を満たしていないと、特約部分では支払いできないのです。
たとえばPL事故は起こっていないのに、出荷した製品に不具合が発覚したのでリコールしたとしても、そのリコールにかかる費用は補償されません。
その点、リコール保険を単体として加入していれば、リコール保険における支払い要件であるリコールの実施は満たすので、補償対象となる余地はあります。
多くの企業はPL保険とリコール保険を別々に加入することが一般的ですが、PL保険にリコール補償の内容を組み込むことも可能です。支払限度額と支払い要件の相違点に注意して検討してみてください。
質問:PL保険とリコール保険はどちらも必須ですか?
製造業を営んでいる者です。恥ずかしい話、損害保険には事務所の火災保険と従業員の労災上乗せのみで、その他の賠償責任保険等には加入していないのです。
もちろんPL保険もリコール保険も加入していません。同業者の集まりに顔を出すと、たまに保険の話になるのですが、ほとんどの会社でPL保険には加入していることがわかりました。
リコール保険に加入している会社もちらほら確認できるといった感じです。
PL保険とリコール保険はどちらも必ず加入すべきでしょうか?教えてください。
回答|業界によってはどちらも有用ですが、PL保険を優先度高めて検討しましょう。
PL保険は多くの業界で重要かつ必須の保険とされており、特に製造業や消費財業界では強く推奨されます。
一方、リコール保険は必須とまでは言えませんが、製品リコールが発生した場合に膨大な費用がかかることがあるため、企業にとって有用な保険であることは確かです。
特に消費者向け製品や自動車業界などでは、リコール保険に加入することは推奨されています。
質問者様の業界や製造品目はどのようなものかはわかりませんが、製造業者であることから、最低限PL保険の加入は必須と言えます。
質問者様の作った製品が原因で消費者が損害を被ってしまった場合、その損害規模によっては経営の危機に直結するダメージを負いかねません。
優先度を高めてぜひ検討してください。
リコール保険についても、業界や製造品目によっては検討の余地が出てきます。
なおリコール保険に加入しなくとも、PL保険にリコール補償特約として付帯することもできます。
設定できる補償金額は小規模なものになりますが、ぜひ検討してください。
質問:リチウムイオンバッテリーのPL保険にリコール補償を付帯できる保険会社はありますか?
車載ドライブレコーダー向けのリチウムイオンバッテリーを製造している会社です。
2024年6月頃、保険代理店より「リコールに関する特約が付帯できなくなった」との連絡を受けました。
実際には、現在リチウムイオンバッテリーのPL保険にリコール補償を付帯できる保険会社はあるのでしょうか?
回答|現在、リコール補償を付帯できる保険会社は1社のみです。
リチウムイオンバッテリーは発火・発煙などのリスクを伴う製品であるため、ほとんどの損害保険会社では「引受対象外の品目」として扱われています。
そのため、PL保険に加え、リコール費用を補償する特約を付けることが極めて困難になっています。
しかし、現在も1社だけは、一定の条件のもとでリコール補償特約の付帯が可能です。
ただし、リスク評価や安全対策状況、販売ルート、使用用途などを詳細に審査されたうえでの個別判断となるため、必ずしもすべてのリチウムイオンバッテリーが引き受け対象となるわけではありません。
製品の種類や供給先、過去のトラブル履歴などによっては、引受が拒否されるケースもありますので、契約前には事前に十分な情報提供とリスク評価への対応が求められます。
まとめ
今回の記事では、PL保険とリコール保険のそれぞれの特徴や違いについて解説しました。
PL保険とリコール保険は、どちらも企業が製品のリスクに備えるための重要な保険ですが、その役割は異なります。
PL保険は、製品の欠陥による事故や損害に対する責任をカバーするのに対して、リコール保険では、欠陥が発見された場合にリコールにかかるコストをカバーします。
企業が製品を市場に出す際には、これらの保険を適切に組み合わせてリスクマネジメントを行うことが大切です。
PL保険とリコール保険は、どちらの方が上位というものではなく、相互に補完しあう関係にあります。
ただ、どちらを優先すべきかという点に関しては、筆者の個人的な見解でいえば、法律上の損害賠償責任をカバーするという点でPL保険を優先すべきと考えます。
ひとつの意見として参考にしてもらえたら幸いです。