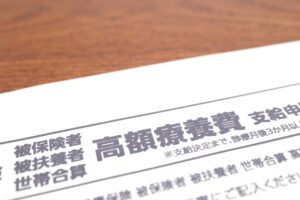退職代行サービスとは?利用のメリットとデメリット!活用事例を紹介


目次
退職代行サービスとは?その仕組みと利用の広がり
近年、働き方改革や労働環境の多様化とともに注目を集めているのが「退職代行サービス」です。
これは、本人に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な手続きをサポートしてくれるサービスを指します。
従来、退職の意思表示は社員本人が上司や人事部に直接伝えるのが一般的でした。
しかし、パワハラや長時間労働などによって上司と話すこと自体が精神的負担になっている人や、強引な引き留めで退職できないといったケースが増える中、退職代行サービスのニーズは年々拡大しています。
今回の記事では、退職代行サービスについて深堀りします。筆者の経験談も交えて、事例として紹介したいと思います。
退職代行サービスの運営者
退職代行サービスは、運営者の属性によって大きく3種類に分類することができます。
それは「弁護士」、「労働組合」、「民間企業」の3つであり、法律上、対応可能な業務に制限がかかるため、運営者によってサービス内容・範囲に特徴があります。
運営者ごとの特徴を下記に簡単に解説します。
弁護士の退職代行サービス
弁護士の運営する退職代行サービスは、3つの種類の中で最も対応できる業務が広いというのが特徴です。
弁護士が交渉の窓口に立ってくれるので、たとえば未払いの賃金を請求したり、会社から損害賠償請求をちらつかされている場合等といった交渉の場面では、退職従業員にとって心強い味方となってくれます。
ただし、利用料の面では3つの種類の中では最も高額で、相場として30,000円~100,000円くらいとなります。
タフな交渉の余地があり、法的な問題が発生しそうな場合は弁護士の退職代行サービスが適していると言えます。
労働組合の退職代行サービス
労働組合の運営する退職代行サービスは、対応可能な業務範囲の広さの割に、比較的低廉な利用料(20,000円~50,000円くらい)という特徴があり、3つの種類の中ではバランスの良いサービスと言うことができます。
損害賠償請求といった訴訟には対応できないものの、団体交渉によって退職条件の交渉ができるのはメリットです。
ただし法的な問題に発展する場合は、別途弁護士に依頼する必要があり、その分の費用も別途発生します。
民間企業の退職代行サービス
民間企業の運営する退職代行サービスは、3つの種類の中で最も低廉な料金(20,000円前後)で利用できます。
退職に当たって法的な問題が発生しなさそうな場合で、「自分の口から退職の意思を伝えられない」といった方には向いていると言えます。
ただし、民間企業の退職代行サービスの場合、業者の立ち位置は、あくまでサービス利用者の退職の意向を伝えるだけの「使者」であり、交渉事は基本的に行いません。
安心して任せるには、弁護士や労働組合の運営するサービスを利用した方が良いと言えます。
以上に解説した3種類の運営事業者ごとにその特徴をまとめると、下記のようになります。
【サービス内容比較表】
| 弁護士 | 労働組合 | 民間企業 | |
|---|---|---|---|
| 業務範囲の広さ | ◎ | 〇 | △ |
| 退職意思の伝達 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
| 退職条件の交渉 | 対応可能 | 対応可能 | 対応不可 |
| 訴訟対応 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 |
| サービス利用料 | 3~10万円 | 2~5万円 | 2万円前後 |
退職代行サービスの仕組み
退職代行サービスは、本人に代わって「会社に退職の意思を伝え、退職手続きをスムーズに進める」ことを目的としたサービスです。
運営者やサービス料金によっては、単に「辞めます」と伝えるだけでなく、労働契約の終了に伴う一連のプロセスをサポートする役割を担ってくれるところもあります。
ここでは、どのような流れや仕組みで進んでいくのかを詳しく見ていきましょう。具体的に7つのステップに分類し、それぞれ解説します。
ステップ①:利用申し込みと相談
まずは利用者が退職代行業者に相談することから始まります。
最近では電話やメールに加え、LINEなどのSNSで24時間相談を受け付けている業者が多く、相談までの心理的なハードルは下がっています。
相談時に確認されるのは主に以下の内容です。
・勤務先の会社名や業種、雇用形態(正社員・契約社員・アルバイトなど)
・退職希望日(即日か、日数を空けるか)
・有給休暇の残日数や消化の希望有無
・未払い残業代や給与の有無
・貸与物(制服・PC・社員証など)の有無
これらを踏まえ、業者が「代行可能かどうか」「弁護士対応が必要かどうか」等を判断します。
ステップ②:契約・支払い
相談後、正式に依頼する場合は利用契約を締結します。支払い方法はクレジットカードや銀行振込が中心ですが、最近ではPayPayなどのキャッシュレス決済にも対応している業者が増えています。
費用は、民間企業が運営するサービスの場合は2万円程度が一般的ですが、弁護士や労働組合が運営する場合はやや高額(5万〜10万円程度)になる傾向があります。
ステップ③:会社への連絡
契約が完了すると、いよいよ退職代行業者が利用者の勤務先へ連絡を入れます。
主な連絡手段は「電話」と「書面」です。
・電話:会社の上司や人事部に直接電話し、「本人は退職の意思を固めているため、今後は本人への直接連絡は控えてほしい」と伝えます。
・書面:退職届や通知書を作成・郵送することで、退職の意思を正式に伝えることもあります。
この段階で、会社は利用者本人に直接連絡を取ることが難しくなり、やむを得ず代行業者を通じてやり取りを進めるという流れができあがります。
ステップ④:退職手続きの進行
会社側は、退職の意思を受理すると次のような事務処理に入ります。
・退職届の受理
・貸与物(社員証・制服・備品など)の返却方法の案内
・源泉徴収票・離職票・雇用保険関連書類の送付
・最終給与の精算
利用者は業者の指示に従って、退職届を郵送したり、会社の持ち物を宅配便で返却したりするだけで済むため、会社に直接出向く必要はありません。
ステップ⑤:法的交渉の有無
退職代行のサービス内容には、大きく分けて2種類あります。
①一般の代行業者(民間企業)でできるもの(非弁業者)
退職の意思を伝えることがメイン。
※有給休暇の消化や未払い賃金の請求などの交渉は行えない。
※法的交渉が必要な場合は別途、弁護士に依頼する必要がある。
②弁護士や労働組合が運営する退職代行でないとできないもの
退職の意思を伝えることに加え、会社側との条件等の交渉までの実施。
※訴訟の対応といった法律上の交渉は、弁護士でないとできません。
利点として、下記のようなことが挙げられます。
・「有給を全て消化したい」「残業代を請求したい」といった要求を会社に正式に伝えられる。
・費用は高くなるが、権利を守りながら退職できる。
利用者が「ただ辞めたい」だけなのか、「未払い分もきちんと請求したい」のかによって、選ぶべきサービスは異なります。
ステップ⑥:即日退職は可能か?
法律上、退職は労働契約や雇用形態によって取り扱いが異なります。
正社員(無期雇用):民法上、退職の意思を伝えてから原則2週間後に効力が発生します。ただし、会社との合意や有給休暇を利用することで実質的に「即日退職」が可能な場合も多い。
有期契約社員・アルバイト:契約期間の途中であれば「やむを得ない理由」が必要になるが、実際には会社側がトラブル回避のため、早期退職を認めるケースも多い。
退職代行サービスは、この「即日退職のハードル」を下げるサポートをしてくれる存在でもあります。
ステップ⑦:退職成立後のフォロー
退職代行業者の中には、退職が成立した後も「転職エージェント」や「キャリア相談」と提携しているところがあります。これにより、退職後すぐに新しい仕事を探せる環境が整えられているケースも少なくありません。
退職代行が利用される背景
ここまで退職代行サービスの仕組みやその特徴について解説してきましたが、退職代行が必要とされる背景には、下記のような日本特有の労働文化があります。
「辞めづらい空気」
終身雇用や年功序列の文化の中で、退職は「裏切り」とみなされがちで、本人が退職を切り出すこと自体が精神的な負担になります。
引き留めや圧力
上司や会社が退職届を受け取らず、長期間引き延ばされるケースも少なくありません。
ハラスメントや過労
すでに心身が疲弊しており、直接やり取りすることが困難な状況に陥っている人もいます。
こうした問題を解消する手段として、退職代行サービスは「最後の砦」として選ばれるようになってきたのです。
退職代行サービスを利用することのメリット
ここでは退職代行サービスを利用することで得られるメリットについて解説していきます。
メリット①:精神的負担の軽減
退職代行の最大のメリットは、なにより「上司や会社と直接やり取りしなくて済む」ことです。退職を申し出る場面は、多くの人にとって強いストレスを伴います。特に、パワハラ上司や強い引き留めを想定している場合は、「辞めたい」と切り出すだけで精神的に大きな負担になります。退職代行を利用すれば、本人に代わって業者が退職の意思を伝えてくれるため、直接対話による心理的ダメージを回避できます。
メリット②:即日で出社をやめられる可能性
通常、正社員が退職を希望する場合は「退職の意思表示から2週間後」に効力が発生します(民法627条)。しかし、退職代行を利用することで「即日出社不要」となるケースも少なくありません。業者が会社に連絡を入れた時点で本人の意思が明確に伝わり、会社側もトラブルを避けるために早めに了承することが多いためです。心身が限界に達している人にとって、このスピード感は大きな安心材料となります。
メリット③:ハラスメントや引き留めから解放される
退職を伝えた後に起こりやすいのが「強引な引き留め」や「退職理由への詮索」です。場合によっては「裏切り者だ」「代わりがいないから認めない」といったパワハラまがいの発言をされることもあります。退職代行サービスを使えば、こうした不当な圧力から距離を置けるため、安全に退職できる環境が整います。
メリット④:運営者が弁護士なら法的権利の行使も可能
弁護士が運営する退職代行業者に依頼すれば、未払い残業代や退職金の請求、有給休暇の消化交渉といった「法的な交渉」まで対応してもらえます。民間企業が代行業者(非弁業者)の場合ではできない領域ですが、弁護士が介入することで、自分の労働者としての権利を最大限守りながら退職できるという点は大きなメリットです。
メリット⑤:非正規雇用・アルバイトでも利用可能
退職代行サービスは正社員だけでなく、アルバイトや契約社員も利用できます。学生や副業として働く人が「シフトを減らしてほしいと頼んでも認められない」「辞めたいのに脅される」といった状況に置かれるケースは少なくありません。そのような場合でも、このような代行サービスを使えば円滑に退職手続きを進めることができます。
メリット⑥:プライバシーの保護と安全性
退職代行業者を通じて会社とやり取りするため、会社が本人に直接連絡することを控えるケースが多いです。特に精神的に追い込まれている人にとっては「電話やメールが来ないだけでも安心できる」という心理的効果があります。
退職代行サービスを利用することのデメリット
退職代行サービスを利用するにあたって、メリットもあれば当然デメリットもあります。デメリットについても触れておきたいと思います。
デメリット①:費用がかかる
退職代行サービスの利用料は、運営する事業者にもよりますが、安くても2万円程度が相場です。さらに、弁護士が対応する場合は5万〜10万円程度かかることもあります。特に若年層やアルバイトの利用者にとっては大きな出費となるため、「ただ辞めるだけにお金を払うのはもったいない」と感じる人も少なくありません。
デメリット②:給休暇の消化や金銭請求は非弁業者では不可
運営事業者が民間企業であったりと、通常の退職代行業者(非弁業者)は「会社に退職の意思を伝える」ことしかできません。有給休暇を必ず使いたい、残業代を請求したい、といった交渉はできず、自分で対応するか弁護士に依頼し直す必要があります。そのため、サービス内容を理解せずに依頼すると「思っていたほどメリットがなかった」と感じるリスクがあります。
デメリット③:会社との関係悪化の可能性
代行業者を使って退職した場合、会社側には「本人が直接辞めることすらできなかった」という印象が残ることがあります。将来的に同じ業界で再就職する際や、人間関係が狭い業種では自分自身の評判に影響を与える可能性もゼロではありません。特に小規模な業界や地域密着型の企業では注意が必要です。
デメリット④:即日退職が必ず認められるわけではない
退職代行を利用しても、法律上は無期雇用の場合「退職の意思表示から2週間後」に効力が発生します。そのため、会社が形式上は「即日退職は認めない」と主張する可能性もあります。実務的には出社不要となるケースが多いものの、「法的には退職成立まで2週間必要」という点をしっかり理解しておくことが重要です。
デメリット⑤:業者の質に差がある
退職代行サービスは急速に増えた分、業者ごとの質に大きな差があります。中には運営実態が不透明だったり、利用者の相談を十分に聞かずに機械的に対応したりする業者も存在します。また、法的知識がないのに「有給を必ず取れる」など誤解を招く説明をするケースもあるため、利用前に信頼できる業者かどうかを確認する必要があります。
退職代行サービスの活用事例を紹介
ここでは退職代行サービスの利用事例をいくつか紹介したいと思います。
筆者も業務の性質上、従業員の退職の現場に触れる機会が多くあります。
そのような中で、ここ数年、退職代行を利用されたケースを多く経験しました。そのときの経験を参考に、事例として紹介させていただきます。
【退職代行の利用事例①:新入社員が精神的に追い詰められたケース】
◆退職時の状況
22歳の新入社員Aさんは、入社直後から長時間労働と上司の厳しい叱責に悩まされていました。配属からわずか2か月で心身ともに限界を感じ、毎朝出社前に体調不良や不安発作を起こすようになりました。退職を考えましたが、「新人で辞めるなんて許されない」と言われるのが怖く、上司に話す勇気が出ませんでした。
◆退職代行サービス利用の流れ
Aさんは深夜に退職代行業者にLINEで相談し、その日のうちに正式依頼。翌朝、業者が会社へ連絡を入れ、「本人は即日退職を希望しているため、出社は不要」と伝達しました。会社側は驚いたものの、連絡窓口が業者に一本化されたため、Aさんに直接連絡を取ることはありませんでした。
◆結果
Aさんは翌日から出社せずに済み、精神的な負担が大幅に軽減しました。有給休暇付与前の退職となったため、休暇の消化については交渉の余地がなかったものの、最終給与と必要書類は自宅に郵送されました。Aさんは休養後、転職活動を始め、より自分に合った職場に再就職しました。
【退職代行の利用事例②:パワハラと引き留めに悩んだ中堅社員】
◆退職時の状況
34歳の営業職Bさんは、10年以上勤務した会社で上司からのパワハラを受け続けていました。暴言や過大なノルマ設定に加え、退職を申し出ても「お前が辞めたら部署が予算はどうするんだ」「辞めさせるつもりはない」と拒否され続け、退職届すら受理してもらえませんでした。心身が疲弊し、うつ症状が出始めたため、退職代行サービスに相談しました。
◆代行利用の流れ
Bさんは弁護士が運営する退職代行に依頼することにしました。弁護士が会社に正式な通知を送り、退職意思を法的に主張しました。さらに、有給休暇の全日数消化を要求し、未払い残業代についても支払いを求めました。
◆結果
当初、会社は強硬姿勢を崩さなかったものの、最終的には法的トラブルを避けるためBさんの退職を承認しました。有給休暇は全て消化され、さらに未払い残業代として約50万円が支払われました。Bさんは「精神的に限界だったが、弁護士に依頼したことで安心して辞められた」と振り返っています。
【退職代行の利用事例③:アルバイトでも辞められないケース】
◆退職時の状況
19歳の大学生Cさんは、飲食店でアルバイトをしていました。人手不足を理由に、シフトを一方的に増やされ、学業に支障が出るほどの負担にまで発展しました。しかし辞めたいと伝えても「代わりが見つかるまで許さない」「辞めるなら損害賠償請求する」と脅されました。大学生でまだ無知だったCさんは、それ以上の退職の意向は怖くて言い出せませんでした。
◆代行利用の流れ
Cさんは低価格でアルバイト対応を行う退職代行業者を見つけてすぐに依頼。業者が店長に連絡し、「本人は退職を決意しているため、今後のやり取りは控えてほしい」と伝達しました。
◆結果
翌日から出勤せずに済み、残っていた給与も後日銀行口座に振り込まれました。脅されていた損害賠償請求はもちろん行われず、トラブルなく退職完了しました。Cさんは「学生でも使えるのは助かった」と話しています。
【退職代行の利用事例④:地方勤務の単身赴任社員】
◆退職時の状況
45歳のDさんは、家族と離れて地方に単身赴任中でした。慣れない環境に加えて業務量が多く、心身に不調をきたしていました。Dさんの異変を察知した家族に、これ以上の心配をかけたくないという思いを持つようになり、Dさんは会社を辞めたいと考えました。しかし直属の上司が厳格で「退職は絶対に認めない」と強く言われる状況でした。
◆代行利用の流れ
Dさんは退職代行サービスを通じて退職届を提出。業者が会社と連絡を取り、貸与物の返却についても宅配便で対応可能と調整しました。
◆結果
Dさんは実家に戻る形で退職が成立しました。赴任先に戻る必要もなく、無理に顔を合わせることなく退職手続きを完了できました。
退職代行を利用した方が良い場合
前項で退職代行サービスの利用事例を紹介しましたが、実際には従業員が会社を退職するにあたって、退職代行サービスを利用しなければならないという場合は多くはありません。
ここでは退職代行サービスの利用を検討した方が良い場合として、3つのケースを紹介します。
もしこの記事を読んでいる方で、いまの職場を退職したいと考えている場合は、下記に挙げる3つのケースいずれかに該当するかといった点も参考にして、サービスの利用を検討してみましょう。
違法な長時間労働
長時間労働が続く場合は、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。具体的な基準として、月に80時間の残業時間が当たり前のように発生するような労働環境は、違法となる可能性が高いです。残業時間の管理がいい加減な職場は、従業員に対する「安全配慮義務」「健康配慮義務」を尽くしているとは言えません。心身に異変が生じる前に退職代行サービスを利用するのは、健康管理・精神衛生の面でも有効です。
ハラスメントが蔓延している
職場でパワハラ・セクハラといったハラスメントが蔓延しているような職場環境の方も、退職代行サービスを利用を検討すべきです。そのような環境では、退職を申し出ても様々な理由をつけてにぎりつぶされてしまう可能性も高いです。さらには、退職を申し出ることでハラスメントに拍車がかかることすら考えられるので、第三者に入ってもらうことは有効です。
心身に異常をきたしたとき
問題のある職場環境に身を置き続けたことで、実際に心身に異常が出てしまった場合は、すぐに退職代行サービスの利用を検討しましょう。アクションが遅くなってしまうことで、心身の不調も進行してしまいかねません。仮に職場環境に馴染めない原因が自分自身にあるとしても、心身の不調が現に出てしまっているのであれば、一刻も早く不調の原因となっている環境から脱出し、回復に努めるべきです。
退職代行サービスの利用者層と今後の展望について
とある調査会社によると、退職代行サービスを利用して退職した人が在籍していた企業は20%を超えています(2024年のデータ)。
その利用者層について、20~30代前半の新入社員や若手社員が多い傾向にあるものの、40代でも一定割合で存在しており、サービスの普及が広まっていることがわかります。
このようなサービスの普及には、入社後すぐに「思っていた仕事内容と違う」「職場環境がつらい」等と感じた場合、自分で辞める勇気が持てず、このような代行サービスに頼るケースが増えてきたということが背景にあります。
特にブラック企業で働く人々にとっては心強い存在となっています。
今後もこのようなサービスの普及の広まりは加速し、その市場規模は60億規模にもなる見込みが予測されています。
従業員を雇用する企業側としても、労働環境の改善を進め、対話を重視し法整備を進めるといった動きが活発になります。
社会全体としても、「退職の自由」が認められる風潮も強まっています。
退職代行サービスは、その象徴的な存在であり、今後さらに法的整備やサービス内容の多様化が進むことでしょう。
まとめ
退職代行サービスは、従来の「会社に辞意を直接伝える」という固定観念を覆し、社員の自由な働き方や人生の選択を後押しする新しいサービスです。
もちろん、利用には費用やリスクも伴いますが、精神的に追い込まれている人にとっては非常に有効な手段となり得ます。
重要なのは、自分に合ったサービスを見極め、安心して次のステップへと進むことです。