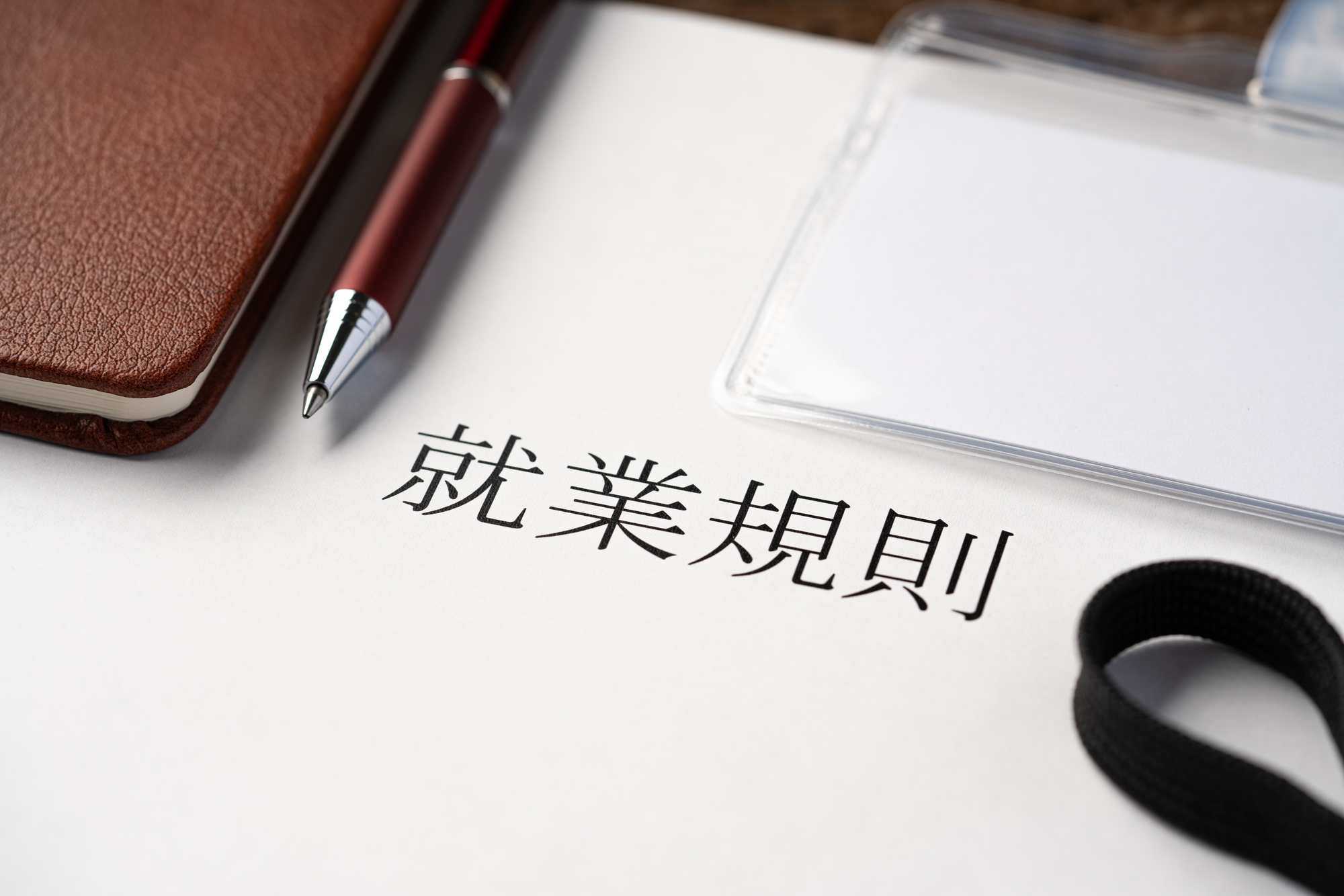法人設立の社会保険は必要?補償内容や種類は?退職した時の手続きは?未加入のデメリットは?


サラリーマンという雇われの身から、独立して一国一城の主になって社会に貢献したいと考えたことのある人はきっと多いことでしょう。
しかし独立して法人を立ち上げるとなると、サラリーマン時代は会社がやってくれていた様々な手続きを自分でしなければならなくなります。
その中で最も重要なもののひとつに社会保険があります。
今回は企業と従業員を取り巻く社会保険について、質問に対する回答を通じて解説していきたいと思います。
目次
質問:法人設立に必要な保険の種類を教えてください。
現在サラリーマンですが、近い将来、脱サラをして法人を立ち上げようと考えています。
法人化すると社会保険の手続きが必要になると思いますが、具体的に何の保険の手続きが必要なのかわかりません。
必要な保険の種類を教えてください。
回答|労働保険と社会保険の加入手続きが必要になります。
法人を立ち上げると、労働保険と社会保険の加入手続きが必要になります。
具体的に、労働保険とは労災保険と雇用保険を指し、社会保険は健康保険と厚生年金保険を指します。
それぞれの加入手続きについて解説していきます。
労働保険の加入手続き
労働保険の手続きは労災保険、雇用保険の順番に行うことになります。順を追って解説します。
まず事業所の所轄の労働基準監督署に労災保険の成立の届出を行います。
成立の届出には以下の書類が必要になります。
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
上記の資料は届出に必須の書類となります。その他添付資料として、事務所の賃貸借契約書や会社の登記簿謄本が必要となる場合もございます。
労働基準監督署の窓口の担当者が詳しく教えてくれますので、それほど心配は必要ありません。
雇用保険の手続き
労働基準監督署の手続きが終わると、ハローワークにて雇用保険の手続きを行います。
手続きには下記の書類が必要になります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
なお、社長(役員)のみで従業員がいない場合は、労働保険の手続きは不要です。
従業員を一人でも雇用する場合に必要となるものです。
社会保険の加入手続き
労働保険とは違い、社会保険は健康保険・厚生年金保険を一緒に手続きを行うことができます。
また、社長(役員)のみで従業員がまだいない場合でも、社長が社会保険の加入要件を満たす場合は手続きが必要となる点も労働保険との相違点です。
なお、法人設立したばかりで、役員報酬を0円にする場合は、社長が社会保険の加入要件を満たさないので、社会保険の手続きは不要になります。
社会保険の加入手続きは下記の書類を所轄の年金事務所へ提出することで行います。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険資格取得届
社会保険の手続きの場合も、上記の資料とは別に添付資料として、会社の登記簿謄本や法人番号通知書、被保険者となる者の年金手帳やマイナンバーカードが必要となります。
また、労働保険や社会保険の手続きには、それぞれ下記のように書類の提出期限が設けられています。
・保険関係成立届・・・保険関係成立日から10日以内
・概算保険料申告書・・・保険関係成立日から50日以内
・雇用保険適用事業所設置届・・・雇用保険の適用対象となる従業員を雇用した日から10日以内
・雇用保険被保険者資格取得届・・・被保険者となった日の翌月の10日まで
・健康保険・厚生年金保険新規適用届・・・事実の発生日から5日以内
・健康保険・厚生年金保険資格取得届・・・事実の発生日から5日以内
しかし実際には期限を過ぎても手続きは行ってくれます。ただ、可能な限り早めに届出を行うに越したことはありません。
心配な場合は、専門家(税理士や社労士)に依頼するのも一つの手です。
ぜひ検討してみてください。

質問:社会保険の補償内容を簡単で良いので教えてほしいです。
とある田舎で設計事務所を営んでいる者です。
法人設立後まだ2期目にさしかかったばかりの、まだまだ新米経営者ですが、従業員も数人抱えていて、もっとがんばらなきゃと思っているところです。
ところで従業員を雇用すると、様々な社会保険の加入義務が発生するので、手続き自体はやりましたが、実はそれぞれの補償内容をよくわかっていません。
社会保険の補償内容を簡単で良いので教えてほしいです。
回答|企業が従業員を雇用した場合に加入が義務付けられている社会保険は下記の4種類
企業が従業員を雇用した場合に加入が義務付けられている社会保険は下記の4種類となります。
・労災保険
・雇用保険
・健康保険
・厚生年金保険
※ここでいう社会保険は広義の社会保険を指します。
厳密な意味では労災保険、雇用保険は狭義の労働保険を指しますので、念のため補足です。
それぞれについて、補償内容を解説してきます。
労災保険
労災保険は正式名称を労働者災害補償保険といい、労働者が業務上、もしくは通勤途上において傷病を負った場合に必要な給付を受けることができるものです。保険料は全額を事業主が負担するので、労働者の負担はありません。
労災保険の給付内容は大きく分けて下記のようになります。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料・葬祭給付
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付
たとえば、業務中の傷病が原因で病院や診療所に診てもらう場合も、原則として被災労働者は治療費を負担する必要はありません。
この仕組みを療養補償給付といい、治療費は労災保険の保険者である政府が負担してくれます。
なお労災保険の補償内容については下記の記事でも解説していますので、参考にしてください。
【参考記事:業務災害補償保険と労災の違いを分かりやすく現役の社労士が解説いたします。】
雇用保険
雇用保険は、離職者に対する生活保障のための給付や、職業訓練等の費用の一部を負担する等、離職者が安心して就職活動ができるよう様々な給付をすることで、離職者の生活の安定や就職の促進を図る保険です。
雇用保険の保険料は一定割合を従業員も負担する仕組みとなっており、給与から天引きすることで負担しています。
雇用保険の給付は大きな分類として下記のようになっています。
・失業等給付
・育児休業給付
・雇用保険二事業
上記からさらに各要件に細分化される仕組みとなっており、給付内容は非常に多岐にわたります。
なかでも一般的なものは、失業した場合にハローワークで失業の認定を受けた場合に受給できる生活保障のための給付です。
それが失業等給付の基本手当といいます。
なお、雇用保険の給付内容については下記の記事でも解説していますので、参考にしてください。
【参考記事:雇用保険の目的や受け取れる条件は?加入要件を詳しく解説!】
健康保険
健康保険は業務外の事由で傷病を負った場合に、必要な給付を受給することができます。
※業務上の事由に該当する場合は労災保険からの給付となります。
保険料は労使折半で、従業員負担部分は給与天引きされる仕組みとなっています。
健康保険の給付内容は下記のようになります。
・療養の給付
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費
・療養費
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・移送費
・傷病手当金
・出産育児一時金
・出産手当金
・埋葬料、埋葬費
上記のように、健康保険も様々な保険給付が設定されています。
多くの人にとって一番馴染みがあるのは、病院や診療所で診てもらったときの、費用負担を3割に抑えることができるという療養の給付でしょう。
なお、健康保険の給付内容についても下記の記事で解説していますので、参考にしてください。
【参考記事:病気やケガをしたときの受け取れる給付は?社会保障制度を解りやすく解説】
厚生年金保険
厚生年金保険は被保険者の老齢、障害、死亡といった事由が発生した場合に必要な給付を行う保険です。
保険料は労使折半で、従業員負担部分は給与天引きされる仕組みとなっています。厚生年金保険の給付は下記となります。
・老齢の給付:老齢厚生年金
・障害の給付:障害厚生年金
・死亡の給付:遺族厚生年金
年金というと定年退職後に生活保障目的にもらうもの、というイメージが一般化されていますが、老齢以外でも障害や死亡を事由に給付されるのです。
なお、厚生年金保険の給付内容についても下記の記事で解説していますので、参考にしてください。
【参考記事:公的年金の死亡・傷害・老齢で受け取れる!受け取れない?年金を解りやすく解説します。】
質問:従業員が退職した場合の手続きはどのようなものがあるのでしょうか。
サービス業を営んでいます。先日、長く勤めてくれている従業員から退職の意向がある旨の話がありました。
別にやりたいことができたからという理由だということなので、寂しい気持ちはありますが、夢に向かって応援したいと思い、退職の背中を押すことにしました。
ところで、従業員が退職した場合の手続きはどのようなものがあるのでしょうか。
本人に迷惑かけたくないので、しっかり漏れのないよう手続きしたいと思い、質問しました。
回答|社会保険や税金関係と会社側で行うべき手続きは多岐にわたります。
従業員が退職した場合、会社側で行うべき手続きは多岐にわたります。今回は社会保険や税金関係に絞って解説します。
社会保険、税金関係で行うべき手続きは下記となります。
・社会保険の手続き
・雇用保険の手続き
・所得税の手続き
・住民税の手続き
以下、それぞれについて解説します。
社会保険の手続き
従業員が退職した場合、社会保険の資格喪失手続きをする必要があります。資格喪失日(従業員退職日の翌日)から5日以内に、以下の書類・添付資料を事業所管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
・健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届
・健康保険証(本人分、被扶養者分含めて)
資格喪失日から5日以内とあまり日数の余裕がないので、退職する被保険者にはあらかじめ健康保険証を家族分も含めて用意しておいてもらう等、早めの対応が必要です。
雇用保険の手続き
社会保険同様、雇用保険についても資格喪失の手続きが必要になります。
退職日の翌々日から起算して10日以内に以下の書類・添付資料を事業所管轄のハローワークに提出する必要があります。
・雇用保険被保険者喪失届
・労働者名簿
・出勤簿又はタイムカード
・雇用契約書等
・離職証明書(※)
・賃金台帳(※)
・離職理由を確認できる書類(※)
(※)離職票を必要とする場合に必要となります。
所得税の手続き
所得税の手続きとしては、源泉徴収票の発行が該当します。
源泉徴収票には退職する日の属する年の1月1日以降で会社に雇用されている期間に支払った給与・賞与額と、控除された社会保険料、所得税等が記載されています。
退職従業員が転職する場合には、転職先で必要となりますので、早めに発行してあげましょう。
住民税の手続き
住民税を特別徴収(給与天引き)している場合、従業員の居住地の自治体に「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、退職日の属する月の翌月10日までに提出する必要があります。また、退職日によって住民税の処理は、以下の通り異なります。
・1~5月退職:5月までの住民税を一括徴収。
・6~12月退職:退職月の住民税は特別徴収。翌月以降は普通徴収へ切替。ただし希望すれば一括徴収も選択可。
退職月によって対応が異なること、また従業員の希望が反映できるケースもあるので、取り扱いには注意が必要です。
質問:法人が社会保険の手続きを怠るとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
飲食店を経営しています。法人化して2年ほど経ちます。
あまり大きな声では言えないのですが、実は社会保険の手続きを何もしていません。
必要なのはわかっているのですが、日々の忙しさを言い訳に、怠っている状況です。
法人が社会保険の手続きを怠るとどのようなデメリットがあるのでしょうか?教えてください。
回答|加入の義務を満たさない場合は、罰則やデメリットが生じます。
法人が一定の要件を満たすことで社会保険に加入することは、法律で定められた義務です。
その義務を満たさない場合は、罰則やデメリットが生じます。罰則の具体的な内容や、考えられるデメリットをいくつか紹介します。
6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
社会保険に加入していないことに関し悪質とみなされると、6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科される可能性があります。
悪質とみなされるケースは、何度も加入指導を受けているのにもかかわらず手続きをしなかったり、虚偽の申告を行ったりするケースが該当します。
最大過去2年間分の保険料を遡って徴収される
社会保険の未加入が発覚し強制適用となった場合、最大で過去2年間分の保険料を遡って徴収される可能性があります。
2年間分ともなると、資金繰りに大きな影響が出ることは言うまでもありません。
さらに、過去2年間で退職している従業員がいた場合、その従業員の負担分も会社で支払わなければなりません。
退職した従業員に請求することは可能ですが、連絡が取れない等、請求が困難な状況は十分に考えられます。
ハローワークに求人が出せない
社会保険に加入義務があるのにも関わらず、加入手続きを行っていない事業所は、ハローワークに求人を出すことができません。
優秀な従業員の確保のための手段が制限されるばかりか、対外的にみても信用のない企業とみなされ、企業存続において死活問題になりえます。
助成金の申請に影響が出る
助成金を申請するにあたって、社会保険の加入有無が審査対象になっているものもあります。
未加入の場合は当然そのような助成金を申請することができなくなります。
加入義務があるのにも関わらず加入手続きをしていないなんてケースは問題外でしょう。
このように、社会保険の加入手続きを怠ると様々なデメリットが想定されます。
社会保険に加入することで、会社にとっては法定福利費の負担が増えることは事実です。
しかし手続きを怠ることで、法定福利費以上の経済的ダメージを被る可能性もあります。
そして、そもそも社会保険の手続きは法的な義務です。
しっかり手続きしましょう。
手続きについて不明な場合は、社会保険労務士等の専門家に相談するのもひとつの手です。気軽に相談してみましょう。
- インスタ用●
- 法人を立ち上げると社会保険の手続きが必要になります。具体的には労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険です。
- 労災保険は労働者の業務上、もしくは通勤途上において傷病を負った場合に必要な給付を受けることができるものです。給付内容は以下の通り。
療養(補償)給付
休業(補償)給付
障害(補償)給付
遺族(補償)給付
葬祭料・葬祭給付
傷病(補償)年金
介護(補償)給付
二次健康診断等給付
- 雇用保険は、離職者に対する生活保障のための給付や、職業訓練等の費用の一部を負担する等、離職者が安心して就職活動ができるよう様々な給付をすることで、離職者の生活の安定や就職の促進を図る保険です。給付内容は以下の通り。
失業等給付
育児休業給付
雇用保険二事業
- 健康保険は、業務外の事由で傷病を負った場合に、必要な給付を受給することができます。給付内容は以下の通り。
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
訪問看護療養費
療養費
高額療養費
高額介護合算療養費
移送費
傷病手当金
出産育児一時金
出産手当金
埋葬料、埋葬費
- 厚生年金保険は、被保険者の老齢、障害、死亡といった事由が発生した場合に必要な給付を行う保険です。給付内容は以下の通り。
老齢の給付:老齢厚生年金
障害の給付:障害厚生年金
死亡の給付:遺族厚生年金
- 社会保険の手続きを怠ると様々なデメリットがあります。具体的には下記のようなものです。
6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
最大過去2年間分の保険料を遡って徴収される
ハローワークに求人が出せない
助成金の申請に影響が出る
- 社会保険の手続きは法律で定められた義務です。しっかり手続きするようにしましょう。